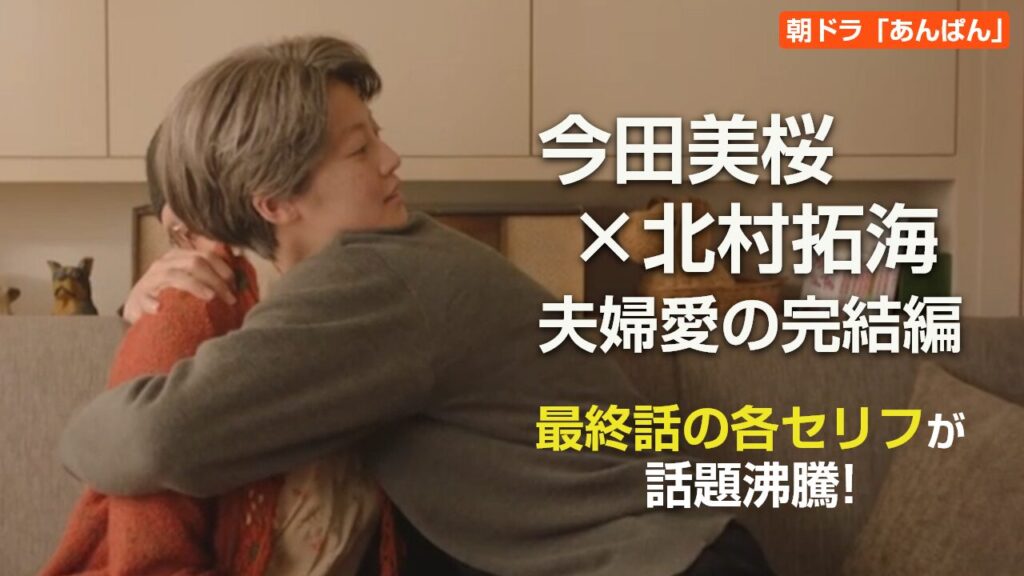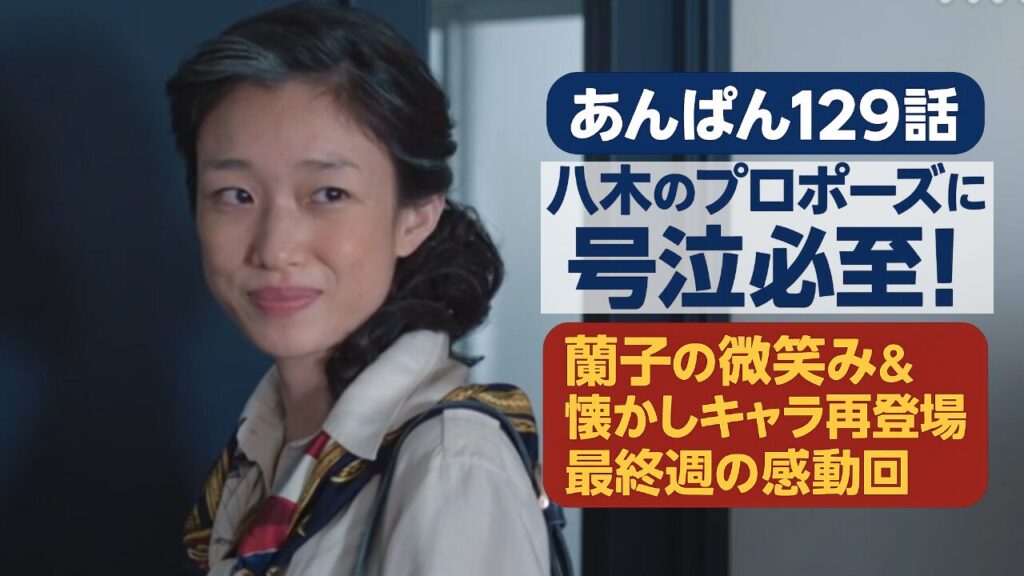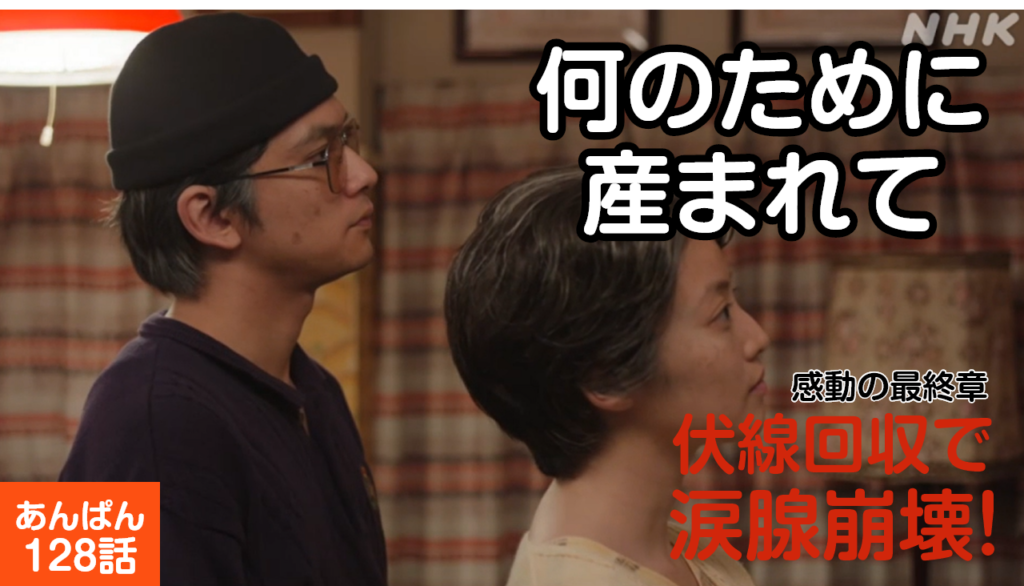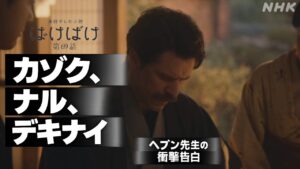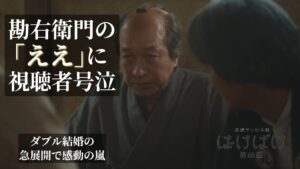朝ドラあんぱん相関図②
引用元:NHK
戦後の混乱期、新たな希望の光が差し込んだ67話
朝ドラ「あんぱん」第14週67話「幸福よ、どこにいる」では、高知新報が夕刊発行を申請し、東海林(津田健次郎)が編集長に抜擢される重要なエピソードが描かれました。戦時中の言論統制から解放され、真実を伝える新聞作りへの挑戦が始まります。
朝ドラ『あんぱん』第14週第67話 あらすじ
物語は高知新報の会議室から始まります。進駐軍の言論の自由政策により、多くの新聞社が新聞発行を奨励される中、高知新報も夕刊発行を決定。遊軍記者だった東海林が編集長に任命され、岩清水信司(倉悠貴)とのぶを部下として選びます。
倉庫を編集部にする東海林の指示で、岩清水信司とのぶは片付けに奔走。「どんな夕刊にすべきか」と構想を練る中、のぶが記者への想いを語ると、東海林の目に涙が浮かびます。戦時中に嘘まみれの記事を書いてきた反省から「嘘偽りのない生の声」を目標に掲げ、3人の結束が生まれました。
一方、復員した嵩は健太郎、ごんたと共に進駐軍の廃品を扱う雑貨店を開業。浅田家ではメイコがラジオの「のど自慢」に聞き入るシーンで締めくくられます。戦後復興への希望と、それぞれの新たな出発を描いた印象的な回となりました。
東海林編集長誕生!津田健次郎の迫真演技に視聴者感動
朝ドラ「あんぱん」第14週67話は、高知新報の会議室シーンから始まりました。戦後復興期の新聞業界に新たな風が吹く重要な転換点となる回です。
「このたび、わが社では夕刊発行の申請をする」
社長の宣言により、高知新報の新たな挑戦が始まります。進駐軍による言論の自由政策により、戦時下の「1県につき1紙」の縛りから解放され、より多くの新聞社が新聞発行を奨励される時代背景が丁寧に説明されました。
そして注目の人事発表。遊軍記者だった東海林(津田健次郎)が夕刊の編集長に抜擢されます。
「お前が決めろ」
社長から人員選考を任された東海林は、迷わず岩清水信司(倉悠貴)とのぶを選択。この場面での津田健次郎の表情には、責任の重さと同時に新しい挑戦への期待が込められていました。
SNSの反応

東海林編集長!遊軍記者で、すぐに夕刊チーム編成するところ素敵、メンバーは信頼されてると感じるよね。また、津田健次郎さんの声がいいんだよな。
視聴者が津田健次郎の演技力と声の魅力を改めて実感したシーンでもありました。
津田健次郎の「猫の手」セリフが話題
編集部となる倉庫で片付けをする岩清水信司(倉悠貴)とのぶ。そこへ東海林の一言が印象的でした。
「猫の手も借りたいにゃー」
このセリフの言い回しから、「津田健次郎の方言の使い方が自然すぎる」という投稿も見られました。高知弁の温かみを感じさせる演技は、戦後の人々の絆を表現する重要な要素となっています。
涙を浮かべる東海林の心境変化
最も感動的だったのは、のぶが記者への想いを語った後の東海林の反応です。カメラは東海林の表情をアップで捉え、目に浮かぶ涙を丁寧に映し出しました。
このシーンの演出意図について考察すると、戦時中に嘘まみれの記事を書いてきた東海林の後悔と、新しい時代への希望が交錯する複雑な感情が表現されています。津田健次郎の繊細な演技により、セリフに頼らずとも東海林の内面が視聴者に伝わる秀逸なシーンでした。
「嘘偽りのない生の声」-戦後新聞界への痛烈なメッセージ
67話で最も重要なメッセージが込められたのが、東海林の新聞観を表すシーンです。
「新聞を信用していない。嘘ばっかり書く新聞にほとほと愛想が尽きた」
遠藤の痛烈な批判から始まる一連の会話は、戦後新聞界が直面していた信頼失墜の現実を浮き彫りにしました。
「戦時中は戦争を賛美して推奨して、戦争が終わったらそれまでのこと全部なかったような顔して正反対のことを書く。そんな嘘まみれの新聞を誰が信じるか」
この東海林のセリフは、現代のメディア不信にも通じる普遍的な問題を提起しています。SNSでは現代の報道への批判的な意見も多く見られました。
現代視聴者の反応



今日のあんぱん「新聞は嘘ばっかり」と東海林編集長が言ってたけど、偏向報道ばかりのNHKのドラマが言ってもなあ…内部皮肉ってやつか?
戦時中メディアへの批判的視点
東海林自身も戦時中の記事について言及します。
「戦争協力記事を書いてきた」
戦後日本のメディア関係者が共通して抱えていた罪悪感を代弁しています。脚本は単純な善悪論ではなく、時代に翻弄された個人の苦悩を丁寧に描写しています。
そして東海林が掲げた理念
「俺らが書くのは嘘偽りのない生の声だ。戦後の今を生きる人々の声だ」
このセリフは、新しい時代の新聞作りへの決意表明であり、視聴者にも強い印象を与えました。
記者の使命感を描く脚本の巧妙さ
「否定されることを恐れるな。記者の鉄則だ」
東海林のこの言葉は、多くの視聴者の心に響きました。
SNSの感動的な反応



「否定されることを恐れるな」そんな事いってくれる上司いなかったな。”恐れずに間違えてみろ、大丈夫だから”って言ってくれてるみたい
現代社会でも通用する普遍的なメッセージとして受け取られています。SNSでも「理想の上司像」として東海林編集長を挙げる投稿が見られました。
のぶの記者魂覚醒シーン-教師時代の後悔から生まれた決意
のぶの成長物語における重要な転換点となったのが、この67話です。編集長就任を告げられた東海林からの問いかけに、のぶは自分の想いを率直に語りました。
「記者は、どこまで行っても、世の中に問い続けるしかないんじゃないでしょうか」
この言葉の背景には、教師時代の深い後悔があります。
「教師をしていたとき、学校で間違ったことをたくさん子どもらに教えてきました。それで戦争が終わったら、全部なかったような顔をして」
教師から記者への転身
のぶの告白は、戦時中の教育現場の実情を物語る貴重な証言でもあります。国家が推進する教育方針に従わざるを得なかった教師たちの苦悩は、当時の多くの教育者が抱えていた共通の問題でした。
「そんな私が自分の言葉で記事を書いて、人の心に訴えかける」
この決意表明に、東海林が感動して涙を浮かべるシーンは、67話のクライマックスの一つです。カメラワークも効果的で、のぶの表情から東海林の表情へとスムーズに移行し、二人の心の通い合いを視覚的に表現していました。
視聴者の共感



夕刊のメンバーにのぶも加わることになりました。のぶの眼は輝いてました。夕刊の内容は不明ですが、未定義の未来をはじめるということは、自分達自身も新しく再定義することができる期待に胸が熱くなっている気がします。
のぶの成長物語の転換点
これまでのぶは、病気で夫を失い、戦争で子ども兵士へと駆り立て、様々な困難に直面してきました。しかし67話では、過去の経験を糧として新しい道を歩む決意を固めました。
「精一杯頑張ります」
のぶのこの言葉には、単なる意気込み以上の重みがあります。戦時中の自分を否定するのではなく、その経験を活かして真実を伝える記者になろうとする姿勢は、戦後復興期の多くの日本人の心境を代弁しています。
SNSでは「のぶの成長が朝ドラらしくて感動する」という投稿も多く、朝ドラの王道である女性の自立と成長を描く物語として高く評価されています。
進駐軍廃品回収ビジネス-嵩たちの新事業が描く戦後経済
一方、復員した嵩の物語も新たな展開を見せました。健太郎と共に始めた進駐軍の廃品回収事業は、戦後経済復興の一面を描く重要な要素です。
「今日も豊作やね」
健太郎のこのセリフからは、新事業への手応えを感じ取れます。さらにごんたも仲間に加わり、事業の拡大が期待されます。
「アメリカさんにとってはゴミなんだよ。アメリカさんが使わなくなったもの、そういうのも捨てちゃうんだもん。そりゃ、日本も負けるわけだよ」
廃品回収の時代背景
このセリフは、敗戦国日本と占領軍アメリカの経済格差を端的に表現しています。アメリカ軍が不要として廃棄するものが、日本人にとっては貴重な商品になるという現実は、当時の日本の物不足を物語っています。
視聴者の時代考察



古道具店、嵩と健ちゃんだけだと美意識で集めた商品だけになっちゃいそうだから、コン太くんが仲間になってくれて良かった😄実際、今日コン太くんが持ってたの飯盒に見えた
細かい小道具にも注目する視聴者の鋭い観察力が、ドラマの時代考証の精密さを証明しています。
アメリカ”さん”の呼び方に注目
特に注目されたのが、嵩の「アメリカさん」という呼び方でした。
SNSで話題



戦後間もない時代は『アメリカ”さん”』って『さん』付けしてたんだよね⋯そして倉くんが一瞬見せた笑顔にノックアウトされた
敗戦直後の日本人の複雑な心境を表現する演出として、多くの視聴者が注目しました。占領軍への敬意と恐れ、そして依存の入り混じった感情が「さん」付けに込められています。
メイコのラジオ聴取が希望の象徴-「のど自慢」シーンの演出意図
67話のエンディングを飾ったのは、浅田家でのメイコのシーンでした。畑仕事から帰ってきたメイコが、ラジオの「のど自慢」に聞き入る場面は、戦後復興期の日本社会における娯楽文化の復活を象徴しています。
ラジオから流れる「リンゴの唄」に聞き入るメイコの姿は、多くの視聴者に感動を与えました。
ラジオ文化の浸透
ラジオの「のど自慢」番組は、戦後日本の娯楽文化復活を象徴する重要なアイテムです。戦時中は「贅沢は敵だ」として制限されていた娯楽が、戦後になって徐々に復活していく過程を描いています。
メイコが番組に夢中になる様子は、音楽への憧れと同時に、東京への憧れも表現しているように見えます。SNSでは「メイコの歌手デビューフラグ」という考察も見られました。
メイコの歌手への道筋
「上手い人も下手な人もおる。この人はなかなか上手やね」
ラジオから聞こえる司会者の声に、メイコは自分も参加したいという気持ちを抱いているようです。
視聴者の予想



メイコ、まさか・・・歌が好きなメイコ、いよいよ東京への巻かにゃ



メイコ歌手デビューで健ちゃんがメイコのマネージャー。のぶが『高知からスター誕生』を夕刊の記事にする。こんなぶっ飛び展開も東海林編集長ならあり得る🤔w
視聴者の想像力をかき立てる演出として、のぞ自慢シーンは効果的に配置されていました。
SNSで話題の名セリフ・名シーン総まとめ
67話は名セリフ・名シーンの宝庫でした。特に印象的だった要素をまとめてみます。
津田健次郎の演技力
「つまらん記事やったら全部ボツにするからな」
厳しい編集長としての一面を見せる東海林ですが、津田健次郎の演技により威圧感ではなく愛情を感じる絶妙な表現でした。
視聴者の評価



悲劇ばかり続く中でようやく光が差してきたような展開。ツダケンがいる安定感。記者になったのぶの今後が気になる。
方言の魅力



「津田さんの語尾のにゃーはもう文蔵さんにしか聞こえない」
高知弁の温かみが、戦後復興期の人情豊かな雰囲気を演出しています。
時代考証の精密さ
小道具から台詞回しまで、戦後間もない時期の描写が丁寧に再現されており、視聴者の没入感を高めています。
「あんぱん」第14週67話は、戦後復興期の希望と決意を描いた印象的な回でした。東海林編集長の涙、のぶの記者魂覚醒、メイコのラジオ聴取という3つの要素が絡み合い、新たな時代への出発を力強く描いています。
津田健次郎をはじめとする俳優陣の演技力、時代考証の精密さ、そして現代にも通じる普遍的なメッセージにより、多くの視聴者の心を捉えた秀作エピソードとなりました。SNSでの反響の大きさも、この回の完成度の高さを証明しています。
次回以降、東海林率いる夕刊チームがどのような記事を世に送り出すのか、そしてメイコの歌手への道はどう展開するのか、ますます目が離せない展開が期待されます。
第14週67話の見どころ・伏線まとめ
- 東海林編集長誕生の意味:遊軍記者から編集長への抜擢は、戦後復興期における人材の適材適所を表現。津田健次郎の演技で東海林の責任感と期待感を巧妙に描写
- 「嘘偽りのない生の声」の理念:戦時中のメディア批判を込めた新聞作りの決意表明。現代のメディア不信にも通じる普遍的メッセージとして視聴者に強い印象を残す
- のぶの記者魂覚醒:教師時代の後悔から生まれた真実を伝える決意。朝ドラらしい女性の自立と成長物語の重要な転換点として描かれる
- 進駐軍廃品回収事業の展開:嵩・健太郎・ごんたのチーム結成により事業拡大の兆し。戦後経済復興の一面を描く重要な伏線として機能
- メイコの音楽への憧れ:ラジオ「のど自慢」への聞き入り方から、歌手への道や東京進出の可能性を示唆。今後の展開への重要な布石
- 夕刊チームの結束:東海林・岩清水信司(倉悠貴)・のぶの3人体制で始まる新聞作り。戦後復興期の新たな出発を象徴し、今後の物語展開の中核となる要素