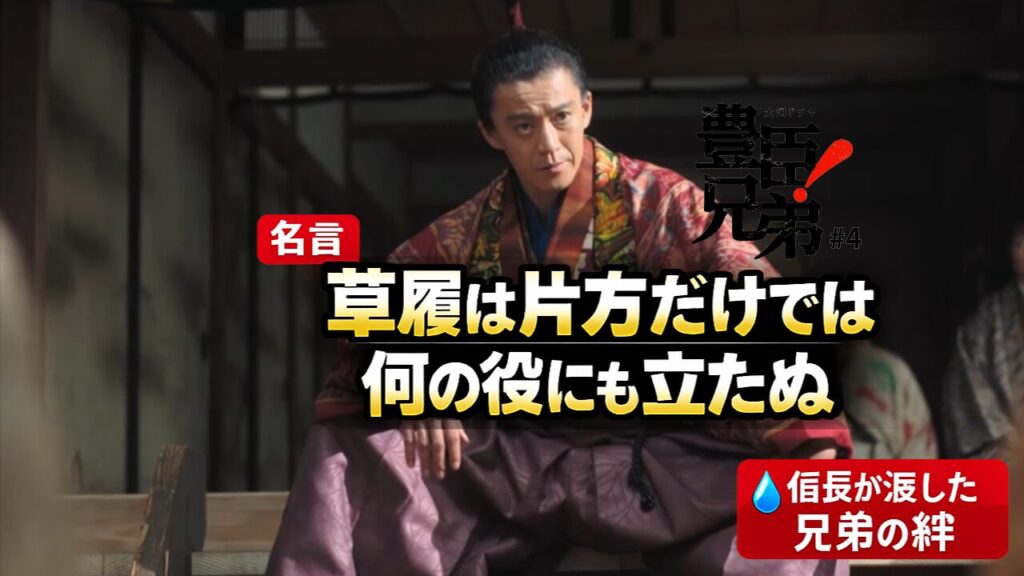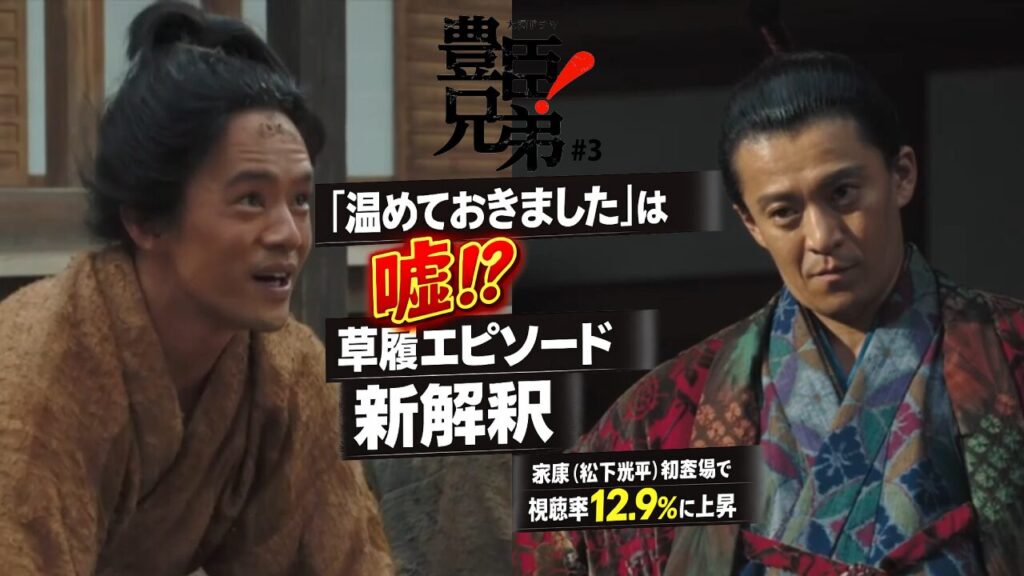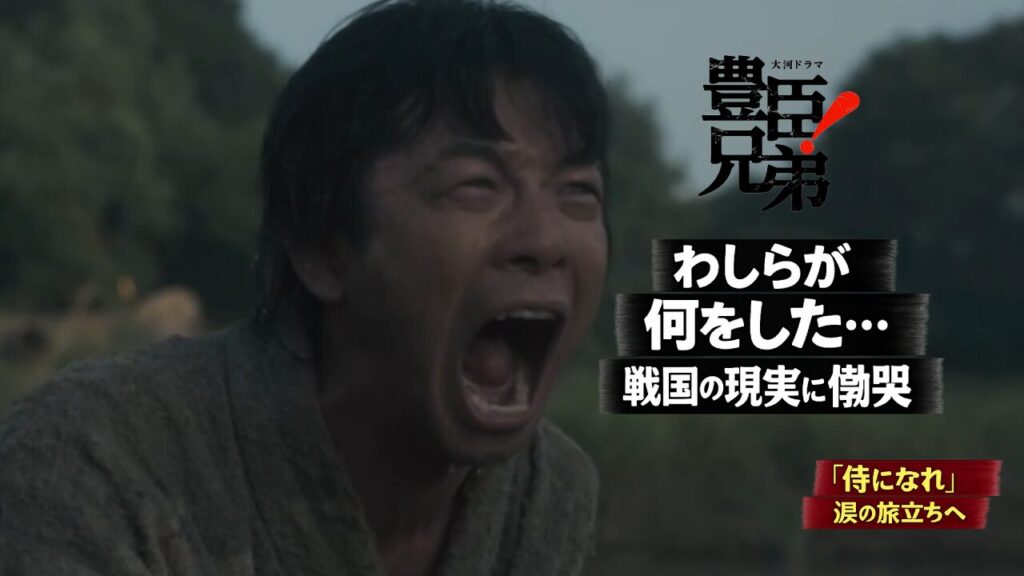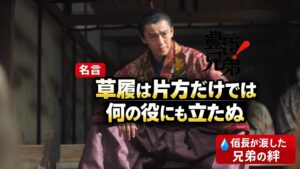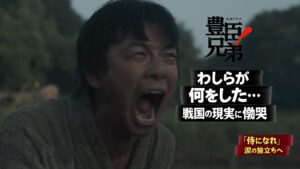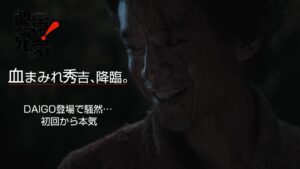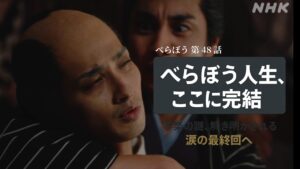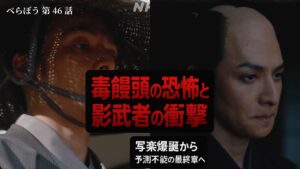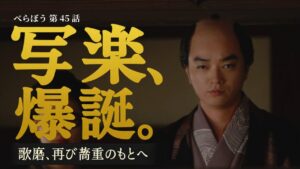「べらぼう」第16話は、前話で描かれた“毒入り手袋”事件の結末と、平賀源内の「死」をめぐる真相が描かれた必見の回だった。
手袋による殺人計画、跡を消された証拠、そして首もとに落ちる影。源内の死は「自殺」とされる一方で、ドラマは「本当にそうだったのか?」と問い掛ける。
そして、あの手袋事件を「非実の成分を保ちつつ、真実を伝える」静かな抗議として文章や舞台で伝えていこうとする講習道の重三郎の姿も光りました。
本記事は「源内は本当に死んだのか?」「手袋事件の真相」「講習道としての重三郎」というテーマを紹介しながら、Xで話題になったセリフや続く物語への期待を織り交ぜ、耕き込んだ考察を紹介します。
源内の死~自殺か他殺か?残された“原稿”が語るもの
この回、最大のショックは「平賀源内、死す」の一報でした。しかし、正確には「自殺」であることが発表されるなか、議論は持続されます。


「原稿が1枚だけ残っていて、あとは持ち去られていた。つまり、あの場に誰かがいた証になるのではないかと」 「源内先生が飲める酒を飲み、竹光を持ち、その上近くの人間を殺めたとされる…そんなことがあると思いますか?」
「自殺」という決着を望んだ人間は誰なのか。なぜそこまでして“死”という幕を引かなければならなかったのか──。
この「不完全な死」の感覚に、Xでも深い疑念や考察が多数つぶやかれていました。
「誰も遺体を見ていないんだよね?」
「罪人は、ものを確認されないまま埋められる。これは戦略じゃん?」
とどめは白湯?かな。砒素かトリカブトでも入れたか。罪人の遺体は引き渡さないという取り決めを利用した隠蔽工作。最初から全て計算通りに動かしているのはやはりあの傀儡師(と大奥総取締)か。#べらぼう
— インスマウス (@innsmouthjapan) April 20, 2025
平賀源内、田沼が逃してどこかで生き延びていてほしい。名前を変えてひっそり生きたみたいな。誰かの遺体を身代わりにして死んだことにして片付けるくらい田沼に小細工してほしい。#べらぼう
— marinext19 (@mari_messages) April 21, 2025



源内の死を前にしては、「そんな人がなぜ」「まだやり残したことがあったはず」と、胸が締め付けられる想いでした。
人は、従うように見せて、ほんの少しのことで「存在ごと」消されてしまうものなのか──。 この物語が不完全なままに残されたこと。それを受け入れようとする人々の姿に、歴史と向き合うことの苦しみと重みを感じずにはいられませんでした。
“毒を帯びた手袋”は誰が仕組んだのか
事件の核心にある“毒手袋”。第15話で西の丸様の死因として疑惑が浮上したこのアイテムは、今話でより一層不穏な存在として描かれました。
「手袋がない……誰かが持ち去ったということはございませんか?」 「田沼様から急ぎ注文を受けて、その手袋を作ったのは評判の“頃”だと──」
このやり取りが示すのは、政治の中枢にいる者たちによる“計画的な道具化”。 贈り物という形で届けられた手袋が、時の権力を揺るがす毒として働く──それが仕組まれていたとしたら、陰謀のスケールは一層広がります。
「触れた者は必ず死ぬ。『死を呼ぶ手袋』といったところにございますか」 「送るものを“渡りに船”と考えた外道がいる」
Xでもこの“誰が仕組んだのか”という視点に考察が集中していました。
「田沼=黒幕説がいよいよ濃厚に?」 「手袋=呪具として機能してるの、ホラーだしサスペンスだし最高」
NHKドラマで描かれる一橋治斉は、久米明さんが演じた「天下御免」では、家治死去・田沼失脚の黒幕、蓮様が演じた「大奥」では戦慄の役柄🥶、そして満兄ちゃんが演ずる「べらぼう」も、胡散臭い匂いがプンプン🤣なので、ロクな扱いを受けていませんね😆
— ゴーシュ左利き (@0638823infosee1) April 21, 2025
べらぼう、尊号一件の時に出版サイドで報復する流れが見えたな。
— KBN (@J_A_M__) April 21, 2025
とすると田沼さま失脚辺りで黒幕判明してから鬼平からの情報リークか?
大河ドラマ『べらぼう』で黒幕キャラとなっている生田斗真演じる一橋治済。史実では77歳まで生きて勝ち逃げしたとされるが、出家した晩年の姿の肖像画を拝見する限り、目がやけに虚ろで余裕かました表情ではないな。人を多く殺めてきたのだから、相当メンタルが詰んでいたのでは。
— びっぐぴゅあ@知られざるシネマ (@bigpure2010) April 20, 2025
黒幕は治済か…田沼もまた転がされていたのか? #べらぼう #べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺
— 下北沢サウスウエスト (@shimokity) April 20, 2025
そんで生田斗真。芋食ってるだけなのに怖い。ホント何なの。どっから出してんの、その黒幕感。#べらぼう
— ちぃ (@1TV08Ot9duGGMo6) April 20, 2025
この“手袋”の設定には唸らされました。 ただのアイテムが、政治・人間関係・陰謀すべてを巻き込む“トリガー”になっている。また、「何気ない日常品が実は大きな影響を持つ」ことに気づかされますが、それに通じる怖さがあります。



「手袋」が一体何を象徴し、なぜここまで重要視されたのか。まだまだ明かされていない真実があるように思えてなりません。
重三郎が継ぐ「源内の意志」──書物と芝居で未来を描く
「源内は死んだ。でも、彼の志は消えていない」── この回で印象的だったのは、蔦屋重三郎が源内の死をどう受け止めたか、そして彼が“未来”に何を託そうとしているのか、という点です。
「楽しいことを考える。それが俺の流儀なんで。平賀源内を生き延びさせるぜ」 「この将来は、源内先生の本を出し続けることでさ、ずっと。それこそ俺が死んでも」
この言葉に胸を打たれた方も多かったのではないでしょうか。 源内の物語を“芝居”として残す、青本として世に広げる。その方法は、まさに「語ることで死者を生かす」行為。
「手袋を手にしたやつが、次々死んでく。でもその実、言い伝えに乗っかった悪党の仕業で──って話ですよ」
フィクションの皮を被って、真実を語る。それは“江戸の抗議文学”として、痛烈で、そして優しいやり方だったのかもしれません。



「死んだ人を、生かし続ける」という重三郎の行動に、深く共感しました。
「命を受け継ぐ」「想いを残す」ということを考える機会が増え、このエピソードはまさにその核心に触れていたように思います。 源内のように孤独に苦しみながらも、誰かのために知恵を尽くした人の思いを、どう継いでいくか。 それを“本”と“芝居”という手段で示した重三郎の決断に、心から敬意を抱かずにはいられません。
視聴者の声とSNSの考察まとめ
「源内の死」と「毒入り手袋」事件を中心に、SNS(特にX)ではさまざまな感想・考察が飛び交いました。とくに注目されたのは、次の3つの視点です。
死を信じない声、多数「誰も亡骸見てない」
「源内、ほんとに死んだの?」
「罪人は遺体も確認されない。これ逆手にとって逃げてる説あるぞ」
「“生きてる源内”にもう一度会いたい。次回以降も諦めない」
作中でも「芝居で語り継ぐ」描写があったため、視聴者の間でも「これは死ではなく演出」という捉え方が強まりました。
芝居仕立てのメタ構造に驚き
「“毒入り手袋”をそのまま浄瑠璃にする発想が最高」
「青本→芝居→観客へ。語ることで真実を伝えるって、まさに蔦屋の仕事だよね」
「現実が芝居になり、芝居が現実になる。この構造、エグいほど深い」
芝居と現実が交差するこの演出に「現代の報道やSNS文化にも通じる」と評価する声もありました。
「田沼=黒幕説」再燃の理由
「田沼の関与、ついに本格的に匂わせてきたな…」
「急ぎで手袋を作らせた“頃”が田沼と繋がってるとか、伏線張られすぎて震える」
「次に死ぬのは誰?もう誰も信じられん」
ドラマ序盤から権力と策略を握っていた田沼意次。その“見えざる手”が確実に物語を動かしているという分析も、多く見受けられました。
まとめ:源内は“死んだ”のではなく、“生かされ続ける”
第16話は、物語の転換点として非常に重要な回でした。
平賀源内という人物の“死”を描きながらも、重三郎はそれを“終わり”として描かない。「語り継ぐ」「残す」「芝居にする」という手段で、彼を“未来に送り出す”という選択をしたのです。
「源内先生が死んだとしても、その本を出し続けることで生き続けさせられる」
「それが、俺の役目だ」
源内は、決して派手なヒーローではありません。でも、知恵を尽くし、理不尽に苦しみながら、それでも誰かのために生きようとした。
その姿が物語として描かれ、書物として残り、舞台として語られる。
このセリフが象徴するように、記憶も想いも、語る人がいれば決して消えない。 そしてその語り部として、蔦屋重三郎という男の覚悟が、いま大きく前に踏み出そうとしています。