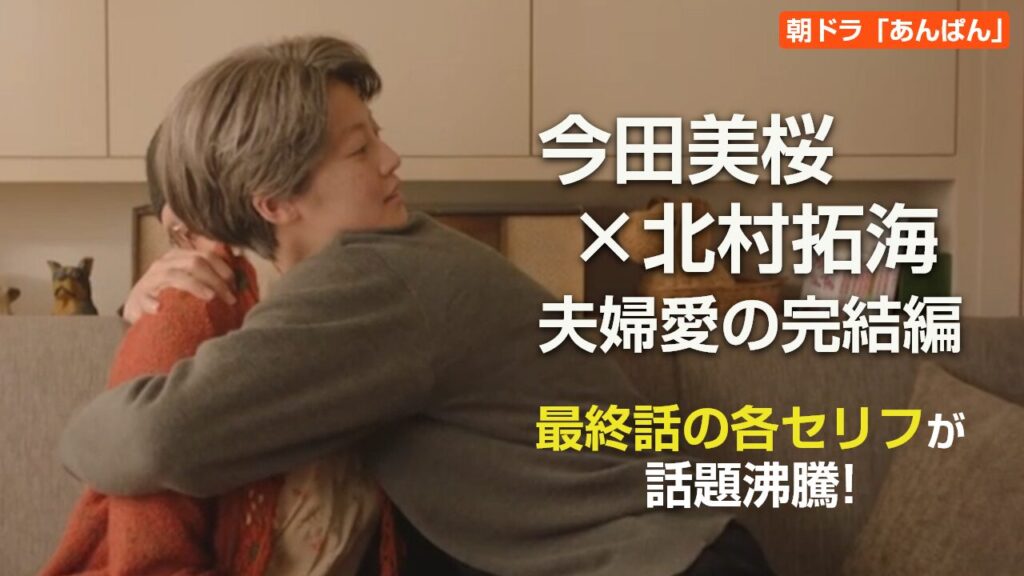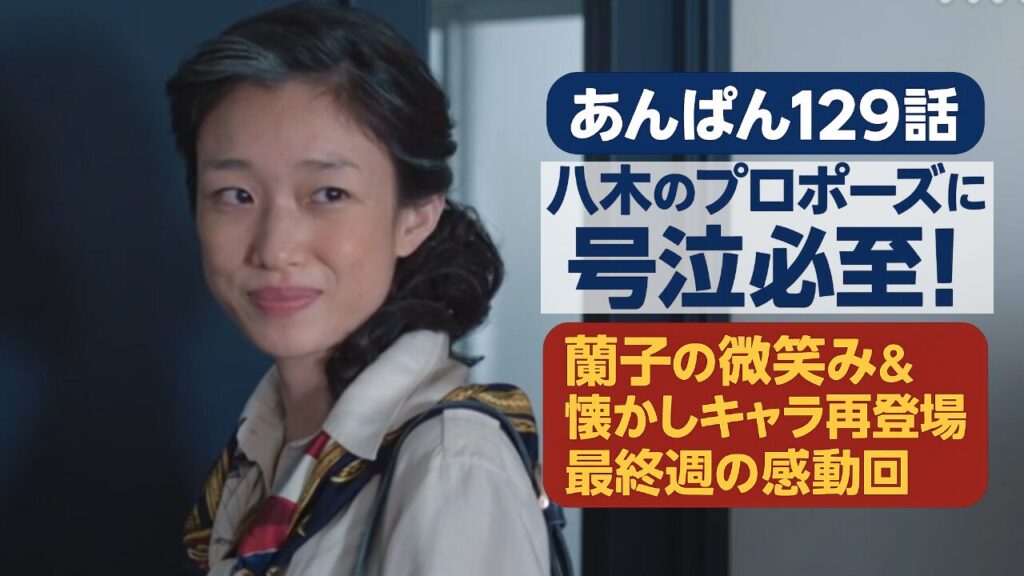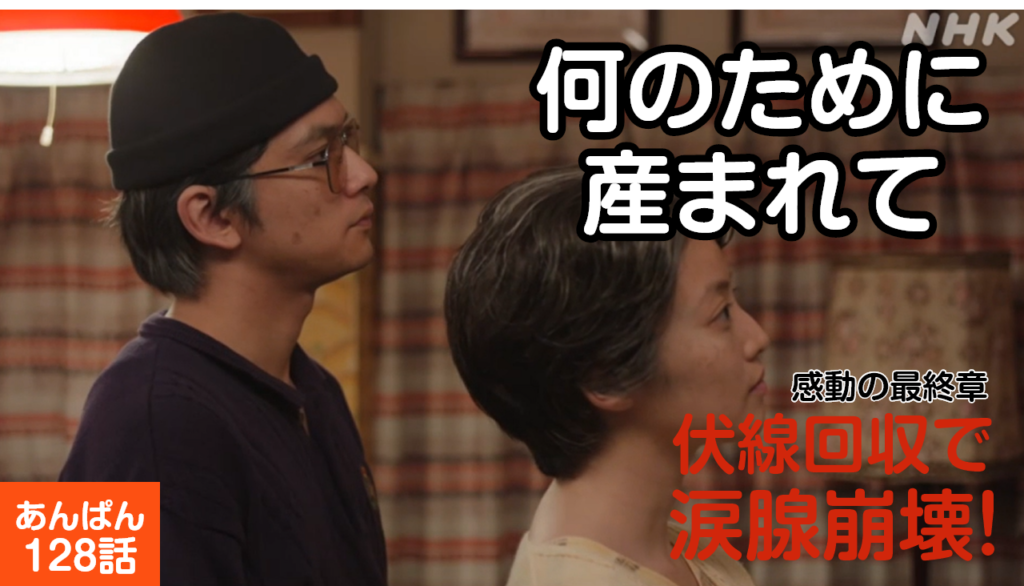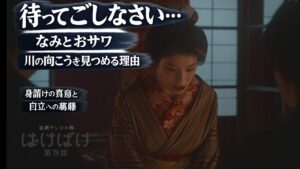朝ドラ「あんぱん」第17週83話「あなたの二倍あなたを好き」では、東京で活動するのぶ(今田美桜)と高知でスランプに陥る嵩(北村匠海)の距離感が描かれました。そして物語は昭和南海地震という歴史的な災害によって大きく転換します。
朝ドラ『あんぱん』第17週第83話 あらすじ
東京で戦災孤児の取材を続けるのぶは、牧徹子とともに施設の視察を行い、政治の力で困窮する子どもたちを救う方法を模索していました。一方、高知の月刊くじら編集部では嵩が深刻なスランプに陥り、東海林編集長が手塚治虫の漫画を見せても、その素晴らしさに圧倒されてかえって落ち込んでしまう始末でした。
そんな中、1946年12月21日午前4時19分に発生した昭和南海地震のニュースが東京にも届きます。高知出身の牧徹子も動揺し、のぶは家族と嵩の安否を心配します。高知新報社も混乱状態となり、嵩との連絡も取れない状況に。死者1200名という甚大な被害の中、のぶの心は愛する人たちへの想いで揺れ動きます。引き出しに眠る赤いバッグが象徴する二人の絆は、この災害を経てどのような変化を見せるのでしょうか。
のぶの東京奮闘記|戦災孤児への想いと政治への期待
東京に来て2か月が経ったのぶ(今田美桜)の日々は、まさに目の回るような忙しさでした。今回の83話では、戦災孤児たちの声を直接聞き取る場面から始まります。
「私のいたところは、牢屋みたいで鉄格子があって、朝早くに起こされて、寝るまでずっと畑で芋や麦を作って、ずっとひもじかった。だから逃げてきました」
子どもたちの証言は、戦後復興の影で置き去りにされた現実を浮き彫りにします。のぶが速記で書き取るこれらの声は、政治の世界に届けるべき生の叫びでした。牧徹子議員とともに進める調査は、単なる視察を超えて、具体的な政策提案につながる重要な活動となっています。
「何も食べさせてくれないから」というたけるくんの言葉は、子どもたちが置かれた無力な立場を端的に表現していました。のぶの丁寧な聞き取りは、この「声なき声」を政治の場に届ける重要な橋渡し役となっています。
牧徹子との連携で見えた希望の光
牧徹子議員は施設視察の経験を踏まえ、のぶにこう語りかけます。
「政治は貧しい人、恵まれない人にこそ手を差し伸べないといけない。それが原則です。戦災孤児はまず国が面倒見ないといけない」
この言葉は、個人の家庭での保護を第一とする当時の方針への批判でもありました。のぶの「これが個人に丸投げということですね」という指摘は、政治の本質を突いた鋭い観察でした。施設への予算配分を提案するという具体的な目標も示され、のぶの東京での活動に明確な方向性が見えてきます。
「それをもとに施設への予算配分を提案できるよ」という牧徹子の言葉からは、のぶの調査活動が実際の政策に反映される可能性が感じられました。のぶが速記技術を活かして社会貢献する姿は、多くの視聴者の共感を呼んでいます。
蘭子の成長と手紙に込められた温かさ
一方で、蘭子の経理の仕事が決まったという明るいニュースも届きました。東京での生活基盤が整いつつある中で、故郷への想いも忘れません。蘭子との手紙のやり取りは、離れていても続く絆を象徴する温かな場面でした。
「困っている子供たちの声を速記で書き取って、後でまとめて牧哲子先生に報告するのです。おねちゃんの速記、役に立っちゅうがやね」
蘭子のこの言葉は、のぶの活動への理解と支援を示しています。しかし、メイコが嵩の赤いバッグのことを伝えようとした際、蘭子が「やめちょき」と制止したのは印象的でした。
「それは2人の問題や」という蘭子の判断は、二人の関係に過度に介入することを避ける配慮が感じられます。この微妙な距離感の取り方は、蘭子の成長を感じさせる場面でもありました。
嵩のスランプと創作への葛藤|手塚治虫登場の意味
高知の月刊くじら編集部では、嵩(北村匠海)の深刻なスランプが続いていました。付録の仕事を任されても、ペンが進まない状況に編集部メンバーも心配していました。
「朝からずっと止まっていますよ」という岩清水の報告が示すように、嵩の創作活動は完全に停止状態でした。のぶが東京に行ってから2か月、物理的な距離が心理的な影響を与えているのは明らかです。
特に注目すべきは、東海林編集長が手塚治虫の漫画を見せる場面です。手塚治虫氏の漫画を東海林が渡して、嵩が面白いと言って火がつくと思ったら、「俺はダメだ~」とさらに落ち込んでしまいます。
この展開は、のちの「漫画の神様」である手塚治虫の作品に触れた嵩の反応として、非常に意味深いものでした。優れた作品に触れることで、かえって自分の力量の差を痛感してしまう嵩の心境は、創作者なら誰もが経験する葛藤です。
東海林編集長の優しさと厳しさ
優しく火をつけてあげようとしますが、却って沈み込んでしまう嵩を見て、怒鳴り散らしてしまいます。東海林編集長の人間臭い一面が描かれたこの場面は、視聴者からも「津田さんって演技が上質」との評価を得ています。優しさと厳しさを併せ持つ上司の姿は、多くの働く人々の共感を呼びました。
「やっぱりノブさんがおらんと駄目ながやないですか」
という琴子の言葉は、嵩のスランプの原因がのぶの不在にあることを示唆しています。創作活動における精神的な支えの重要性が、この場面から強く感じられます。
赤いバッグが示す二人の距離感
引き出しの中に眠る赤いバッグは、嵩とのぶの関係性を象徴する重要なアイテムです。嵩が一瞬固まるこの場面は、のぶへの想いの深さと、それを伝えられない自分への歯がゆさを表現していました。
SNSでは「引き出しに入った赤いハンドバッグはいつ渡せるのか」という視聴者の声が多く見られ、二人の関係の進展への期待が高まっています。また
「バッグは適当に保管してるとあっという間に傷むので、男が適当に保管してて10年近くもきれいなままというのは信じられん」
という現実的な指摘もあり、嵩がいかに大切に保管していたかが分かります。
このバッグは単なる物ではなく、嵩にとってのぶとの思い出と愛情を象徴する宝物となっているのです。スランプの中でもこのバッグを見つめる嵩の心境は、視聴者の心を強く打ちます。
昭和南海地震の衝撃|歴史的災害が変える運命
物語の後半、1946年12月21日午前4時19分に発生した昭和南海地震のニュースが東京に届きます。この歴史的な災害の描写は、物語に緊迫感をもたらしました。
1946年12月21日の現実
「昨日朝、西日本で大きい地震だ」
八木さんの言葉から始まる地震の報告は、戦後復興期における新たな試練の始まりでした。震源地は熊野灘、マグニチュード8.0という大規模な災害は、関西・四国地方を中心に甚大な被害をもたらしました。
「昨日早朝4時20分に発生した。熊野灘沖を震源とする大地震により、関西、四国地方を中心とする西日本の各地で甚大な被害」
ニュースの詳細な報告は、災害の規模の大きさを物語っています。視聴者からも
「日本国憲法公布から一ヶ月余り後の1946(昭和21)年12月21日午前4時19分、夜明け前の暗闇の中で西日本が大きく揺れ始めた」
という歴史的背景の解説が寄せられ、ドラマの時代考証への関心も高まっています。
「高知県でも100名以上の死者が出ているとのことです」
秘書からの報告は、高知出身の牧徹子を動揺させました。普段は冷静な牧徹子が「珍しく慌ててしまう」様子は、故郷への愛着の深さを物語っています。
のぶの動揺と家族への想い
「高知で地震があったそうです。大変なことになる心配」
のぶの動揺は、家族への想いと嵩への心配が入り混じったものでした。最後に嵩の名前が上がる場面は、のぶにとって嵩がいかに大切な存在かを示しています。
「先生のご実家は市内ですね。」
「市内から外れた丘の上のに祖母と母がおります」
牧徹子の家族の状況説明からは、地震被害の深刻さと家族への心配が伝わってきます。のぶも同じように、高知の家族と嵩の安否を案じているのです。
高知新報社の混乱と嵩の行方|SNSで話題の不安
高知新報社では地震の影響で大混乱が続いていました。建物がぐちゃぐちゃになった様子は、災害の深刻さを物語っています。
地震の大きさを物語るかのように、あらゆるものが落ちてしまっている高知新報内で琴子が片付けをしています。
この描写は、報道機関としての機能が麻痺した状況を示しています。情報収集と発信の拠点が被災することで、災害の全容把握がいかに困難かが分かります。
編集部メンバーの絆と責任感
「あいつが住んでいる場所が一番被害がひどいという」
岩清水の報告は、嵩の安否への不安を一層高めました。東海林編集長の「何かあった際は俺の責任や」という言葉からは、部下への深い愛情と責任感が伝わってきます。
「一昨日の夜、会社に泊まり込んでなかったら、我々もどうなっていたか」
編集部メンバーが無事だったのは、仕事への献身があったからこそでした。しかし、その分嵩の安否が心配されます。
「一昨日は無理やりうちに帰した」という東海林の後悔の念は、上司としての責任感の表れでもあります。この場面での津田健次郎さんの演技は、視聴者から
「今日の東海林編集長、宗との面白パートと、地震後シリアスパートの温度差で風邪ひきそうになるくらい緩急すごかった」
と評価されています。
視聴者の心配と考察
SNSでは
「嵩くんどこにいるの?嵩くんも朝田家のみんなもどうか無事でいて」
という心配の声が多く寄せられています。また
「でもたかしくんは大丈夫よ。亡くなったらストーリーが(以下略)」
という冷静な分析も見られ、視聴者の物語への信頼も感じられます。
「嵩の住まいについて説明されてないから不明。御免与の旧柳井医院に健太郎と居候かと思えば…違いそうだし」
という詳細な考察も見られ、視聴者がいかに真剣に物語を追っているかが分かります。
「死者1200名という新聞を読むのぶ」の場面では、災害の規模の大きさと、のぶの心境の複雑さが描かれました。家族、嵩、仲間たちの安否が気になる中で、のぶがどのような行動を取るのかが注目されます。
「のぶにとって最初の親のいない子は嵩なんやな。のぶの中では今もずっとあの時の弱弱しい嵩のままなのかな」
という視聴者の考察は、のぶと嵩の関係性の原点を見事に捉えています。
八木さんとのぶの教育観|未来への投資
「辛い」という漢字は、1本線を足すと「幸」という字になるんだよ」
のぶが子どもたちに教えていた漢字の話は、まさに今の状況を暗示するかのようでした。困難な状況も、見方を変えれば希望につながるという前向きなメッセージが込められています。この場面は視聴者からも
「漢字っておもしろいね!きっと、物の考え方も、ちょっと見方を変えるだけで変わるんだろうね」
という感想が寄せられています。
戦災孤児たちとの関わりの中で、八木さんとのぶの教育に対する考え方も描かれました。
「八木さんがおっしゃる言ったがです。子供らには食べ物と同じくらい心の栄養が必要やって」
この言葉は、物質的な支援だけでなく、精神的な成長の重要性を示しています。八木さんとのぶは
「考え方も方法も全く違うけど戦災孤児たちのことを真剣に考えてるのは共通してる」
と視聴者からも評価されています。
「今日食べるもんも大事やけんど未来をどう考えるかが政治や」
この言葉は現代にも通じる重要なメッセージです。「目先の事も大事だけど、未来の事も大事!」という視聴者の感想からも、このセリフが多くの人に響いていることが分かります。
子どもたちの
「俺おねちゃんがいいな」
私は優しいし、お目めがかわいいし、おじさんをいつも忙しそうだし、いっつも怒ってて怖いし」
という率直な感想は、微笑ましい場面でもありました。子どもの目から見た大人の姿は、時に的確で示唆に富んでいます。
このエピソードは、昭和南海地震という実際の歴史的災害を背景に、人間関係の絆と愛の深さを描いた重要な回となりました。のぶと嵩の距離感、家族への想い、そして赤いバッグに象徴される二人の関係性が、この災害を通じてどのように変化していくのか、今後の展開が非常に楽しみです。
災害という試練を通じて、人々の絆がより一層深まることを期待させる、感動的なエピソードでした。戦後復興期における様々な困難の中でも、希望を失わずに前進する登場人物たちの姿は、現代の私たちにも勇気を与えてくれます。
まとめ
今回の第83話「あなたの二倍あなたを好き」の見どころと伏線をまとめます。
- 昭和南海地震の歴史的背景 – 1946年12月21日の実際の災害を丁寧に描写し、戦後復興期の新たな試練として物語に組み込んだ脚本の巧みさ
- 嵩のスランプと手塚治虫の登場 – のちの「漫画の神様」の作品に触れた嵩の反応は、創作者としての成長への重要な伏線
- 赤いバッグの象徴性 – 引き出しに眠るバッグは二人の関係性の距離感を表し、災害を経てどう変化するかが今後のポイント
- のぶの感情表現の複雑さ – 視聴者が指摘する「ダブルバインド」的な表現は、戦後の混乱期における内面的葛藤の演出として注目
- 政治と個人の関係性 – 戦災孤児問題を通じて描かれる「個人に丸投げ」への批判は、現代社会への問題提起でもある
- 災害を通じた絆の再確認 – 地震という試練が、のぶの家族愛と嵩への想いの深さを改めて浮き彫りにした重要な転換点