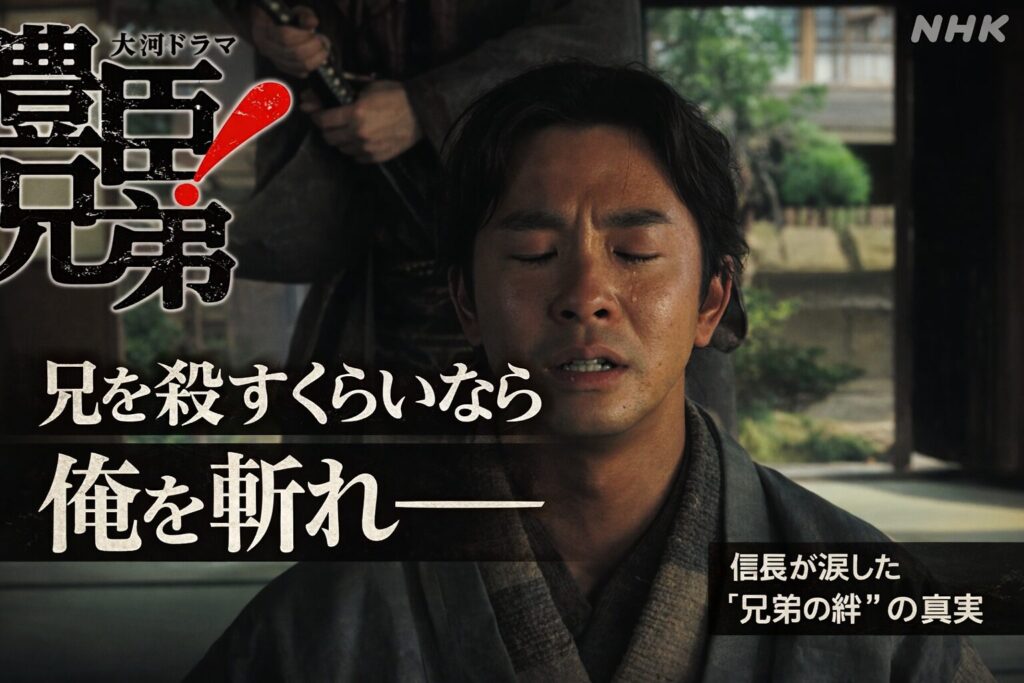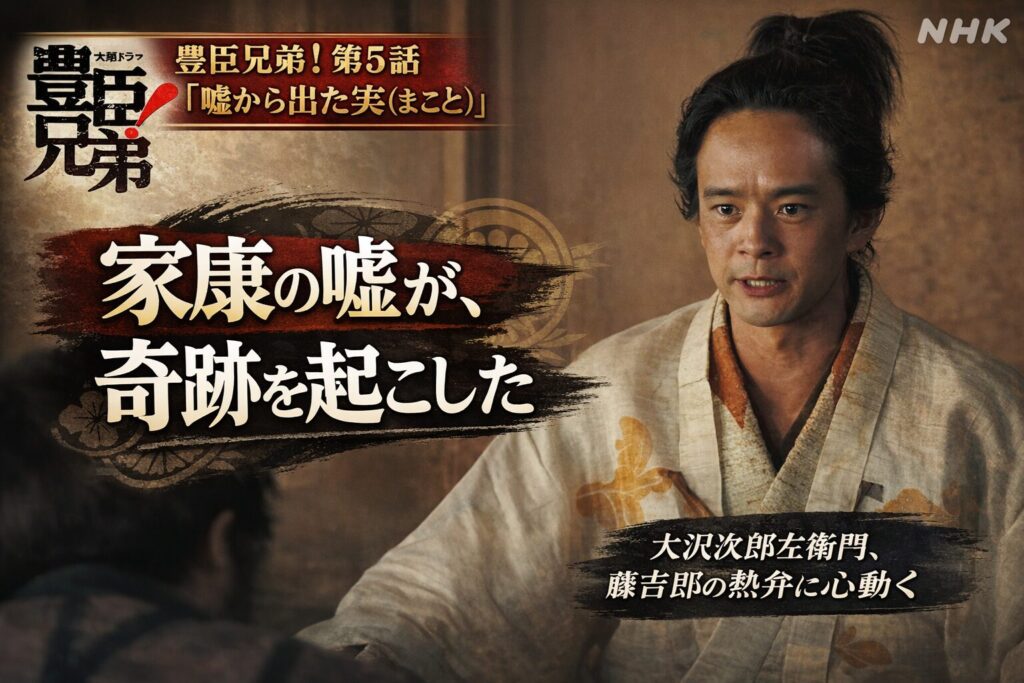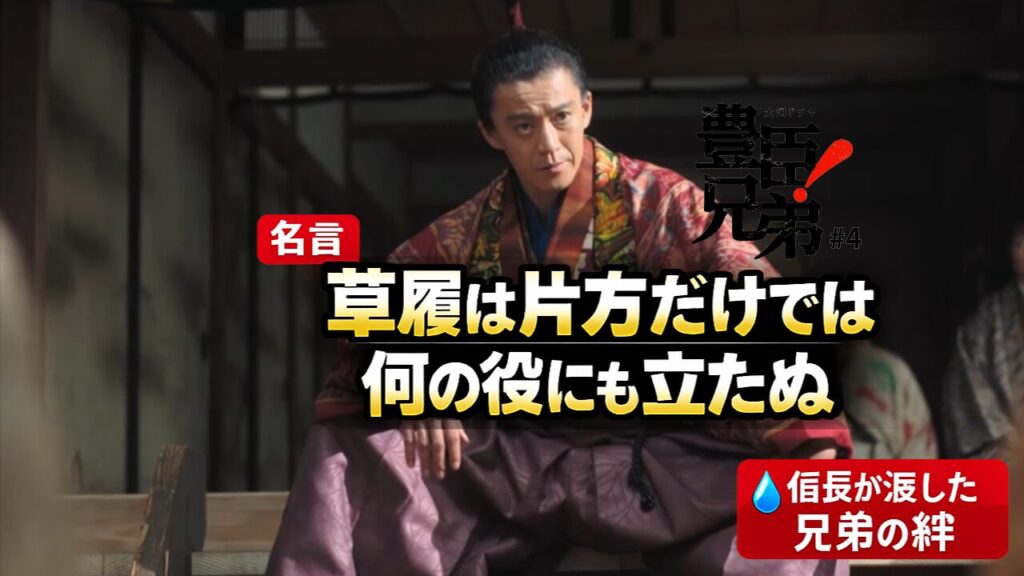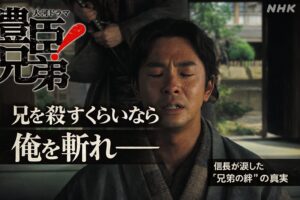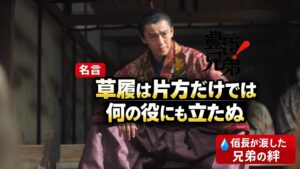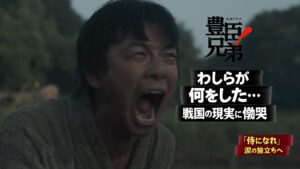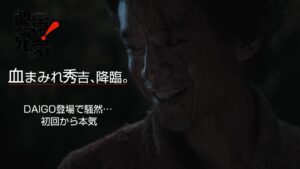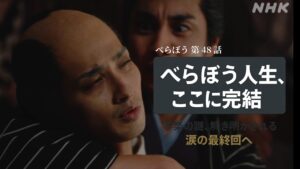吉原発、江戸行き──「べらぼう」第17話では、蔦屋重三郎(横浜流星)が「往来物」という新たな出版戦略に打って出ます。教育と商売が交差するこの挑戦は、単なる商売ではなく、“本を通して未来をつくる”という信念に裏打ちされたものでした。
一方で、前回から続く“毒入り手袋”事件の余波は政の中枢にも波及。田沼意次(渡辺謙)は西の丸様の後継を巡って動き出し、上様の側には亡き「知保の方」に似た女性・鶴子が現れます謙
市中からの圧力、吉原の思惑、そして浮かび上がるカラマルの影──今話では“人と人をどうつなげるか”“誰と歩むか”というテーマが、さまざまな角度から描かれました。
1-1. 【あらすじと全体展開】第17話は何が描かれた?
耕書堂の成長と市中との駆け引き
「スタジオめがけて客が来るようになった」
正月に10冊の青本を刊行し、蔦屋重三郎の名は市中に轟くまでに。
吉原の女郎屋に寄るついでに「スタジオ(耕書堂)」に立ち寄る、そんな文化現象すら生まれています。
一方で、出版業界の“元締”である市中の版元たちはそれを面白く思っておらず、蔦重に圧力をかけ始めます。
「市中の連中が戻ってきたんだよ。初動の仕事は受けるんだよ」
鶴子の登場と「知保の方に似ておる」の意味
後継問題に揺れる徳川家では、上様(将軍)を慰めるために「知保の方の遠縁にあたる」という女性・鶴子が送り込まれます。
「表を上げよ」
「よう、似ておる…」
このセリフの余韻が長く、本当に知保の方と似ているのか?など話題になりました。
傀儡子のセリフが再び登場「独りぼっちは寂しいの~」
再び現れた謎の傀儡子がこんな言葉を口にします。
「独りぼっちは寂しいの~」
前話で源内に向けて語ったこの言葉が、今度は蔦重にも向けられているように感じる…そんな不穏さと寂しさが漂います。
1-2. 徳川家と“知保の方”の影──上様の心に残る面影とは?
上様の「表を上げよ」──それは何を意味するのか?
上様の「表を上げよ」は、ただの儀礼的セリフではなく、“知保の方”という存在に対する喪失の補填であると同時に、何か過去の思いを封じるような重みがありました。
田沼意次の策──後継を探る「西の丸の椅子」
「田沼様は西の丸の座に誰が色気を見せてくるか密かに探っておられました」
この一言で、田沼が“毒手袋事件”の真相と、将軍家の後継をどう繋げようとしているかが見えてきます。彼の手綱捌きは本当に巧妙。
1-3. 往来物とは?江戸の教育出版と蔦重の戦略
子ども向けの“本”を売る理由
「往来者とは、子供が読書を覚えるための本です」
「俺が掘った板で作る本、娘みたいなもんじゃねえか」
蔦重にとってこの出版は、単なる商売ではありません。未来のために“教育の種をまく”こと。しかも「娘」と表現するあたりに、彼の“父性”がにじみます。
「関わった人は味方になる」──蔦重の流通革命
「自分が関わった本というのは自慢したいし、すすめたいのが人所」
「つまり、関わったその人たちは味方となる」
この言葉が今話最大のキーワード。蔦重は“販路を増やす”のではなく、“人を味方にする”戦略で江戸を変えようとしているのです。
1-4. 再び登場の“カラマル”──絵に込められた伏線?
「絵を見て…まさかカラマルが描いたものでは…」
過去の記憶、絵の筆致、そして言葉にできない予感──
再びカラマルの名が浮上したことで、物語はさらに“源内ライン”と“カラマル=未来ライン”を繋げて動き始めます。
1-5. SNSで話題のセリフと考察まとめ【Xより】
- 「傀儡子の“独りぼっち”が今回もグサグサ刺さる」
- 「蔦重、もう完全に江戸の“お父さん”ポジになってる」
- 「往来物=娘って例えが最高。もう蔦重を応援せずにいられない」
- 「カラマルって生きてる?絵師で再登場フラグ?」