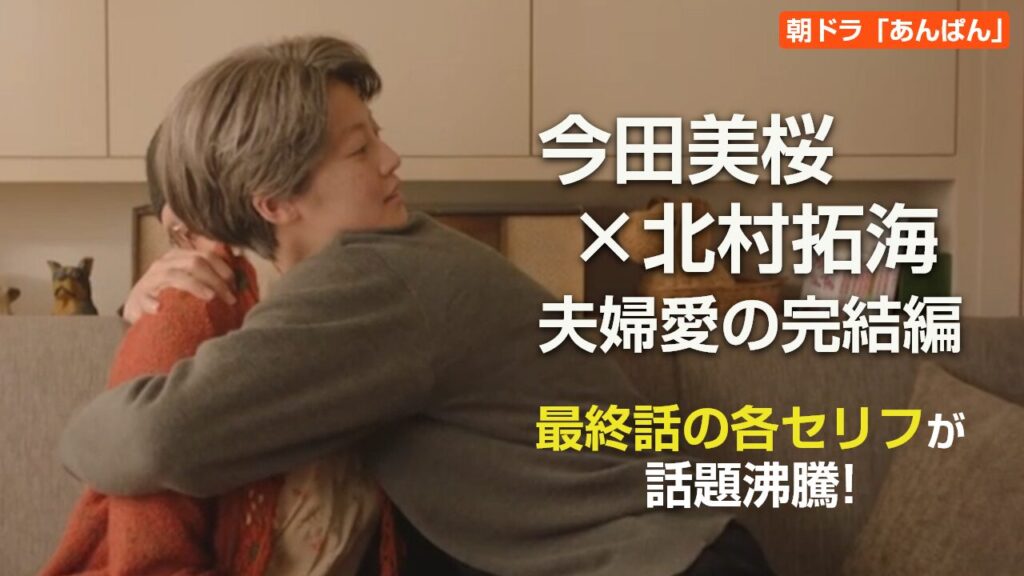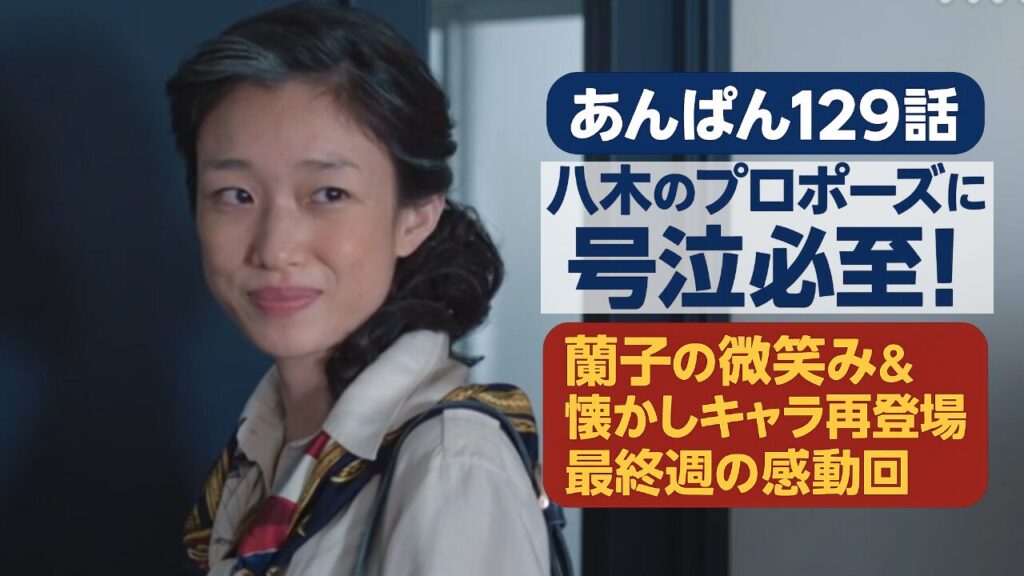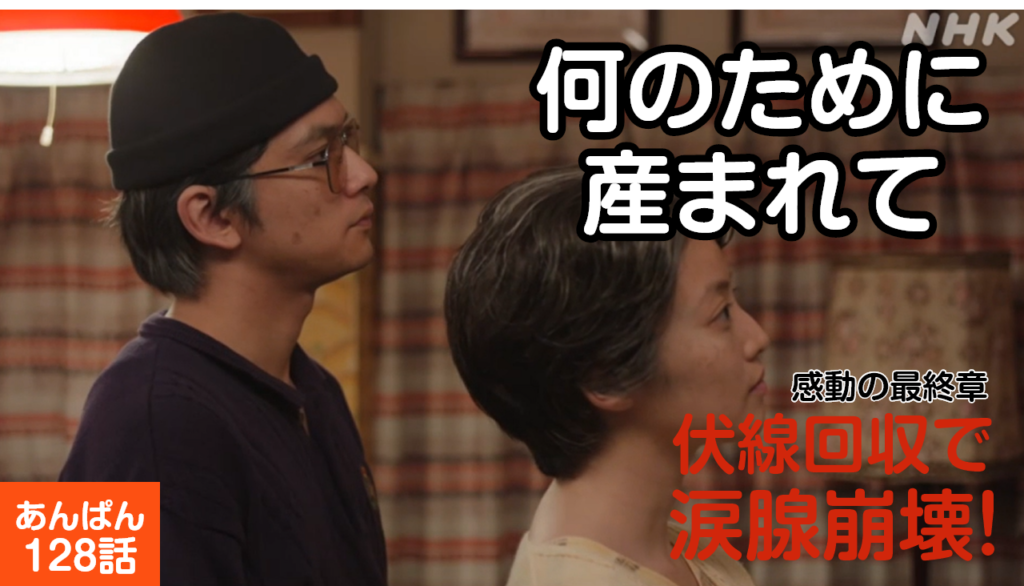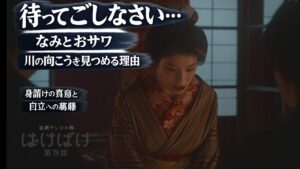朝ドラ「あんぱん」第24週第120話「あんぱんまん誕生」で、ついに物語のクライマックスが到来しました。琴子さんからの手紙で東海林編集長の死を知った嵩とのぶ。編集長が命を削って伝えた「逆転しない正義」の想いを胸に、嵩は徹夜でついにあの「アンパンマン」を描き上げます。
朝ドラ『あんぱん』第24週第120話 あらすじ
4月20日に亡くなった東海林編集長。病身を押して上京し、嵩とのぶに会いに来た本当の理由が、琴子さんの手紙で明かされます。編集長は「あの2人はついに見つけたぞ。逆転しない正義を」と嬉しそうに語っていたのです。
その夜、何かに突き動かされるように机に向かう嵩。引き出しから紙を取り出し、東海林編集長の励ましの言葉を回想しながら、一晩中ペンを走らせます。朝になって「できたぁ…」とつぶやく嵩の前には、顔があんぱんの「あんぱんまん」の姿が。
「自分の顔を食べさせるがね」「例え自分の命が終わっても、大丈夫。あんぱんまんの命は終わらない、続くんだ」という嵩の言葉に、のぶは涙を流します。「うち、こういうヒーロー、ずっと待ちよった気がする」と感動するのぶの姿に、視聴者も思わず涙腺が緩んだ名シーンでした。
昭和48年10月、ついに生み出されたあんぱんまんは、子ども向けの月刊絵本として幼稚園や図書館に置かれることになります。
琴子さんの手紙が明かした東海林編集長の真実
朝ドラ「あんぱん」第120話は、琴子さんからの速達で幕を開けました。岩清水さんと結婚した琴子さんからの手紙には、東海林編集長に関する衝撃的な事実が記されていました。
4月20日の別れ – 命を削った上京の理由
「4月20日、庄司明さんが亡くなられました」
という琴子さんの言葉に、のぶと嵩は言葉を失います。手紙によると、東海林編集長は入院していた病院を抜け出して東京へ向かったのです。
「命の保証はできないと、お医者様は止めたそうです。それでも、どうしても、お2人に会って確かめたいことがあると」
この琴子さんの手紙の内容は、前回の東海林編集長の上京が単なる激励ではなかったことを物語っています。編集長は自分の命を削ってまで、嵩とのぶに会いに来たのです。病身を押しての上京は、まさに命がけの行動でした。
視聴者からは「編集長の献身的な姿に涙が止まらない」「本当に愛に溢れた人だった」という感動の声が多数寄せられています。編集長の行動は、物語全体を通じて描かれてきた「人への愛」「正義への信念」を体現したものと言えるでしょう。
「逆転しない正義」を見つけた編集長の最期
琴子さんの手紙で最も印象的だったのは、編集長の最後の言葉でした。
「東海林さんは、あの2人はついに見つけたぞ。逆転しない正義をとうれしそうにそうおっしゃって。本当にとてもうれしそうな笑顔で、それからしばらくして、息を引き取られたそうです」
この「逆転しない正義」という言葉こそが、アンパンマン誕生のキーワードとなります。編集長は嵩とのぶの中に、戦争を経験し、飢えを知っているからこそ生み出せる真の正義を見出していたのです。
編集長の死を知った嵩の
「そんなことって、命を削って」
という言葉からは、恩人を失った深い悲しみが伝わってきます。しかし同時に、この悲しみこそがアンパンマン誕生の原動力となっていくのです。
SNSでは「編集長の最期の言葉が重すぎる」「『逆転しない正義』の意味を考えさせられる」といった考察の投稿が数多く見られました。戦争体験者である編集長が見つけた「正義」とは何だったのか、視聴者それぞれが深く考えるきっかけとなったようです。
運命の一夜 – 嵩が描いたあんぱんまん誕生の瞬間
琴子さんの手紙を読んだその夜、嵩は何かに突き動かされるように仕事場に向かいます。電気を点け、机に向かう嵩の姿は、まさに創作者の魂が燃えている瞬間でした。
東海林編集長の言葉に導かれた創作活動
引き出しから紙を取り出す嵩。その時、東海林編集長からのアンパンマンへの励ましの言葉が回想として流れます。この演出が非常に効果的で、編集長の想いが嵩の創作意欲を駆り立てていることが視覚的に表現されていました。
のぶへ
「悪いけど、先に寝てて」
と気遣って声をかけ、嵩は創作に没頭します。紙を見つめながら唇を噛みしめ、ペンを取る姿からは、並々ならぬ決意が感じられました。
嵩は一晩中創作に打ち込みます。この徹夜での創作シーンは、多くの創作者が共感できる、まさに「何かに取り憑かれたような」創作体験を見事に表現していました。
朝になってのぶがカーテンを開けると、嵩から
「できたぁ…」
という言葉が。この瞬間、視聴者は物語開始から120話を経て、ついにアンパンマン誕生の瞬間に立ち会うことになります。
「顔を食べさせる」ヒーローの誕生秘話
のぶが紙を見つめると、そこには皆が知る「あんぱんまん」の姿が描かれていました。顔があんぱんで、半分になってしまう設定も既に組み込まれています。
のぶの
「そっかぁ」
という納得の声、そして
「自分の顔を食べさせるがね」
という言葉は、アンパンマンの本質を表しています。この設定について、嵩は深い意味を込めて説明します。
「例え自分の命が終わっても、大丈夫、あんぱんまんの命は終わらない、続くんだ」
この言葉こそが、アンパンマンというキャラクターの核心を表しています。自己犠牲を厭わず人を助けるヒーロー像は、戦争で多くの命を失った体験から生まれた深い愛情表現なのです。
ジャムおじさんがあんぱんまんに新しい顔を付けるシーンも描かれ、命の継続というテーマが視覚的に表現されました。この場面でのぶの目から涙が浮かび、感動と笑みが同時に現れる演出は、視聴者の心を強く打ちました。
SNSでは「アンパンマンの設定の深さに驚いた」「戦争体験があったからこそ生まれたヒーローなんだと実感」といった投稿が多数見られ、改めてこのキャラクターの奥深さが注目されています。
のぶの涙と「ずっと待ちよった」ヒーロー像
アンパンマンの絵を見たのぶの反応は、このドラマの中でも特に印象的なシーンの一つでした。涙を流しながらも笑顔を浮かべるのぶの表情は、今田美桜さんの演技力の高さを改めて示したものでした。
戦争体験が生んだ深い愛情表現
「うち、こういうヒーロー、ずっと待ちよった気がする」
のぶのこの言葉は、戦争を体験した世代が求めていたヒーロー像を表現しています。力で悪を倒すのではなく、自分を犠牲にしてでも人を救うヒーロー。それは戦争で多くの命を失い、飢えを体験した人々だからこそ理解できる愛の形でした。
のぶが涙を流すシーンは、単純な感動ではありません。戦争で夫を失い、自らも飢えを体験したのぶにとって、アンパンマンは理想のヒーロー像だったのです。武力ではなく、愛で人を救うヒーロー。それこそが、戦争を知る世代が本当に求めていたものでした。
嵩も一緒に涙を拭う場面は、夫婦の絆と共通の価値観を示しています。二人とも戦争を体験し、平和の尊さを知っているからこそ、このようなヒーローを生み出すことができたのです。
ジャムおじさんの登場と命の継続
ジャムおじさんがあんぱんまんに新しい顔を付けるシーンの登場は、命の継続というテーマを視覚化した重要な演出でした。顔を食べさせて弱くなったアンパンマンに、新しい顔を与えて元気を取り戻させる。これは死と再生、命の循環を表現しています。
この設定について、視聴者からは様々な反応が寄せられています。子どもたちからは
「顔を食べさせるのはちょっと気持ち悪い」
という率直な感想も出ましたが、大人の視聴者からは「深い意味がある設定だと分かった」「戦争体験があったからこその発想」といった理解の声が多く聞かれました。
実際のセリフでも
「顔食べられていたくないのかなって言いよった。」
「そりゃそうや、食べるたんびにいたいたい言われたら遠慮してしまう」
という子どもたちの反応が紹介されており、このキャラクターの受け入れられ方の複雑さが描かれています。
昭和48年10月 – 世に送り出されたあんぱんまん
ついに完成したあんぱんまんは、昭和48年10月に子ども向けの月刊絵本として刊行され、幼稚園や図書館に置かれることになりました。この場面転換により、物語は新たな段階に入ります。
子どもたちの反応と大人の困惑
茶道を学んだのぶが自宅で小さなお茶の教室を開くシーンから、日常に戻った様子が描かれます。そこでのぶがあんぱんまんの読み聞かせを行う場面は、この作品が実際に子どもたちに届けられる瞬間を表現していました。
「僕の顔を食べなさい」
「僕はアンパンマンだ。いつもお腹の空いた人を助けるのだ。僕の顔はとびきりおいしい」
読み聞かせでののぶの語りは、アンパンマンというキャラクターの本質を子どもたちに伝える重要なシーンでした。しかし、子どもたちの反応は複雑です。
「アンパンマン可愛いね」
という肯定的な反応がある一方で、
「でも、顔を食べさせるのはちょっと気持ち悪い」
「いくらおなかがすいても、顔を食べるのはちょっと」
という戸惑いの声も聞かれます。
これらの反応は、アンパンマンというキャラクターが単純な子ども向けヒーローではなく、深い背景を持った複雑な設定であることを示しています。戦争体験から生まれた愛の表現は、時として子どもには理解しづらいものでもあったのです。
八木の会社での読み聞かせシーン
物語の終盤では、実際に八木の会社にあんぱんまんの絵本が置かれるシーンが描かれました。のぶがあんぱんまんの絵本を届けに行く場面は、作品が世に送り出される記念すべき瞬間として演出されています。
特に印象的だったのは、少女がアンパンマンの絵本を手に取り、読んでいるシーンです。その姿を嬉しそうに見つめるのぶの表情からは、自分たちが生み出した作品が子どもたちに愛される喜びが伝わってきます。
八木さんもアンパンマンの魅力を認識し始めている様子が描かれました。
この場面について、SNSでは「子どもが本当に楽しそうに読んでいるのを見て感動した」「絵本として愛される瞬間が描かれて良かった」といった温かい反応が寄せられています。
最後の次回予告で
「アンパンマン、ミュージカルにしてみませんか?アンパンマンが、もっと多くの人に愛されるって信じてます。戦争で大切な人を失った人たちが、少しだけでもいいので、心が軽くなるような、そんなミュージカルにしてほしいです」
というセリフも登場し、アンパンマンの更なる発展への期待が示されました。
SNSで話題沸騰!視聴者の感動と考察
第120話の放送後、SNSでは多数の感動の声と深い考察が投稿されました。特に東海林編集長の死とアンパンマン誕生のシーンに対する反響は非常に大きなものでした。
「涙腺決壊」の声続出
「涙腺決壊」という表現が多数の投稿で使われたことからも分かるように、この回は多くの視聴者の心を強く打ちました。特に東海林編集長の最期に関する投稿では、「命削って愛を届ける速達便」「編集長、虹の橋で声かける」といった感情的な表現が目立ちました。
「毎日朝ドラを観ています」という投稿では、編集長の献身的な行動に対する深い感動が綴られており、「今回の編集長には泣かされました」という率直な感想が多くの視聴者の気持ちを代弁しています。
また、
「今日のNHK朝の連ドラの、あんぱん、見て、あんぱんまんの誕生と意味合いがやっとわかり、感動して涙が出ました」
という投稿は、120話でようやくアンパンマンの本当の意味が理解できたという感動を表現しており、物語の構成の巧みさを物語っています。
北村匠海さんの「あさイチ」での振り返りトークについても話題になり、「北村匠海のあさイチトークも最高でした」という声や、役者としての多才さを称賛する投稿も多数見られました。
戦争描写と現代への問いかけ
より深い考察を行った投稿も多数ありました。
「東海林さんが亡くなった事をバネにAPMが生まれた」
「嵩とのぶの戦争体験を背負って生まれたAPM。重すぎて大人は拒否反応を示した。幼児はさらりと受け入れた」
という分析は、アンパンマンというキャラクターの複雑さを的確に指摘しています。
「なぜ純粋無垢な心にAPMは響くのか」という問いかけは、子どもと大人の受け取り方の違いについて考察を促すものでした。戦争体験から生まれた愛の表現が、なぜ子どもたちには自然に受け入れられるのか。この点について多くの視聴者が考えを巡らせたようです。
一方で、「ドラマとして評価したい」「実在の人物をモデルにしてるのだから失礼な改ざんは許せない」といった批判的な投稿もあり、視聴者の中でも様々な受け取り方があることが分かります。
ループ構造についても「1話アバンは絵本用原稿?」「ドラマ内時制が第1話アバンに辿り着いた?」といった詳細な分析が行われ、ドラマの構成に対する深い関心が示されました。
まとめ – 今回の見どころや伏線
- 東海林編集長の死が物語の転換点:命を削って伝えた「逆転しない正義」がアンパンマン誕生の直接的なきっかけとなった
- 戦争体験から生まれた真の愛の表現:「自分の顔を食べさせる」という設定は、飢えを知る者だからこそ生み出せた究極の愛情表現
- のぶの「ずっと待ちよった」という言葉の深さ:戦争を体験した世代が本当に求めていたヒーロー像が表現された
- 子どもと大人の反応の違い:純粋な子どもには受け入れられるが、大人には複雑な設定として映る巧妙な対比
- ループ構造の完成:第1話のアバンシーンへの到達により、物語の円環構造が明確になった
- ジャムおじさんの登場による命の継続テーマ:死と再生、命の循環という深いテーマが視覚的に表現された