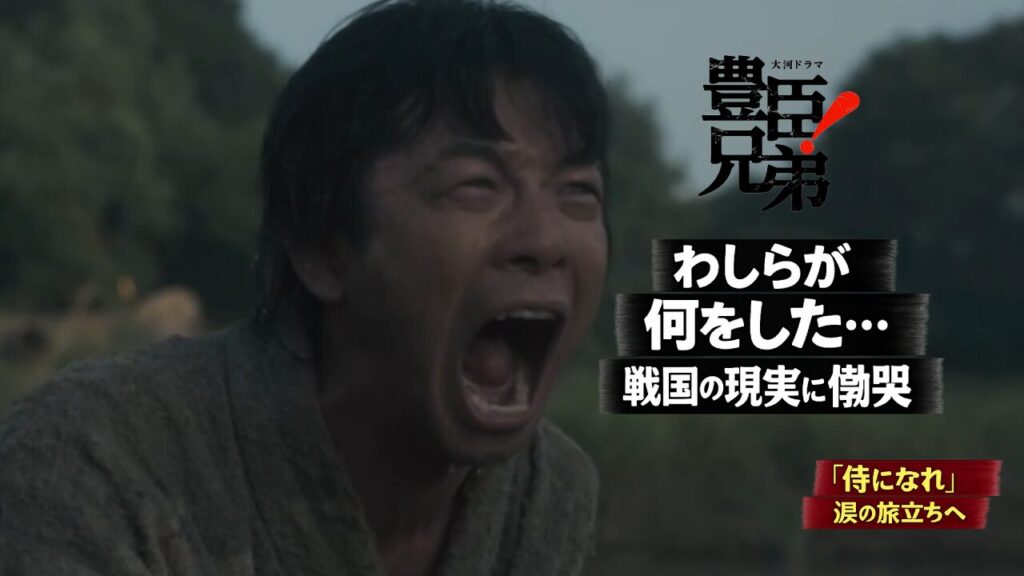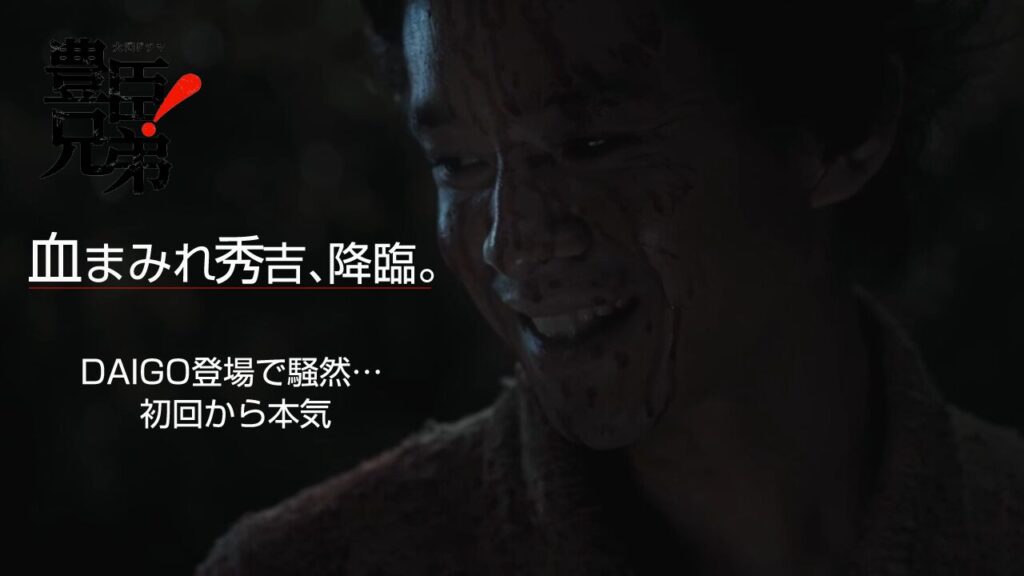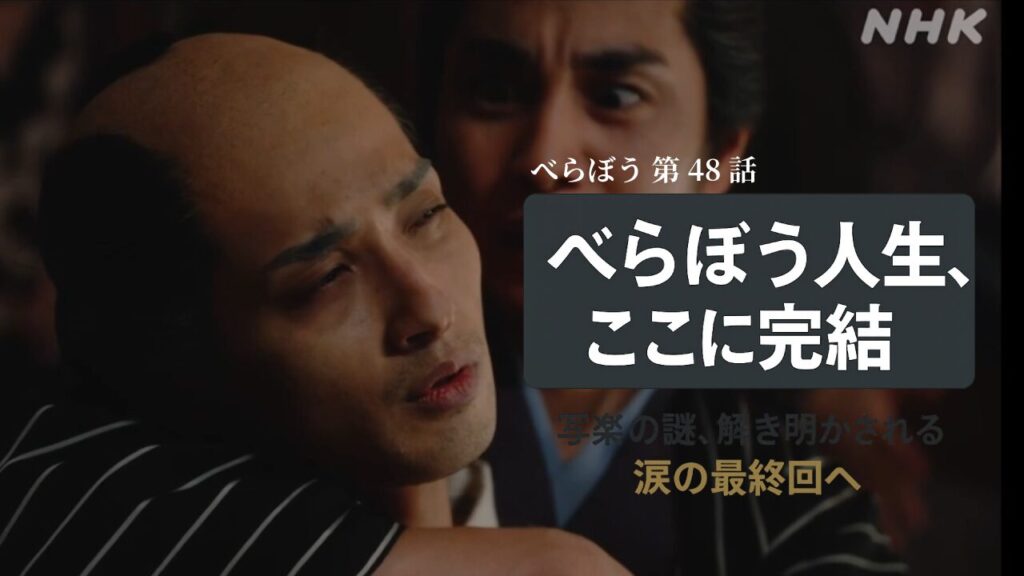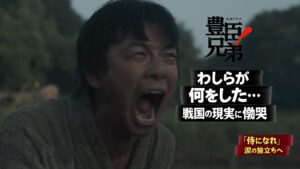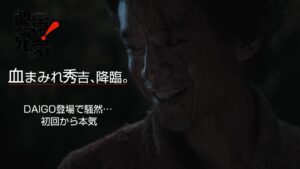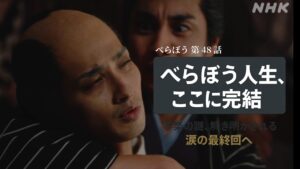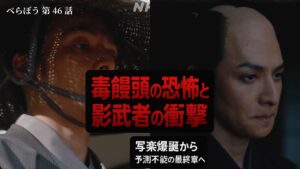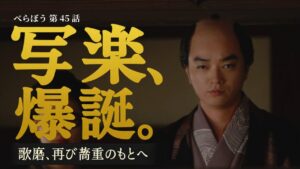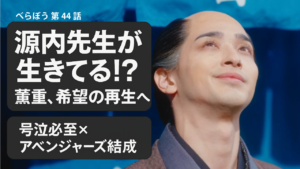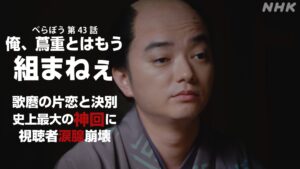大河ドラマ「べらぼう」第39話「白河の清きに住みかね身上半減」が放送され、SNSでは視聴者の感動と興奮の声が殺到しています。蔦重(横浜流星)が出版した教訓読本が絶版命令を受け、松平定信(井上祐貴)との直接対決へ。おてい(橋本愛)の漢詩を駆使した命乞いと「べらぼう!」の平手打ち、鶴屋(風間俊介)の「ほんと、そういうところですよ!」という本気の叱責、そして長谷川平蔵(中村隼人)の颯爽とした登場まで、見どころ満載の神回となりました。身上半減という厳しい処罰を受けながらも、それを逆手に取る蔦重の商才と、仲間たちの絆が胸を打つ展開です。
べらぼう第39話 あらすじ
歌麿(染谷将太)がきよの死を引きずり放心状態に陥る中、つよ(高岡早紀)が寄り添い栃木へ旅立つことに。一方、蔦重は山東京伝作の洒落本三部作を「教訓読本」として出版するが、奉行所から絶版命令が下り連行されてしまう。牢屋で定信と対峙した蔦重は、「白河の清きに魚住みかね」の故事を引用し、人は濁りを求めると持論を展開。しかし定信は聞く耳を持たず、おていが漢詩で命乞いに挑む。結果、京伝は手錠50日、蔦重は身上半減という前代未聞の刑罰に。それでも懲りない蔦重におていが「べらぼう!」と平手打ちし、鶴屋も本気で叱責する。だが蔦重は身上半減を逆手に取り、話題作りで店を再興していく。
歌麿の心の傷とつよの優しさ|栃木行きを決意するまで
きよの死を引きずる歌麿の放心状態
第39話の冒頭は、前回きよを失った歌麿(染谷将太)の放心状態から始まります。蔦重が歌麿の部屋を訪れると、自害を心配した蔦重が刃を回収する緊迫したシーンが描かれました。
歌麿は完全に心を閉ざしており、蔦重が声をかけても反応がありません。演出では、歌麿の虚ろな目と俯いた姿勢が強調され、彼がどれほど深い喪失感に襲われているかが痛いほど伝わってきます。染谷将太さんの繊細な演技が、言葉以上に歌麿の苦しみを表現していました。
つよの献身的な寄り添いと「付いていく」決意
そんな歌麿のもとに現れたのが、つよ(高岡早紀)でした。つよは優しく歌麿に寄り添い、おにぎりを差し出しながら
「気が向いたら食べて」
と声をかけます。
「蔦重から離れたいっていうのもあるみたいだよ」
と心配すると、つよは
「私、当分こっちにいるから」
「あんたは戻りなよ。」
「いや、今日、明日変わってくれりゃあ」
「あんたより、あたしの方が役に立ちそうだしさ」
と、歌麿に付き添う決意を告げます。
この場面でのつよの包容力と母性的な優しさは、視聴者の心を温かくしました。歌麿が栃木の贔屓先で肉筆画を描くと言い出したことで、二人は江戸を離れることになります。つよは
「あんたから離れたいってのもあるみたいだよ」
「今はまだそういうのはダメさ」
と蔦重を諭します。歌麿の心の傷が癒えるまで、そっと見守る選択を促したつよの優しさも印象的でした。
蔦重の教訓読本出版と奉行所の取り締まり|絶版命令の衝撃
「袋とじ」で検閲をすり抜ける蔦重の知恵
寛政2年10月、地本問屋の株仲間が正式に発足し、自主検閲での発行が許されることになりました。鶴屋(風間俊介)が「奉行所と水面下でやり取りを重ね…」ですが、蔦重はこの仕組みを「ざる」だと見抜いています。
事本の関係者が、自己検閲の時に
「公職本の類は出しちゃならないってなってますし」
「抜き打ちで調べにくんじゃないですか?」
と心配すると、蔦重は
「教訓読み本って書いた袋入りにして売るってんで、どうです?」
と提案します。
この「袋とじ」作戦は、表向きは教訓書として売り出しながら、実際には遊郭の指南書である洒落本を世に出そうという、蔦重らしい大胆な策でした。
「教訓読み本放って書いてありゃ、抜き打ちで調べたりしないでしょう」
という蔦重の読みは、当初は功を奏したように見えました。
突然の奉行所襲来と連行シーン
年が明けて3月、まさのぶは
「このまま、何のおとがめもなさそうですね」
と安堵していましたが、その矢先に奉行所の役人が店に押し入ってきます。
「主、蔦屋重三郎であるな」
「山東京伝に咲く錦の裏、仕掛文庫、娼婦絹狂、以上教訓読み本三作を絶版とする」
という宣告が下され、蔦重と京伝が連行されることに。
突然の展開に視聴者も驚愕し、SNSでは「まさかの展開」「蔦重ピンチ」といった声が上がりました。鶴屋たちが必死に止めようとする中、蔦重は比較的冷静な表情で連れて行かれます。この後に待ち受ける定信との対峙を予感させる、緊迫感あふれる演出でした。
蔦重vs定信の対峙|「白河の清きに魚住みかね」の漢詩バトル
定信との緊迫した問答|濁りを求める人の性
牢屋に入れられた蔦重の前に、ついに松平定信(井上祐貴)が姿を現します。
「越中の神様じきじきに見聞なされることとなった」
という前代未聞の事態に、視聴者の緊張感も高まりました。
定信は
「かようなものは二度と出さぬと誓え!」
と迫りますが、蔦重は怯むことなく、有名な故事を引用して反論します。
「透き通った美しい川と濁った川」
という例え話を始めた蔦重に、定信は
「魚は濁りのある方を好む、濁りのある方が、餌が豊かであるのだろう。敵から身を隠しやすいというのもあろうか。流れが緩やかなら、過ごしやすくもあろうしな」
と応えると、蔦重はさらに踏み込みます。
「人も魚とそう変わらんと思うんでさ。人ってな、どうも濁りを求めるところがありまして、そこにうまい飯が食えて、隠れておもしれえ遊びができたりして。怠けてても怒られない。そんなとこに行きたがるっていうのが人情っていうんですかね」
この場面は、まさに「白河の清きに魚住みかね」という有名な狂歌を下敷きにした論争です。定信の進める清廉な改革に対し、人間には濁りも必要だと主張する蔦重の姿勢が鮮明に描かれました。
「人は楽しく生きたい」蔦重の信念が炸裂
蔦重の言葉はさらに大胆になります。
「近頃、白河の清きに魚住みかねて、元の濁りの田沼恋しき…なんて読む輩もいるんですよ?私はね、それはそれでけしからんと思うわけですよ。多少てめえらが窮屈だからって、越中の神様はよき世にするために懸命にきったねー、どぶさらってくださってるわけでしょう」
一見、定信を持ち上げているようでいて、実は皮肉を込めた物言いです。そして蔦重は、自分が教訓読本を出した理由を説明します。
「本屋として、何かできることはないかと知恵を絞って、それでございます。あくまで教訓ですよ、というていで公職本を出す。これを許す越中の神様。これはもう、堅いふりして実は分かってらっしゃる。と勝手な具合に評判になるわけです」
要するに、蔦重は定信を利用して商売をしていたと堂々と宣言したのです。
「これからも、越中の神様の評判を上げるべく、文に励みたいと思います」
という言葉には、定信への挑発が込められていました。
そして、後半では長谷川平蔵のシーンで蔦重の真意が語られます。
「人は楽しく生きたいのでございます」
この一言が、蔦重の信念のすべてを表しています。正しく生きることよりも、楽しく生きることを求める人々。その欲求を満たすために本を作り、文化を支える。それが蔦重の仕事だという誇りが感じられる名セリフでした。
おていの命乞いと漢詩バトル|知性で夫を守る妻の強さ
論語を駆使した舌戦の迫力
蔦重が牢に入れられている間、おてい(橋本愛)は夫を救うために命乞いに向かいます。仲間たちは
「類が及ぶことを考えれば、命乞いはできませんよ」
と止めますが、ていは
「死を待つだけなのであれば」
と覚悟を決めました。
定信のご意見番である柴野栗山(嶋田久作)の前に現れたおていは、論語を引用して夫の無実を訴えます。
「これを導くに徳をもってし、これを整えるに礼をもってすれば」
と切り出し、さらに続けます。
柴野栗山も
「君主は中庸を、精進は中央に反す。照準は中庸に反するば精進にして忌憚なきなり」
と論語で応じ、二人の漢詩バトルが始まります。
この場面での橋本愛さんの凛とした佇まいと、嶋田久作さんの威厳ある演技が素晴らしく、SNSでは「おてい格好いい」「漢詩女子最高」といった絶賛の声が殺到しました。
「義を見てせざるは勇なきなり」の意味
おていはさらに踏み込んで、夫の行動の正当性を主張します。
「夫は、客に倹約しろと言われていると嘆いておりました。遊郭での礼儀や、さようなことを伝えることで、女郎の身を案じ、礼儀を守る客を増やしたかったのだと思います」
そして、
「親兄弟を助けるために売られてくる者、不遇な者を助けるは」
と続け、
「義を見てせざるは勇なきなり」
という論語の一節を引用します。
これは「正しいことだと分かっていながら実行しないのは、勇気がない証拠だ」という意味です。つまり、遊女たちを助けるために本を出した夫は正しいことをしたのだと、おていは主張したのです。
「仁の道に損なわぬお裁きを。願い出る次第に」
というおていの言葉には、夫への深い愛と信頼、そして武家の娘としての誇りが込められていました。視聴者からは「おていさん強い」「涙が止まらない」といった感動の声が続出しました。
身上半減の刑|前代未聞の処罰と蔦重の戯け
京伝は手錠50日、蔦重は身上半減
定信の裁きが下されます。
「みだらなる風俗を描き、地中の風紀を乱した罪により、伊勢屋清、陽明には、みだらなる書物を発行し、風紀を乱した罪。および、手錠50日」
京伝には手錠50日という刑罰が下されました。そして蔦重には「身上の半分召し上げる」という前代未聞の処分が言い渡されます。
蔦重は
「いやあ、俺はふじよりたかぎ、ありがたい山にございます」
と、相変わらずの調子で応じます。お奉行所は
「以後は心を入れ替え、真に世のためとなる本を出すことを望んでの沙汰である」
と告げますが、蔦重の反応は予想外でした。
煽る蔦重に見かねたおていの平手打ち
「真に世のため、それが難しいんですよね。私は真に世のためとは何か、お公家様一度膝を詰めて」
蔦重はここでも煽るような発言をします。身上半減という重い刑を受けながら、まったく懲りていない様子に、おていはついに堪忍袋の緒が切れました。
「べらぼう!」
おていは涙を流しながら、蔦重の頬を力いっぱい平手打ちします。この場面は、妻としての愛情と、夫の無謀さへの怒りが入り混じった、感動的なシーンでした。
橋本愛さんの涙目と力強い平手打ちの演技が素晴らしく、SNSでは「おていの平手打ちに泣いた」「べらぼう!が最高」といった投稿が殺到。このシーンが第39話の最大の見せ場の一つとなりました。
扇谷の親父様が見守る中、おていが泣きながら夫を叱る姿は、武家の娘としての矜持と、一人の女性としての強さを同時に感じさせるものでした。
おていの「べらぼう!」と鶴屋の本気ギレ|仲間の愛ある叱責
おていの涙と「べらぼう!」の平手打ち
牢から解放された蔦重は、おていや鶴屋たちに礼を述べます。しかし、蔦重の態度は相変わらず軽く、事の重大さを理解していないように見えました。
おていの平手打ちは、夫への深い愛情から来るものでした。命を懸けて漢詩で対抗し、夫を守ろうとしたおてい。それなのに、蔦重は煽るような発言を続け、さらなる危険を招きかねない行動を取ったのです。
というSNSの投稿が、まさにこの場面の本質を捉えています。
おていの涙は、怒りだけでなく、安堵と心配と愛情がすべて混ざったものでした。視聴者の多くが「おてい格好いいし泣ける」と共感し、この場面が大きな話題となりました。
鶴屋の「ほんと、そういうところですよ!」が話題沸騰
さらに追い打ちをかけるように、普段は温厚な鶴屋(風間俊介)も本気で怒ります。
「ほんと、そういうところですよ!」
この一言が、視聴者の心に深く刺さりました。いつも笑顔で蔦重を支えてきた鶴屋が、ここまで本気で怒ったのは初めてです。
鶴屋は仲間として、友人として、蔦重の無謀さを心から心配していました。吉兵衛さんと新右衛門さんは江戸払いになり、まさのぶも謹慎を受けています。蔦重の行動が、どれだけ多くの人に影響を与えているかを、鶴屋は痛感していたのです。
というSNSの投稿通り、この場面は鶴屋のキャラクター崩壊とも言える衝撃的なシーンでした。
風間俊介さんの迫真の演技に、視聴者からは「鶴屋さんキレたのエモい」「本気の友情」「涙腺崩壊」といった声が続出。おていと鶴屋、二人の「愛ある叱責」が、蔦重への深い愛情と信頼を物語る名シーンとなりました。
身上半減から起死回生へ|蔦重の商才が光る復活劇
店も暖簾も半分に|「半減の蔦屋」が江戸の名所に
身上半減とは、財産の半分を没収されるという刑罰です。蔦重の蔦屋は文字通り、店も商品も暖簾さえも半分に切り取られてしまいました。
店を訪れた仲間たちは、その徹底ぶりに驚きます。
「売れ筋の品や板ばっかり持って、いきやがって」
「本当に半分だね。暖簾まできっちり半分ですよ。実に褌の記帳面さがうかがえる」
店内には畳も半分しかなく、商品も半分しか残っていません。普通なら、これで商売は終わりです。
しかし、蔦重は違いました。
「半分でも十分じゃないですか?品も半分しかないんだし」
蔦重は、この「身上半減の蔦屋」を逆に宣伝材料にしてしまったのです。
なんぽう先生の励ましと蔦重の決意
そこへ、なんぽう先生(桐谷健太)が様子を見に来ます。相変わらず戯けているなんぽう先生の姿に、場の雰囲気が和みます。
蔦重の商才は見事に発揮されました。「世にもまれな処分を受けた店を一目見ておこうと、人が集まり、そこで残っておる品などを売っておる」という状況が生まれたのです。
「半減の蔦屋、江戸の名所となる吉」
「市中で売れている」
まさのぶの名も、手錠にあったことでより広く知れ渡りました。定信の家臣は
「もう少し重い刑でもよろしかったのでは?」
と進言しますが、定信は
「半減は決して軽くはない。その身にじわじわと効いてくるはずだ」
と諭します。
しかし蔦重は「半減を決して軽くはない」と受け止めつつも、それを逆手に取って起死回生を図ります。この「転んでもただでは起きない」精神こそ、蔦重の真骨頂でした。
視聴者からは「蔦重の商才すごい」「さすが」「面白すぎる」といった称賛の声が上がり、ピンチをチャンスに変える蔦重の姿勢に多くの人が勇気をもらいました。
長谷川平蔵の登場|「火付盗賊改方、長谷川平蔵である!」
青い小僧事件と平蔵の颯爽とした登場
物語の終盤、長谷川平蔵(中村隼人)がついに登場します。
「直ちにお耳に入れたいと、長谷川参っております」
平蔵は、青い小僧と名乗る盗賊団が江戸を荒らし回っていることを定信に報告します。
「上様と見まごうばかりの行列を仕立て、休ませてほしいと家の戸を開けさせ、必ず、その家の妻や娘を恥ずかしめていく」
という卑劣な手口に、定信も
「直ちに捉えよ」
と命じます。
そして、平蔵の決めゼリフが炸裂します。
「火付け盗賊、改め方を、長谷川平蔵である」
この颯爽とした登場シーンに、視聴者は大興奮。SNSでは「平蔵、出番だ!」「待ってました!」「カッコいい」といった投稿が殺到しました。
時代劇ファンなら誰もが知る「鬼平犯科帳」の主人公、長谷川平蔵。その登場は、ファンサービス的な意味合いもありながら、物語の重要な転換点を示すものでもありました。
改革の歪みが生んだ犯罪の増加
平蔵によって青い小僧一味は捕らえられますが、その背景には定信の改革の歪みがありました。
「不景気により雇い止めにあった者」
「宿の取り壊しで、職からあぶれた者たちが、多様な凶行に走った」
改革によって職を失い、行き場を失った人々が犯罪に走ってしまったのです。これは蔦重が言っていた「人は楽しく生きたい」という言葉の裏返しでもあります。
定信は
「不景気で人が、その中には田畑を捨ててきた流れ者が大勢いる。その者らを百姓に戻すさすれば、荒廃した田畑は蘇り、あるべき世の形となる」
と提案しますが、
本多忠籌:「その仕組み、使いたいと申し出たのは、たったの4人でございます」
という結果に。
人々は
「年貢を納め、土間の上で、娘を売らざるを得ぬような暮らしには戻りたくない。悪事を働こうと江戸にいたい」
と考えていました。
最後に
「このままでは、田沼以下の祭りごととのそしりを受けかねませぬ」
という言葉で終わり、定信の改革の限界が示唆されました。長谷川平蔵の登場は、単なるヒーロー的な演出ではなく、改革の功罪を描く重要な役割を果たしていたのです。
6. まとめ|第39話の見どころと伏線
第39話「白河の清きに住みかね身上半減」は、表現の自由をめぐる蔦重と定信の対立が頂点に達した回でした。見どころと今後の伏線を整理します。
- おていの漢詩バトルと「べらぼう!」:論語を駆使して夫を守ろうとしたおていの知性と強さ、そして愛情からの平手打ちが感動を呼びました。武家の娘としての誇りと、一人の妻としての人間性が見事に描かれた名シーンです。
- 鶴屋の本気ギレ「ほんと、そういうところですよ!」:温厚な鶴屋がここまで怒ったのは初めて。友情と心配、そして信頼が込められた叱責に、視聴者の涙腺が崩壊しました。
- 「人は楽しく生きたい」という蔦重の信念:正しさよりも楽しさを求める人々。その欲求に応えることが文化を支えるという蔦重の哲学が、改革の是非を問う重要なテーマとして描かれています。
- 身上半減から起死回生へ:ピンチをチャンスに変える蔦重の商才が光りました。「半減の蔦屋」が江戸の名所となり、話題作りで店を復活させる展開は、蔦重の真骨頂です。
- 長谷川平蔵の登場と改革の歪み:「火付盗賊改方、長谷川平蔵である!」の名乗りで颯爽と登場した平蔵。青い小僧事件を通じて、改革によって職を失った人々が犯罪に走る社会問題が描かれ、定信の改革の限界が示唆されました。
- 歌麿の今後:つよと共に栃木へ向かった歌麿。心の傷が癒えるのか、そして蔦重との関係はどうなるのか、今後の展開が気になるところです。
次回第40話「尽きせぬは欲の泉」では、津田健次郎さんの謎の役や、くっきー!演じる葛飾北斎の登場が予告されており、ますます目が離せない展開となりそうです!