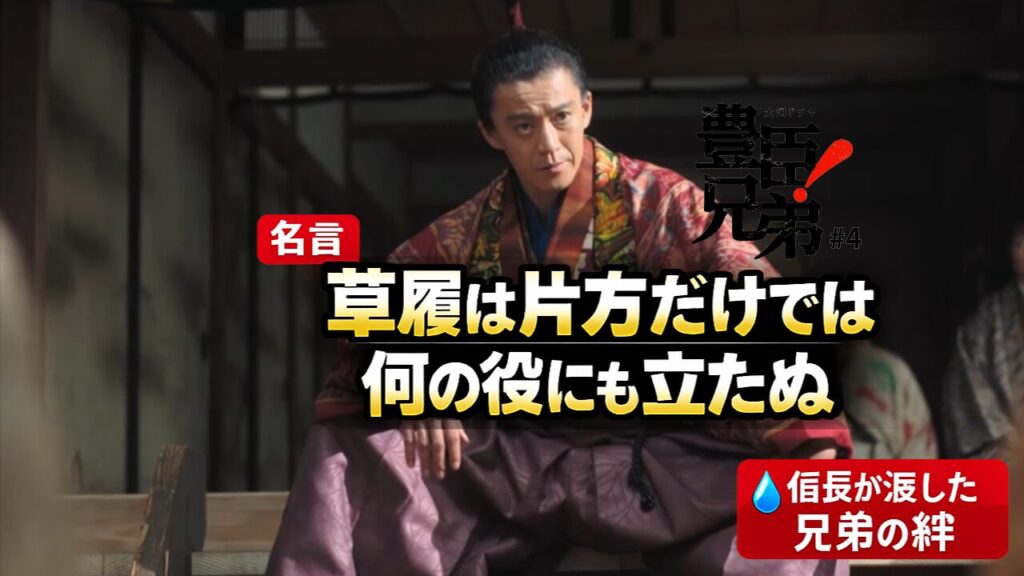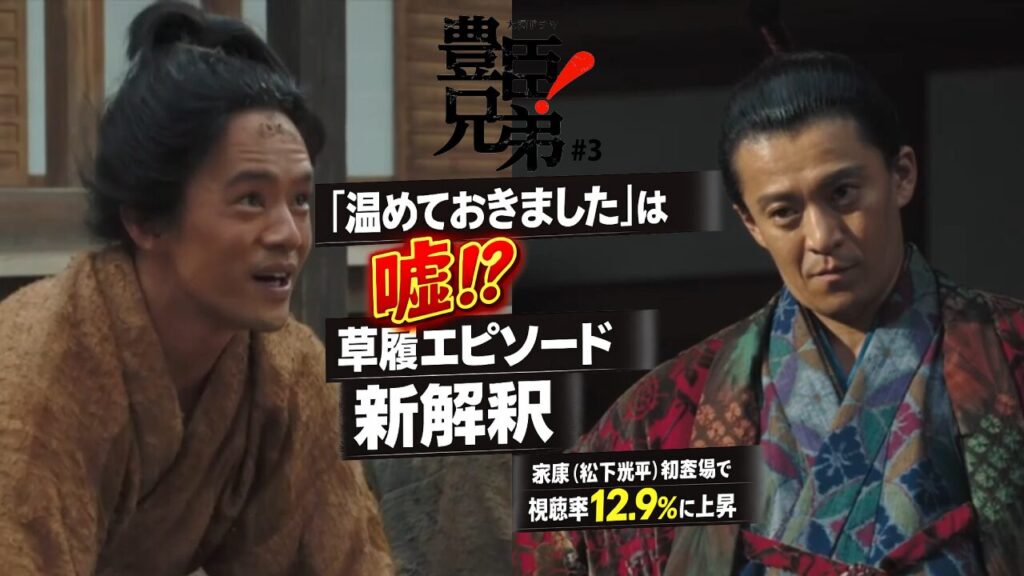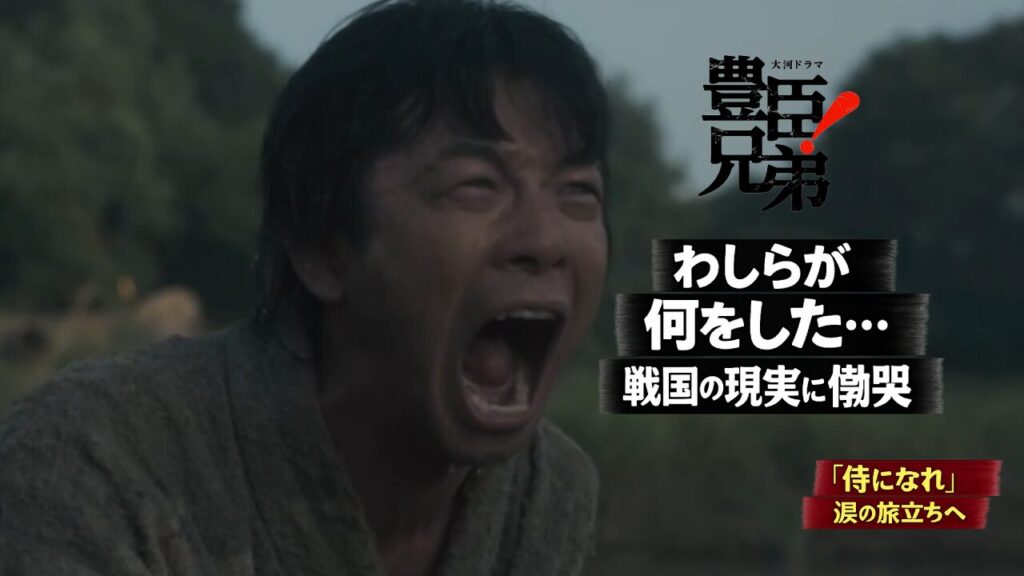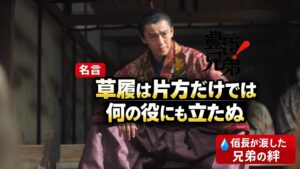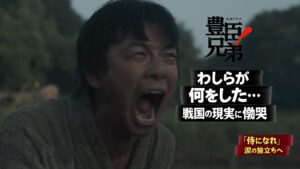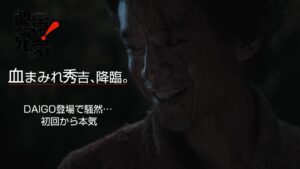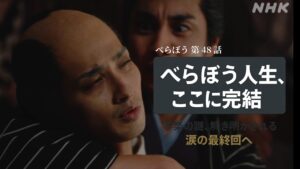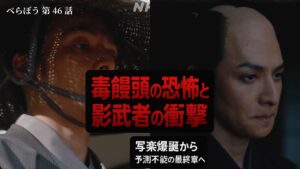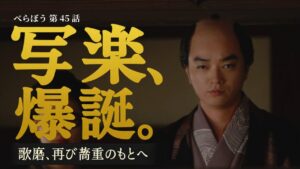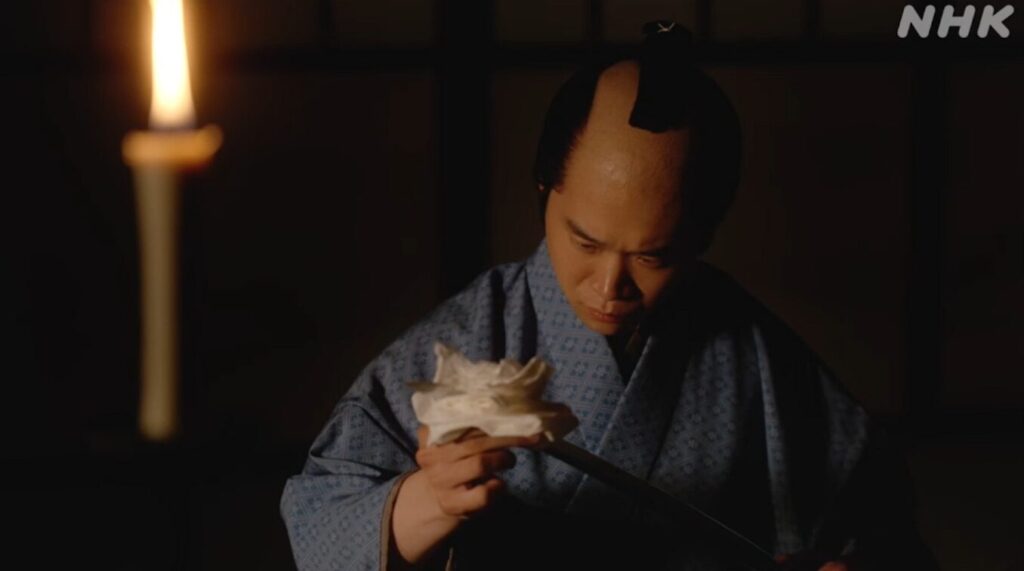
【べらぼう第27話 感想・考察・ネタバレ】 あらすじ
NHK大河ドラマ「べらぼう」第27話「願わくば花の下にて春死なん」が放送され、SNSでは視聴者の悲痛な声が相次いでいます。佐野政言(矢本悠馬)の追い詰められた心理状態と、田沼意知(宮沢氷魚)と誰袖(福原遥)の幸せな身請け話が対照的に描かれた今回。一橋治済(生田斗真)の巧妙な策略により、佐野は次第に田沼への憎悪を募らせていきます。
米価暴騰に苦しむ江戸の庶民を救うため、蔦重(横浜流星)らが知恵を絞る一方で、佐野家では認知症を患う父・政豊(吉見一豊)の暴走により家庭は崩壊状態に。治済の放った丈右衛門が巧みに佐野の心を操り、「田沼が佐野家の系図を亡き者にした」「家宝の桜を盗んだ」という虚偽の情報を吹き込みます。追い詰められた佐野は「私が咲かせてご覧に入れましょう」と狂気じみた決意を固め、刀の手入れを始めます。
ラスト5分、意知が誰袖との幸せな花見を約束した直後、佐野が意知に声をかけ刀を振るうシーンで次回へ。視聴者からは「鎌倉殿メソッド」「絶望的な展開」と森下佳子脚本の手腕を評価する声と、悲劇的結末への恐怖の声が交錯しています。
佐野政言を追い詰める一橋治済の巧妙な策略
NHK大河ドラマ「べらぼう」第27話「願わくば花の下にて春死なん」は、視聴者にとって忘れ難い衝撃的な回となりました。特に佐野政言(矢本悠馬)を巧妙に操る一橋治済(生田斗真)の策略は、まさに「鬼畜」と呼ばれるほどの緻密さを見せつけました。
鷹狩りでの仕掛けと丈右衛門の暗躍
物語の転換点となったのは、将軍家の鷹狩りのシーンでした。佐野の鷹だけが見当たらないという「偶然」の出来事から、悲劇の歯車が回り始めます。意知が気を遣って林に探しに行き、将軍から褒められるシーンで、佐野の表情が微妙に変化する演出が秀逸でした。
「申し訳ございません。上様並びにこの場の皆様をお待たせいたしましたことを、深く、お詫び申し上げます」
意知のこの謝罪の言葉は、本来なら美談として語られるべきものでした。しかし、この瞬間を見逃さなかった丈右衛門の存在が不穏さを醸し出します。治済の放った刺客ともいえる丈右衛門は、佐野の心の隙を狙い撃ちにします。
「えなりん道廣のわざとらしい訴えに好機逃さぬ傀儡使い治済、弱りきった佐野政言を虚言巧みに操る鬼畜(脚本が)」
という投稿が示すように、視聴者は治済の冷酷さを「鬼畜」と表現するほどの衝撃を受けています。
「田沼が系図を奪った」虚偽情報の威力
丈右衛門が佐野に吹き込んだ嘘は、巧妙に真実と虚偽を織り交ぜたものだった。佐野家の系図が紛失したという事実に、「田沼が亡き者にした」という虚偽を混ぜ込む手法は、現代のフェイクニュースの構造そのものでした。
「田沼様が佐野殿の大切な系図を預かると偽り、なきものにした」
この丈右衛門の言葉に、佐野は一度は「偽りだ」と否定するものの、弱り切った心理状態では冷静な判断ができません。さらに追い打ちをかけるように、家宝の桜についても「元は佐野殿の桜ではございませんか」と畳み掛けます。
佐野政言が田沼を恨んだ理由は本当にあったのか?
史実では佐野政言の田沼への恨みには諸説ありますが、ドラマでは一橋治済の策略による虚偽情報が主因として描かれています。これは現代社会における情報操作の危険性を暗示する脚本の巧みさといえるでしょう。
田沼意知と誰袖、身請け話に見る希望と絶望
佐野の絶望と対照的に描かれたのが、田沼意知(宮沢氷魚)と誰袖(福原遥)の関係でした。身請け話が進展する喜びと、それを取り巻く不安定な状況が、視聴者の感情を大きく揺さぶりました。
「土山の名で身請け」意知の苦肉の策
米価が下がらず、田沼家への風当たりが強まる中で、意知は苦渋の決断を下します。表向きは土山の名前を使って誰袖を身請けするという提案は、現代的な感覚では理解しがたいかもしれませんが、当時の社会情勢を考えれば現実的な選択でした。
「土山の名でその後はお見受けしてしまおうと考えた。当面、表向きは土山の妾ということになるが、それでも良いと思ってくれるならば、申し出を受けてもらいたい」
この意知の提案に込められた複雑な心境は、宮沢氷魚の繊細な演技によって見事に表現されました。体面を保ちながらも誰袖への愛情を貫こうとする意知の姿に、多くの視聴者が心を動かされました。
「体面ばかり繕い、情けない話だが、今年の春はソナタと2人花の下で月見をしたい」
この言葉には、意知の率直な気持ちが込められています。タイトルの「願わくば花の下にて春死なん」への伏線ともなるこのセリフは、後の展開を知る視聴者にとって特に胸に迫るものがありました。
誰袖の幸せそうな「んふ」が視聴者の心を刺す
文を読み終えた誰袖の表情と、その後の幸せそうな様子は、福原遥の魅力が最大限に発揮されたシーンでした。特に「んふ」という何気ない反応が、SNSで大きな話題となっています。
「すっかりお気に入りで」
たが袖のこの何気ない言葉と、その後の膝枕シーンは、視聴者に「バブみ」を感じさせるほどの温かさを演出しました。しかし、この幸せな時間が長くは続かないことを知っている視聴者にとって、この場面は切なさを増幅させる効果を持ちました。
「ひざまくらでバブみを感じる意知」「誰袖の幸せそうな『んふ』が辛すぎる」といった投稿からは、視聴者がこのシーンに深い愛情と同時に不安を感じていることが伝わってきます。
米価暴騰問題に見る江戸時代と現代のリンク
今回のエピソードで特に注目されたのは、米価暴騰という社会問題の描き方でした。森下佳子脚本の真骨頂ともいえる、歴史と現代を繋ぐ視点が随所に散りばめられています。
蔦重らが提案する「政としての米販売」
日本橋の商人たちが知恵を絞って考え出した解決策は、まさに現代の政策論議を思わせるものでした。蔦重(横浜流星)が意知に提案する内容は、単なる商売ではなく「政」としての位置づけでした。
「商いと申しましても、儲けを出すわけではございません。仕入れた値で引き渡すのみ」
「恐れながらこれは政にございます」
この蔦重の言葉は、現代の社会保障制度やセーフティネットの概念を先取りしたものとして注目されます。利益を追求しない公的な米販売という発想は、現代の食料安全保障問題にも通じる普遍的なテーマではないでしょうか。
格差社会の描写に見る森下佳子脚本の真髄
「愚民は肩を寄せ合っております。飢えるまでではなくても、食うことに精一杯、不信は諦め、10日に一度床屋もいいとなる。そうやってどんどんどんどん金の巡りが悪くなる」
この蔦重の分析は、まさに現代の経済学における需要不足の悪循環を的確に表現しています。江戸時代の米価問題を通じて、現代の格差社会や経済問題を浮き彫りにする脚本の巧みさは、多くの視聴者に印象を与えました。
SNSでは 「米の転売ヤー摘発、リアルタイムすぎ」という投稿が示すように、視聴者は江戸時代の問題が現代と重なることに驚きを示しています。
べらぼうで描かれる米価問題は現代と関係あるのか?
森下佳子脚本は意図的に現代の社会問題とリンクさせています。格差拡大、投機的な買い占め、セーフティネットの必要性など、江戸時代を通じて現代社会への問題提起を行っているのが特徴です。
佐野家の崩壊と父親の認知症描写
今回のエピソードで最も衝撃的だったのは、佐野家の家庭内での悲劇的な状況だった。特に佐野の父親(吉見一豊)の認知症の症状が暴力的になっていく様子は、多くの視聴者に強い印象を残しました。
吉見一豊の鬼気迫る演技に視聴者戦慄
「咲け〜咲け〜」
桜の木に向かって刀を振るう父親の姿は、認知症の症状として現実にも見られる行動パターンです。吉見一豊の演技は、ただ狂気を演じるのではなく、病気による混乱と、息子への愛情の歪んだ表現を見事に表現していました。
「ようきた、要来てくれた、弁之助と、そなたが来てくれたら安泰だ」
この父親の言葉は、現実と幻想が混在する認知症患者の典型的な症状を表していました。息子の佐野を別の人物と勘違いしながらも、家族への愛情は失われていないという複雑な心境が描かれています。
「私が咲かせてご覧に入れましょう」狂気の決意
泣き崩れる佐野が最後に口にした言葉は、彼の心の完全な破綻を示すものでした。
「父上、私が、咲かせてご覧に入れましょう」
この言葉を発する時の矢本悠馬の表情は、まさに「何か壊れたような」ものでした。父親の期待に応えたいという孝行心と、現実逃避、そして復讐心が混在した複雑な感情が表現されていました。
SNSでは 「佐野殿、鬼滅か忍極の悲しき過去持ちだろ」という投稿が示すように、視聴者は佐野の悲劇的な背景を他のフィクション作品の悲劇的キャラクターと重ね合わせて理解している視聴者もいました。
佐野政言の父親の病気は何か?
ドラマでは認知症(当時は「ぼけ」と呼ばれた)として描かれています。暴力的な症状も含めて、現代の認知症ケアでも課題となる問題を歴史ドラマの中で扱った意欲的な演出といえます。
ラスト5分の衝撃展開と次回への期待
「べらぼう」第27話の最大の見どころは、やはりラスト5分の急展開です。森下佳子脚本の真骨頂ともいえる「絶望的な急転直下」が、多くの視聴者に強烈な印象を残しました。
意知との対峙シーンで終わる絶妙なタイミング
刀の手入れをする佐野の静かな決意の表情から、意知と誰袖の幸せそうな花見の約束、そして最後の佐野が意知に声をかけるシーンまでの流れは、まさに計算し尽くされた構成でした。
「今日は花の下で月を見よう」
誰袖のこの言葉は、タイトルの「願わくば花の下にて春死なん」との関連を強く示唆しています。視聴者は幸せな二人の様子を見ながらも、迫りくる悲劇を予感せざるを得ません。
「山城の神様」
佐野が意知に声をかけるこの最後のシーンで、視聴者は息を呑みました。二人の立場や心境の違いが、この一言に込められているのです。
「鎌倉殿メソッド」と呼ばれる森下脚本の手法
SNSでは 「ラスト5分で絶望させる鎌倉殿メソッド」という表現が示すように、視聴者は森下佳子脚本の特徴的な手法を「鎌倉殿の13人」と関連付けて理解していました。
この手法の特徴は、視聴者に希望を抱かせた直後に絶望的な展開を提示することです。意知と誰袖の身請け話が成立し、二人が幸せな未来を語り合った直後に、佐野の復讐が迫っているという構成は、感情の振れ幅を最大限に活用した演出といえます。
べらぼうの森下佳子脚本の特徴は何か?
歴史と現代を繋ぐ視点、登場人物の心理描写の深さ、そして急転直下の展開が特徴です。特に「希望と絶望のコントラスト」を効果的に使う手法は、視聴者の感情を強く揺さぶります。
次回への期待と考察
第27話の結末を受けて、次回第28話「佐野世直大明神」への期待は高まるばかりです。史実を知る視聴者にとって、佐野政言と田沼意知の悲劇的な運命は避けられないものですが、ドラマがどのように描くかに注目が集まっています。
ポイント
- 誰袖の身請け話は実際にどうなるのか
- 佐野の復讐はどのように描かれるのか
- 一橋治済の最終的な目的は何なのか
- 蔦重や他の登場人物たちはどう関わってくるのか
SNSでは 「この状態で来週おあずけなの無理なんだけど????」という投稿が示すように、視聴者の次回への期待は非常に高いです。
そして、次回放送日は7月20日ではなく7月27日となり、このラストシーンから1週置くことに対しても様々な声が投稿されてます。
森下佳子脚本が描く「べらぼう」は、単なる歴史ドラマを超えて、現代社会への問題提起を含んだ深い作品として多くの視聴者に愛されています。第27話「願わくば花の下にて春死なん」は、その集大成ともいえる回として、大河ドラマ史に刻まれる名エピソードとなりそうです。
特に佐野政言の悲劇は、現代社会における情報操作や格差問題、そして介護問題など、多層的なテーマを内包しています。視聴者がこのドラマに強い共感を示すのは、江戸時代の物語でありながら、現代を生きる我々の課題と深く繋がっているからに他ならないからです。
再来週の放送まで、SNSでは様々な考察や感想が飛び交うのではないでしょうか。「べらぼう」が提示する問題は、視聴後も長く視聴者の心に残り続ける、真に価値ある作品の証明といえます。
まとめ:第27話の見どころと重要な伏線

- 佐野政言の心理的崩壊:一橋治済の策略により虚偽情報を信じ込み、「私が咲かせてご覧に入れましょう」と狂気の決意を固める展開は、次回の悲劇的結末への重要な伏線
- 意知と誰袖の身請け成立:「土山の名で」という条件付きながら身請けが決まり、「花の下で月見を」という約束が、タイトル「願わくば花の下にて春死なん」と直結する不吉な予兆
- 森下佳子脚本の「鎌倉殿メソッド」:幸せなシーンの直後に絶望的展開を予感させる構成で、ラスト5分の佐野と意知の対峙シーンは視聴者を戦慄させた
- 現代社会との重なり:米価暴騰問題を通じて格差社会や情報操作の危険性を描き、「米の転売ヤー摘発」など現代的テーマを巧みに織り込んだ
- 認知症を患う佐野の父親:吉見一豊の鬼気迫る演技で描かれた暴力的な症状は、佐野を追い詰める要因として機能し、現代の介護問題への問題提起も含んでいる
- 史実への橋渡し:誰袖の身請け話での「土山」の名前使用は史実との巧妙な接続点となり、視聴者の歴史への興味を深める仕掛けとして機能している