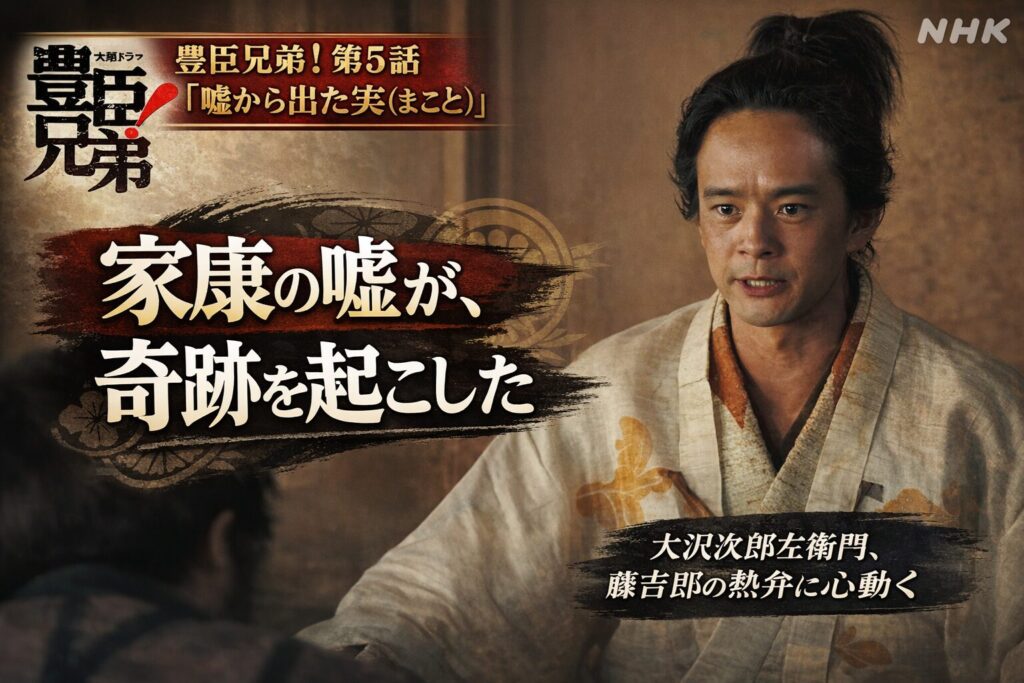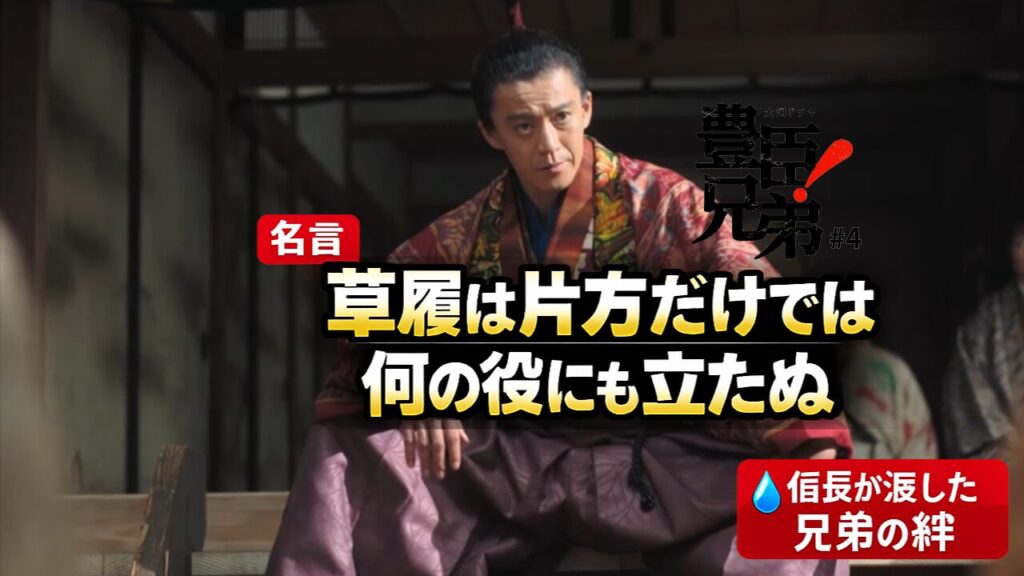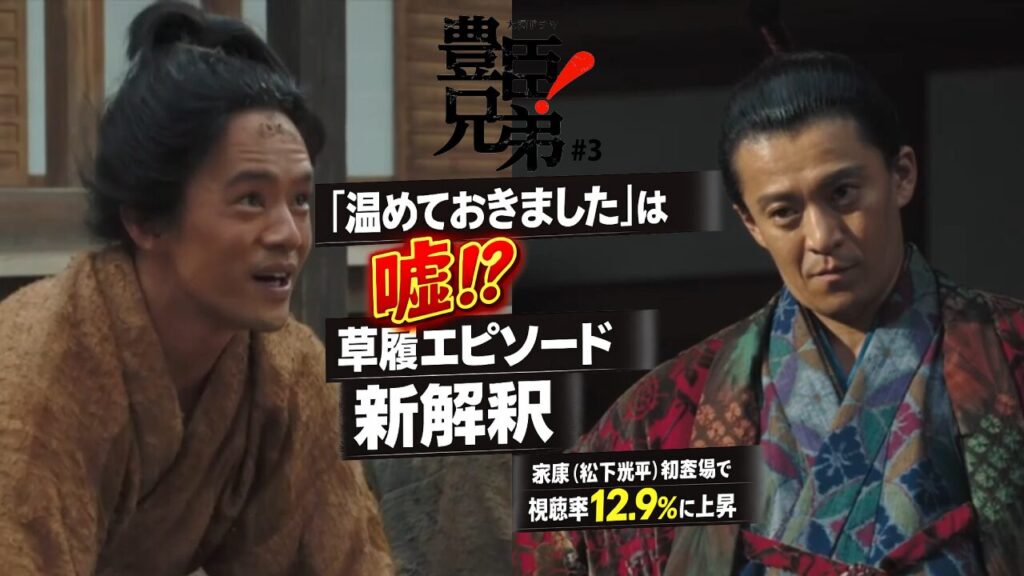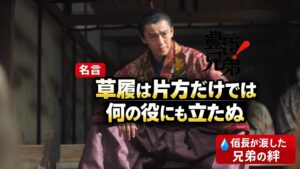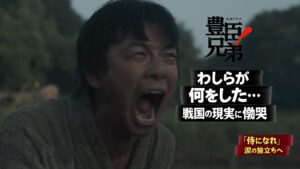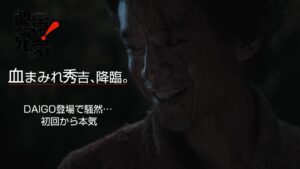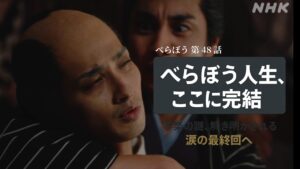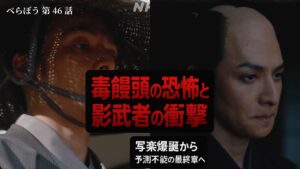大河ドラマ「べらぼう」第42話「招かれざる客」が放送され、SNSでは歌麿(染谷将太)と蔦重(横浜流星)の関係に亀裂が入る展開に涙する声が殺到しています。身上半減から立ち直った蔦重は、てい(橋本愛)の妊娠という喜びに包まれる一方、商売優先の姿勢が歌麿を追い詰めることに。そして、西村屋の二代目・万次郎(中村莟玉)の登場が、二人の運命を大きく変えていきます。定信(井上祐貴)の政治的孤立、爆笑問題・クールポコの新年コメディ、母・つよの死と新しい命の誕生…喜びと悲しみが交錯する第42話を徹底解説します。
べらぼう第42話 あらすじ
身上半減から店を立て直した蔦重は、ていの懐妊を知り喜びに浸る。一方、幕府では定信がロシア問題で孤立し、美人画規制へと動き出す。新年を迎え、看板娘ブームで江戸は活気づくが、商人たちからの注文が殺到し、歌麿は創作への想いと商売のはざまで苦悩する。蔦重は身上半減時の借金返済のため、歌麿に50枚の美人画を依頼。子どもの誕生を理由に頭を下げる蔦重に、歌麿は承諾するものの、その背中には深い悲しみが滲む。そんな中、西村屋の二代目・万次郎が歌麿の元を訪れ、「美男揃え」という新しい企画を提案。蔦重との縁を切る決意を固めた歌麿の表情がクローズアップされ、決裂の予感が漂う…。
つよの死と新しい命の誕生-喜びと悲しみが交錯する蔦屋の新年
第42話は、母・つよの死という悲しみから幕を開けました。偲ぶ会には歌麿や菅原屋の旦那、そして吉原の面々が集まり、つよの遺影の前で手を合わせます。
会の中で、蔦重は商売の話を切り出します。吉原の入銀についてりつ(安達祐実)と交渉し、
「入銀を4両で」
と提案。最終的には
「1両はつよへの弔電かね」
という形で3両に落ち着きます。この交渉シーンは、蔦重の商売人としての冷静さと、母への思いを両立させようとする姿が印象的でした。
しかし、つよの偲ぶ会は次第に奇妙な雰囲気に。参列者たちが「つよのご加護を」と崇め始め、まるで神格化するかのように願いを唱える展開に。この描写は、江戸時代の庶民信仰の一面を表しながらも、どこかコミカルで、シリアスとユーモアが絶妙に混ざり合っていました。
「お口巾着で」ていの妊娠告白に込められた想い
場面は蔦重とていの夜の会話へ。ていがマッサージを受けながら頭を押さえる姿を見て、蔦重は不安を隠せません。つよと同じような症状だったからです。
「医者に診てもらえ」
と心配する蔦重に、ていは真剣な表情で向き合い、告白します。
「子ができたのでございます」
この一言に、蔦重の表情が一変。喜びと驚きが入り混じった表情は、横浜流星の繊細な演技が光る場面でした。ていは続けて
「恥ずかしい、孫がいてもおかしくない歳で」
と照れながらも、幸せそうに微笑みます。
そして二人は口裏を合わせます。
「とにかくお口巾着」
——この言葉は、二人だけの秘密を守る約束。しかし、実は巳之吉たちにはすでに話していたことが明かされ、蔦重が少しヤキモチを焼く様子も微笑ましい。
この夫婦の会話の中で、二人は
「つよの生まれ変わりなんじゃないか」
と思いを巡らせます。母の死と子の命が重なる瞬間——人生の儚さと希望が同時に描かれた、この回の核心的なテーマがここに凝縮されていました。
「おっかさんの生まれ変わり」つよへの祈りと再生の希望
SNSでは、この妊娠のシーンに多くの視聴者が涙したようです。「母上の生まれ変わり」という考えは、江戸時代の輪廻思想を反映しながらも、現代の私たちにも響く普遍的な願い。大切な人を失った悲しみを、新しい命の誕生で乗り越えようとする蔦重とていの姿に、多くの人が共感しました。
一方で、ていの年齢を考えると高齢出産のリスクも懸念されます。次回予告では出産シーンが描かれる様子も。この妊娠が喜びだけでなく、新たな試練の始まりになる予感も漂わせています。
夜、寝る前にていが
「お腹の子が動いた」
と蔦重に声をかけ、蔦重は喜びを隠せず
「べらぼうめ」
とつぶやきます。このタイトルにもなっている「べらぼう」という言葉が、幸せな瞬間に使われる対比が、何とも言えない余韻を残しました。
爆笑問題×クールポコが贈る新年の笑い!看板娘ブームで江戸が沸く
シリアスな展開が続く中、新年のシーンでは一転してコメディ要素が炸裂。クールポコが餅つきをしている場面に、爆笑問題の太田光が手相占い師「開運先生」として登場します。
「やっちまったな」開運先生・太田の縁起担ぎ
太田演じる開運先生は、
「やっちまったな」
というクールポコの定番ネタを披露。芸人のネタをそのまま劇中で使うという遊び心満載の演出に、SNSでは「爆笑問題」「クールポコ」がトレンド入り。視聴者からは「ただの爆笑問題すぎる」「開運先生のキャラ濃すぎ」と、楽しむ声が相次ぎました。
蔦重の店は身上半減から立ち直り、
「畳を入れられるようになった」
と喜ぶ様子も。身上半減の棚は返上となり、店は再び活気を取り戻します。この明るい雰囲気が、後半のシリアスな展開とのコントラストを生み出し、物語にメリハリをもたらしています。
一ツ橋治済までお忍び参戦!48文の茶屋に並ぶ幕閣たち
そして、この回の見どころの一つが「看板娘ブーム」。歌麿が描いた美人画をきっかけに、江戸中に看板娘ブームが巻き起こります。難波屋おきたの店には長蛇の列ができ、なんと
「一杯48文」
という価格設定に老中たちが驚く場面も。
さらに驚くべきは、一ツ橋治済が変装して列に並んでいる姿。権力者でありながら庶民の楽しみに身を投じる治済の姿は、この時代の「お忍び文化」をユーモラスに描いていました。
老中の本多忠籌や松平信明までもが変装して訪れる展開に、SNSでは「このドラマのお殿様、気軽にお忍びしすぎ」という声も。歌麿が描いた絵が権力者から庶民まで魅了する様子は、蔦重の商売の嗅覚の鋭さと、歌麿の才能の凄さを改めて感じさせるシーンでした。
背景では瑣吉が偉そうなポーズを取っていたり、ニヤニヤと眺めていたりと、細かい演出も話題に。こうした遊び心が、重いテーマを扱う中での息抜きとして機能していました。
定信の孤立と美人画規制-「ならぬ!」と叫ぶ独裁者の闇
一方、城中では定信の孤立が深刻化していました。井上祐貴が演じる定信は、幕閣の中で次第に孤立し、追い詰められていきます。
ロシア来航で揺れる幕府、朝廷からの嫌味に歪む定信の表情
ネモロ(現在の根室)にロシア船が来航したという報告を受けた幕閣。老中たちは通商を認める方向で意見が一致しますが、定信は
「ならぬ!」
と声を荒げます。この一言には、彼の頑なな姿勢と、孤立への焦りが滲み出ていました。
定信の表情が歪むカットは、まるで彼の内面が崩れていく様子を象徴しているかのよう。この演出について、SNSでは「血管がブチ切れる定信」「独裁者の孤独」といった声が上がりました。
さらに、朝廷への援助を打ち切ると宣言する定信。しかし朝廷の使者からは嫌味を言われ、定信は疑心暗鬼に陥っていきます。この政治的な駆け引きは、現代の権力闘争にも通じるリアリティがあり、
「現代に通ずるネタが多過ぎて…あの脚本予言の書なの?」
という視聴者の声も納得です。
「また蔦屋か」田沼病の復活と美人画への規制強化
見かねた老中たちは、一ツ橋治済に進言します。治済は歌麿が描いた女性の絵を見ながら話を聞き、
「この娘、大層美しいらしいぞ」
と話を逸らすように言います。この軽妙な態度が、定信の硬直した姿勢と対照的で、治済の人間的な魅力を際立たせていました。
しかし、閣議の場面で定信は、蔦屋の刻印が目に入り
「またあのものか」
と怒りを露わにします。田沼意次の時代の「田沼病」が息を吹き返しているという老中の言葉に、定信の顔はさらに歪みます。
そして定信は、美人画への規制を決断。吉原の遊女の名前しか書けなくなるという、厳しいお達しを出します。この規制は、蔦重や歌麿にとって大きな打撃となり、物語の転換点となっていきます。
定信の孤立は、権力者が陥る「孤独」の象徴。正しいと信じる道を進むあまり、周囲を失っていく姿は、現代のリーダー論にも通じる教訓を含んでいました。
歌麿の苦悩-「一点一点心を込めて描きたい」クリエイターの叫び
看板娘ブームで注文が殺到する中、歌麿は大きな葛藤を抱えていました。この回では、クリエイターとしての歌麿の苦悩が丁寧に描かれ、多くの視聴者の共感を呼びました。
商人たちからの注文殺到、「ひと月でできるわけない」歌麿の怒り
商人たちがこぞって蔦重宛てに美人画の依頼をしてきます。その量に、歌麿は
「ひと月でできるわけない」
と怒りを露わにします。この怒りは、単なる物理的な時間の問題ではなく、作品に対する歌麿の姿勢を表していました。
蔦重が歌麿に助言をしますが、歌麿は不服そうな顔をします。商売人である蔦重と、芸術家である歌麿——二人のすれ違いが、この場面から始まっていました。
蔦重にとって美人画は「商売の一つ」ですが、歌麿にとっては「魂を込めた作品」。この価値観の違いが、二人の関係に亀裂を生んでいく構図が、視聴者にも痛いほど伝わってきます。
重正先生への相談「身勝手なのだろうか」揺れる芸術家の心
重正先生にも、女性の絵を描いてほしいという商人たちが押し寄せているとのこと。この状況は、歌麿だけの問題ではなく、当時の絵師たち全体が抱えていた課題だったことがわかります。
歌麿は重正先生に相談します。
「一点一点心を込めて描きたい、蔦重たちにもわかってほしいが、そう思うのが身勝手なのだろうか」
と自問自答する歌麿。この言葉には、クリエイターとしての誇りと、商売の現実とのはざまで苦しむ姿が凝縮されていました。
重正先生は明確な答えを出しませんが、考え込む歌麿の表情が長くクローズアップされます。この沈黙の演出が、歌麿の内面の揺れを雄弁に語っていました。
SNSでは「歌麿はいい奴すぎるし蔦重はちょっと甘え過ぎだよね」という声が。確かに、蔦重は歌麿の才能に頼りすぎている面があり、その依存関係が次第に歪んでいく様子が、この回の重要なテーマとなっています。
さらに、歌麿が弟子に絵を描かせる場面も。これは、ルネサンス期の工房体制のように、師匠の名前で弟子が作品を量産する手法です。しかし、歌麿自身は「不服」な様子。アーティストとしてのプライドと、現実的な要求との板挟みが、彼を苦しめていました。
蔦重の無茶振りと歌麿の限界-「子どもも生まれる」の一言が決定打に
そして、物語は大きな転換点を迎えます。美人画規制のお達しが出たことで、蔦重は窮地に立たされます。
「入銀なしで借金チャラ」吉原への頭を下げる蔦重の苦境
鶴屋がやってきて、蔦重に厳しい現実を告げます。
「絵は描いていいが、相手の名前しか書けなくなる」
という規制が出たとのこと。これは、蔦重の商売にとって大打撃でした。
蔦重は吉原の面々に頭を下げます。
「入銀はなしで、その分の借金を無しにする」
という条件を提示。身上半減から立ち直ったばかりなのに、再び苦境に立たされる蔦重。この場面では、商売人としての厳しさと、人間関係を大切にする蔦重の姿勢が描かれていました。
「100両を50枚で返す」歌麿への依頼に込められた重圧
蔦重は歌麿に相談します。身上半減の時からの借金返済を待ってもらっていたが、
「100両を歌麿の50枚で返す」
という話でまとまったとのこと。
この依頼を聞いた歌麿は、尊い目をして蔦重を見つめます。蔦重がどれほどの重圧を背負っているか、歌麿は理解しています。しかし、50枚という数字は、歌麿にとっても相当な負担です。
歌麿が考え込む長い描写。この沈黙の時間が、歌麿の葛藤の深さを物語っています。そして、蔦重は決定打を放ちます。
「子どもも生まれる」
この一言が、歌麿の心を動かします。いや、動かしたというよりも、追い詰めたと言った方が正確かもしれません。蔦重は歌麿に頭を下げ、切実に頼みます。
「兄さんの言うことは聞かねぇとな、俺は弟だし」
歌麿は何かを決断し、承諾します。しかし、承諾した後の歌麿の背中が、寂し気にクローズアップされます。この演出が秀逸で、歌麿が本心では納得していないこと、何か大きな犠牲を強いられていることが伝わってきました。
SNSでは
「歌さんよく今の蔦重に付き合ってるなーと感心してたところにいつも以上の無茶振りに加え『子が出来た』で何かが切れてしまったご様子」
という声が。まさにこの場面が、歌麿の心に決定的な亀裂を生んだ瞬間だったのです。
「子どもを盾にする横浜流星」という指摘も的確で、蔦重の行動は確かに歌麿を追い詰めるものでした。母・つよがいた頃の蔦重なら、こんな無茶はしなかったかもしれません。「母の存在は偉大だった」という声が多かったのも頷けます。
西村屋二代目・万次郎の登場-「美男揃え」という新たな可能性
そして、運命の転換点となる訪問者が現れます。西村屋と、その二代目となる万次郎です。
「さすが鱗屋の息子」万次郎のアイデアに揺れる歌麿
西村屋が歌麿のもとを訪れ、鱗屋の子である万次郎を紹介します。万次郎は歌麿に、新しい企画を提案します。
「美男揃えという錦絵を出してもらえないか」
これまで美人画ばかりを描いてきた歌麿にとって、美男画は新しい挑戦です。万次郎のアイデアは斬新で、鱗屋の息子らしい発想の豊かさが光ります。「さすが鱗屋の息子だ、アイデアが豊富に出てくる」という評価の通り、彼の提案は歌麿の心を揺さぶります。
さらに、西村屋たちは蔦重の弱みのようなものを話し始めます。歌麿が少し揺れる様子が描かれました。これは、蔦重への不満が積もっていた歌麿にとって、決断を後押しする材料になったのかもしれません。
歌麿は一度、丁重に断ります。
「今日の私がいるのは蔦重のおかげですから」
——この言葉には、蔦重への恩義と忠誠心が込められていました。しかし、最後に歌麿の表情がクローズアップされ、何かが心の中で変化していることが暗示されます。
「蔦屋とは縁を切る」涙の決断に込められた覚悟
そして、ラストシーン。歌麿が手鏡を見つめています。西村屋の二代目・万次郎がやってきて尋ねます。
「歌麿自身を描くのですか?」
歌麿は答えます。
「西村屋さん、お受けしますよ、仕事。この揃い文を書き終わったら、もう蔦重とは終わりにします」
この宣言に、視聴者は衝撃を受けました。新たな道への覚悟と、蔦重への複雑な思いが入り混じっていました。
SNSでは「涙ぐみつつわざわざ『兄さんに』と口にしたのは新たな道への覚悟か」という考察が。確かに、この言葉は単なる決別ではなく、感謝と決意が同居した、歌麿らしい表現だったのかもしれません。
また、「絵描きと商売人のすれ違い方向性の不一致で解散寸前」という声も的確です。クリエイターとビジネスパートナーの関係は、常にこうした緊張をはらんでいます。歌麿と蔦重の関係は、現代の「推し活」や「職場の人間関係」にも通じる普遍的なテーマを描いていました。
「そんな悪い男やめときなよ歌麿」という声もあり、視聴者の多くは歌麿に同情的でした。しかし一方で、蔦重の状況も理解できるという声も。この複雑な感情が、視聴者を物語に引き込む力になっています。
手鏡に映る歌麿の顔——それは、自分自身と向き合い、新しい道を選ぶ決意の象徴。「美男揃え」として自画像を描くということは、歌麿が初めて「商売」ではなく「自分の表現」を選んだ瞬間なのかもしれません。
📌 まとめ
第42話「招かれざる客」の見どころと伏線をまとめます。
- 歌麿と蔦重の決裂の予感:「兄さんに」という涙の言葉と共に、西村屋へ移る決意を固めた歌麿。二人の絆は修復できるのか、今後の展開から目が離せません。
- ていの妊娠と出産のリスク:「お口巾着」と約束した二人の幸せな時間。しかし高齢出産の不安も。次回予告では出産シーンが描かれ、榊原郁恵演じる産婆も登場します。
- 定信の政治的孤立と美人画規制:「ならぬ!」と叫ぶ定信の姿は、独裁者の孤独を象徴。美人画規制が蔦重の商売にどう影響するのか、政治と文化の対立が激化します。
- 西村屋二代目・万次郎の台頭:鱗屋の息子らしい斬新なアイデアで歌麿の心を掴んだ万次郎。「美男揃え」という新企画が、物語にどんな変化をもたらすのか注目です。
- つよの死と新しい命の象徴:「おっかさんの生まれ変わり」と信じる蔦重とてい。母の教えを失った蔦重が、どう変化していくのかも重要なテーマです。
- 爆笑問題×クールポコの息抜き要素:シリアスな展開の中、「やっちまったな」で笑いを届けた新年シーン。一ツ橋治済のお忍びなど、コミカルな要素も見逃せません。
次回第43話「裏切りの恋歌」では、歌麿の裏切りが本格化し、蔦重との対立が決定的になる模様。ていの出産も描かれ、喜びと悲しみが交錯する展開に。定信の失脚も近づき、江戸の文化と政治が大きく動き出します。
歌麿の「兄さん」という呼びかけの意味、蔦重の商売人としての冷徹さ、そして二人の絆の行方——視聴者の心を揺さぶる第42話となりました。