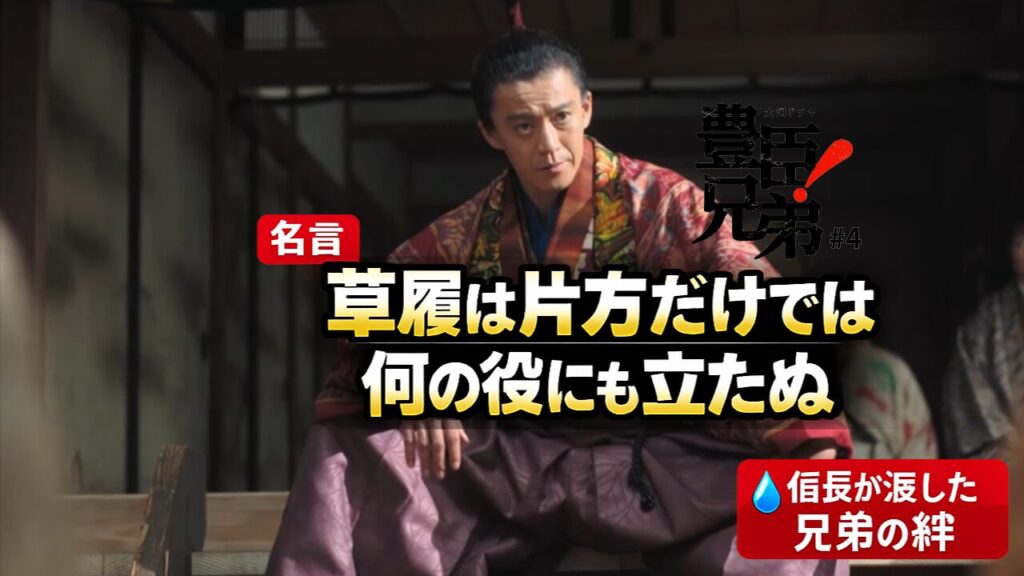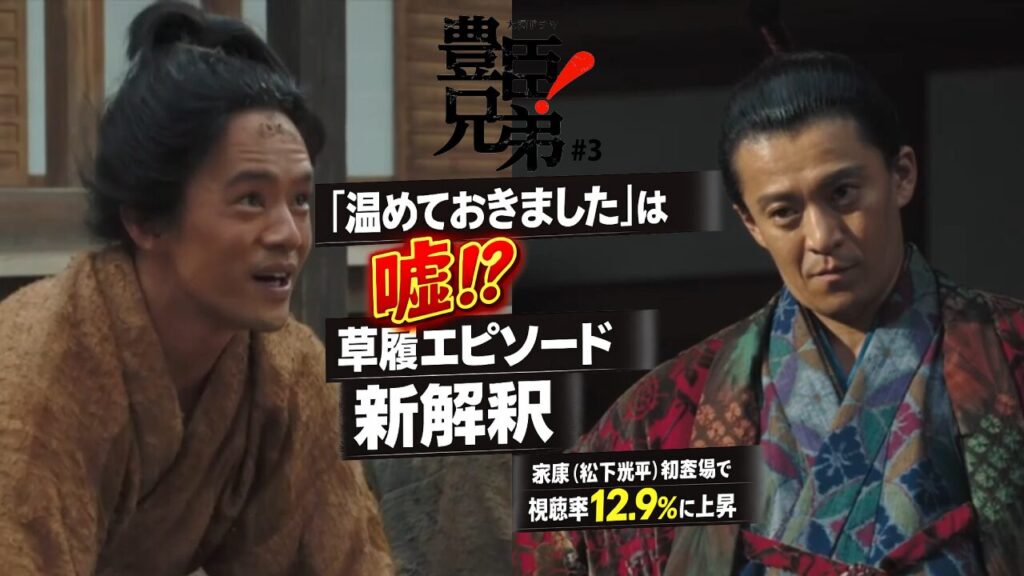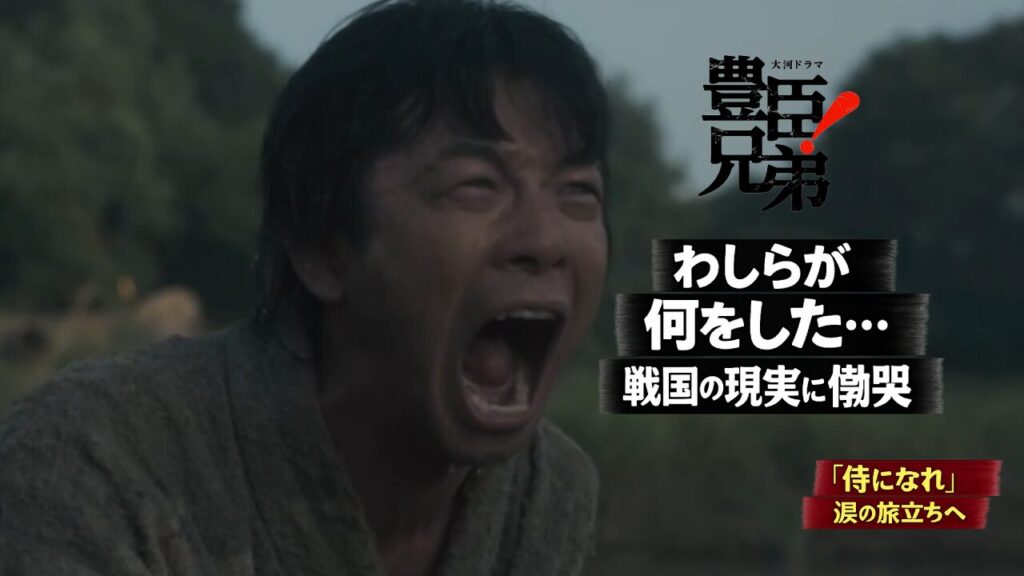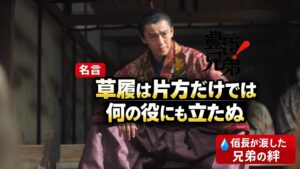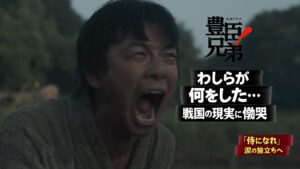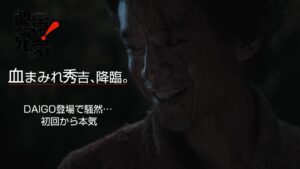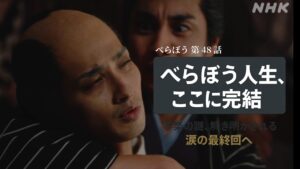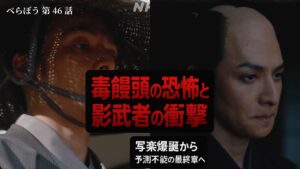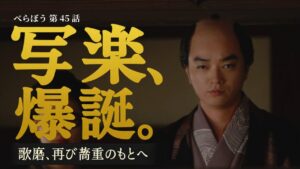大河ドラマ「べらぼう」第33話「打壊演太女功徳」が放送され、新之助(井之脇海)の衝撃的な死に視聴者が号泣。SNSでは「新さま〜!」「森下脚本容赦ない」のコメントが殺到しました。打ちこわしの混乱の中で描かれた友情と別れ、そして歌麿の絵が示す命の輝きについて詳しく解説します。
べらぼう第33話 あらすじ
天明7年5月、江戸で大規模な打ちこわしが発生。新之助らは米の売り惜しみをした米屋を次々に襲撃します。混乱する老中たちに対し、田沼意次(渡辺謙)は冷静に対応策を提言。蔦重(横浜流星)も意次のもとを訪れ、米の代わりに金を配る案を進言します。一方、一橋邸では治済(生田斗真)が定信(井上祐貴)に老中就任の正式決定を告げますが、定信は意外な反応を見せます。打ちこわしの現場では、丈右衛門だった男が再び暗躍。蔦重を狙った刃から身を挺して守った新之助が命を落とし、長谷川平蔵が敵討ちを果たします。深い悲しみに沈む蔦重のもとに歌麿(染谷将太)が現れ、新作の絵を通して命の意味を語りかけます。
新之助の悲痛な最期に視聴者涙腺崩壊!友情を貫いた忠義の死
大河ドラマ「べらぼう」第33話「打壊演太女功徳」は、視聴者の涙を誘う衝撃的な展開で幕を閉じました。天明7年5月に発生した江戸の打ちこわしを背景に、新之助(井之脇海)の命を懸けた友情が描かれ、SNSでは「新さま〜!」「こんなのってあんまりだよ」といった悲痛な叫びが溢れています。
打ちこわしの混乱が続く中、蔦重(横浜流星)がお救い銀の告知を行っていると、背後から丈右衛門だった男がナイフを持って接近します。まさに蔦重が刺されそうになった瞬間、新之助が間一髪で気づき、身を挺して庇うのです。
「これは打ち壊しだ。人を殺める場ではない」
新之助の最後の言葉は、彼の信念を物語っています。打ちこわしに参加していた新之助でしたが、暴動と殺人は別次元の問題だと考えていたのです。この台詞には、江戸時代の民衆蜂起における「道徳的な線引き」が込められており、単なる破壊活動ではない民衆の意志を表現しています。
新之助の死に込められた脚本の意図
森下佳子氏の脚本は、新之助の死を通して友情の尊さと自己犠牲の美徳を描いています。新之助は前回の放送で一度は闇堕ちしかけましたが、今回は「光の戦士」として蔦重を守り抜きました。この展開に対し、視聴者からは
「先週の闇堕ちからの、光の戦士になった新さまが…!!」
というコメントが寄せられています。
新之助の死は、蔦重にとって三度目の大きな喪失です。おふく、とよ坊に続く別れは、蔦重の人格形成に深い影響を与えることになります。
蔦重の成長を促す大きな転機
新之助の死後、蔦重は完全に打ちのめされ、墓前で虚ろな表情を見せます。しかし、この絶望こそが蔦重の成長を促す重要な転機となるのです。友を失った悲しみは、後に蔦重の出版業における人間への深い洞察力として昇華されることでしょう。
田沼意次の政治手腕が光る!打ちこわし対策と「お救い銀」の妙策
打ちこわしの報告を受けた幕閣が混乱する中、田沼意次(渡辺謙)の冷静な対応が際立ちました。意次は状況を的確に把握し、具体的な解決策を次々と提示します。
「我らの御用商人が、打ち壊しの的になっておると言っておったではないか。今から、皆身を切るのでは?」
この台詞からは、意次が打ちこわしの標的が自分の政策に関わる商人たちであることを正確に理解していることが分かります。問題の本質を見抜く政治的嗅覚の鋭さが表れています。
蔦重が意次のもとを訪れて進言したのは、米の代わりに金を配る「お救い銀」の策でした。
「素人考えなのですが、米じゃなく金は出せませんか?金ならお手元にたりしませんか?とりあえず、金を配って、その金で決まった量の米を買えるようにすりゃ、女将もちゃんと考えてくれてるってなりゃしませんか?」
意次の危機管理能力と政治的嗅覚
蔦重の提案を聞いた意次は即座にその有効性を理解し、実行に移します。この場面は意次の優れた危機管理能力を示しており、現代の政治家にも通じる実用的な政治手腕として描かれています。
「善作かもしれんな。よかった」
意次のこの反応は、蔦重の提案を高く評価していることを表しています。老中でありながら、町人の意見に耳を傾け、柔軟に政策を修正する姿勢は、意次の政治家としての器量を物語っています。
お救い銀配布の歴史的意義
お救い銀の配布は、江戸時代の社会保障制度の一環として実際に行われていました。ドラマでは、この歴史的事実を踏まえつつ、意次と蔦重の連携による政策実現として描いています。民衆の不満を武力で鎮圧するのではなく、経済的支援で解決を図る手法は、当時としては画期的なアプローチでした。
長谷川平蔵の勇姿と「丈右衛門だった男」の正体
打ちこわしのクライマックスで最も印象的だったのは、長谷川平蔵の活躍です。蔦重を狙う丈右衛門だった男を弓で射貫く場面は、まさに鬼平犯科帳を彷彿とさせる格好良さでした。
「お先手組をお出しになってはいかがでございましょう」
平蔵の進言は、事態の深刻さを物語っています。先手組は江戸城の警備を担当する精鋭部隊であり、その投入は非常事態宣言に等しい措置です。
丈右衛門だった男の正体について、蔦重は意次にこう報告しています。
「男は源内先生の屋敷に出入りしていたことを思い出しました」
この台詞から、丈右衛門だった男が平賀源内を陥れた張本人であり、今回の打ちこわしでも扇動的な役割を果たしていたことが判明します。
中村隼人が魅せる鬼平的な剣捌き
長谷川平蔵を演じる中村隼人の演技は、多くの視聴者から絶賛されました。
「鬼平かっこよかったな〜このままNHK版鬼平犯科帳が始まってもおかしくない」
というコメントが示すように、中村隼人の存在感は圧倒的でした。
平蔵が丈右衛門だった男を射貫く瞬間は、正義が悪を裁く象徴的な場面として描かれ、視聴者に大きなカタルシスを与えました。
丈右衛門だった男の暗躍と因縁の決着
丈右衛門だった男は源内先生を陥れた時から蔦重の前に立ちはだかる存在でした。今回の死により、この因縁に一つの決着がついたと言えるでしょう。しかし、その代償として新之助の命が失われたことで、蔦重の心に深い傷を残すことになります。
歌麿の『画本虫撰』が描く命の輝き―喪失から立ち直る蔦重
新之助の死に打ちのめされた蔦重のもとに、歌麿(染谷将太)が現れます。歌麿が持参したのは、新作の『画本虫撰』でした。
「命を写し取るようなもんだなって。いつかは消えていく。命を紙の上に残す。命を写すことが、俺のできる償いなのかもしれ!って思い出して」
歌麿のこの言葉は、芸術の本質について語っています。絵画が単なる美的表現ではなく、生命の記録であり、永遠への架け橋であるという思想が込められています。
蔦重は歌麿の絵を見て驚きます。
「生きてるみてえだな」
この反応は、歌麿の技法が従来とは全く異なる次元に達していることを示しています。写実的でありながら生命力に溢れる新しい画風は、後の浮世絵革命の先駆けとなるものです。
歌麿の画風変化と芸術観の深化
『画本虫撰』は実在する歌麿の作品であり、ドラマではこの史実を巧みに物語に組み込んでいます。虫という小さな生き物を通して生命の神秘を描く歌麿の姿勢は、蔦重の心境と重なり合います。
「近頃は少し、心が軽くなってきたんだよ」
歌麿のこの台詞は、芸術創作を通して自分なりの救済を見出したことを表しています。蔦重もまた、この絵を通して喪失の意味を理解し始めるのです。
新之助への鎮魂歌としての絵画
歌麿が蔦重に問いかけます。
「新さんって、どんな顔して死んだ?」
この質問に対する蔦重の答えは、新之助の生き様を肯定的に捉え直す転機となります。
「いい顔しちゃいなかったかい?」
「いい顔だったよ」
この対話を通して、蔦重は新之助の死を単なる喪失としてではなく、価値ある人生の完成として受け入れ始めます。歌麿の絵は、まさに新之助への鎮魂歌としての意味を持つのです。
一橋治済の陰謀と松平定信の意外な反応
政治的な動きも見逃せません。一橋治済(生田斗真)は定信(井上祐貴)に老中就任の正式決定を告げますが、定信の反応は予想外のものでした。
「その儀謹んでお断りしたく」
定信のこの発言は、単なる謙遜ではありません。若輩者としての自分の限界を正確に把握した上での判断です。
「そしは弱輩ご公儀のお役目を務めたこともございませぬ。老中にはなれど、ちにでは、軽んじられ、祭事を成す力などございませぬかと」
治済の駒を失った焦燥感
治済にとって「丈右衛門だった男」の死は大きな痛手でした。この駒を失ったことで、治済の陰謀は新たな局面を迎えることになります。
「目障りな本屋を消せなかったことは残念」
小説版で明かされたこの治済の心境は、蔦重への敵意が依然として強いことを示しています。
史実の天明の打ちこわしとドラマの創作性を比較
ドラマの最後に挿入された史実解説では、天明7年5月の打ちこわしが全国で同時多発的に起こったことが説明されています。
「赤坂に住む旗本が打ち壊しを行う人、人について、日記に残しています。米や大豆を盗まず、近隣へ配慮するなど、統率の取れた集団でたと記しています」
この史実とドラマの描写を比較すると、実際の打ちこわしが単なる暴動ではなく、一定の規律を持った民衆蜂起だったことが分かります。
「打ち壊しの波が江戸中へと広がる中で、米商人と幕府を糾弾する内容が書かれた旗が立てられた」
ドラマでも、この政治的メッセージ性が「筋にはのぼりなども立ち、祭政を改めよう」という台詞で表現されています。
史実では打ちこわしの鎮圧に先手組が投入されましたが、ドラマでは長谷川平蔵の活躍として脚色されています。この創作により、歴史の大きな流れの中に個人の物語を巧みに織り込んでいるのです。
今回の見どころと伏線
- 新之助の友情と自己犠牲 – 蔦重を守るために命を捧げた新之助の死は、蔦重の人生観を大きく変える転機となる
- 田沼意次の政治的手腕 – お救い銀の策を即座に実行に移す判断力と危機管理能力が際立った
- 歌麿の芸術観の深化 – 『画本虫撰』を通して表現された「命を写し取る」という新しい芸術観
- 長谷川平蔵の正義 – 丈右衛門だった男を射貫く場面は、悪への裁きと正義の勝利を象徴的に描いた
- 治済の陰謀の新局面 – 重要な駒を失った治済が今後どのような手を打つかに注目が集まる
- 定信の政治的成熟 – 老中就任を一旦辞退する姿勢に、慎重さと大局観を持った政治家としての資質が表れた