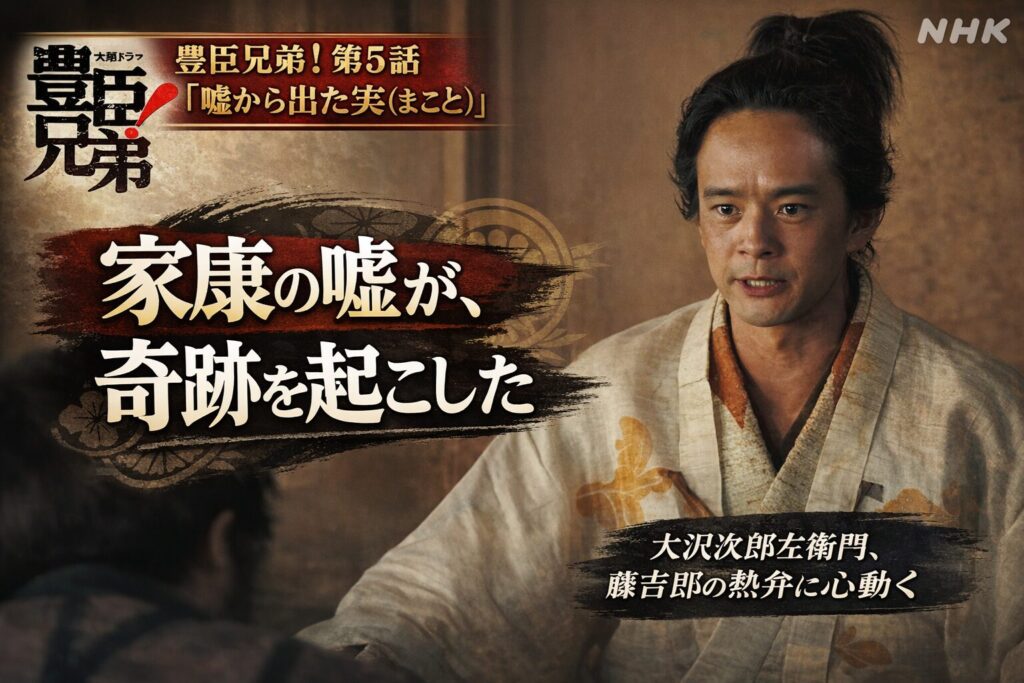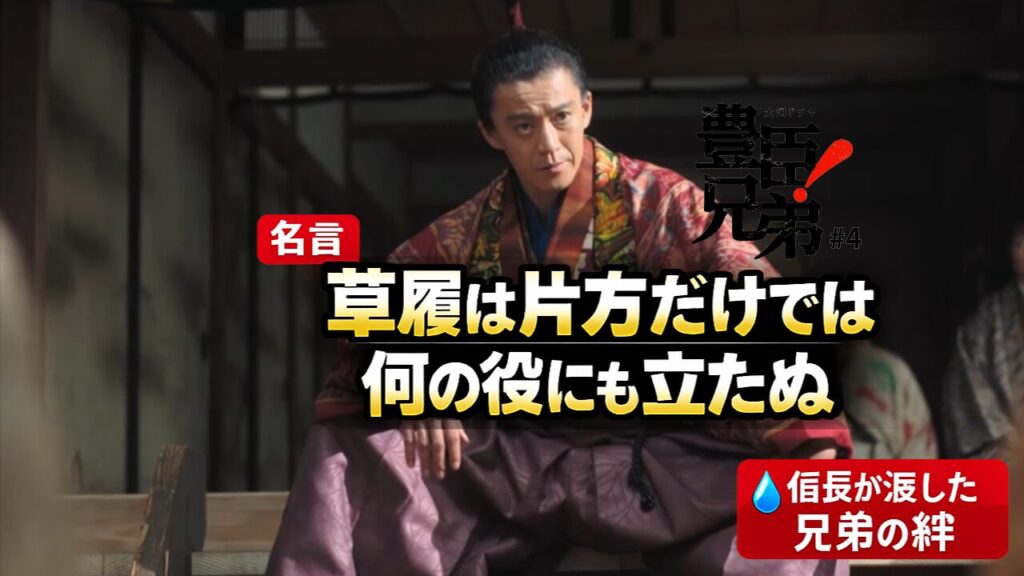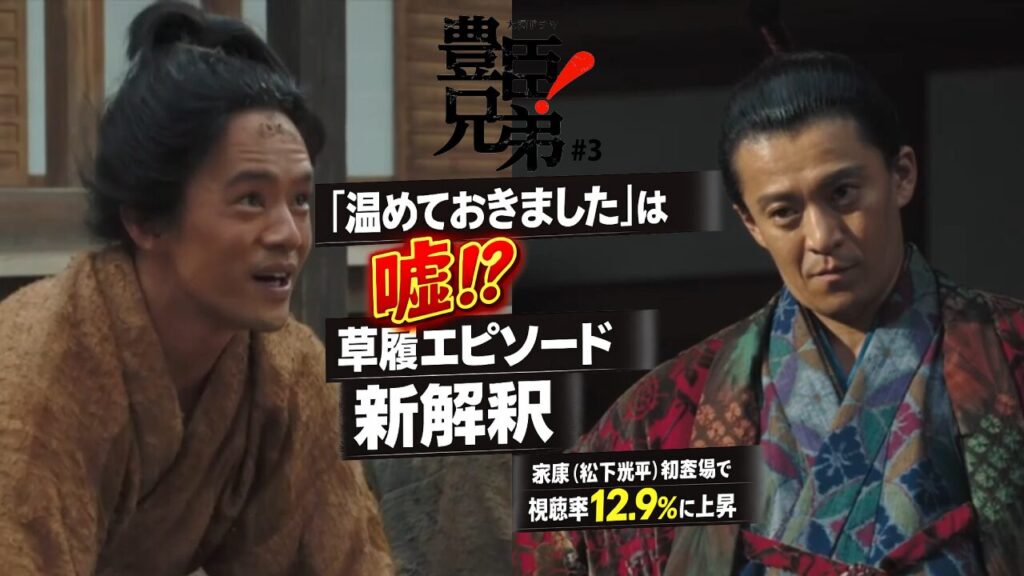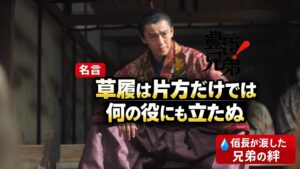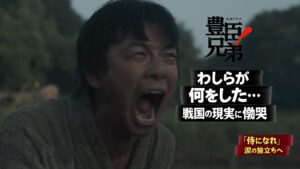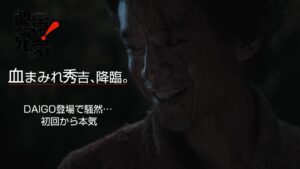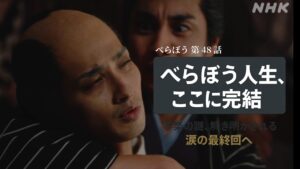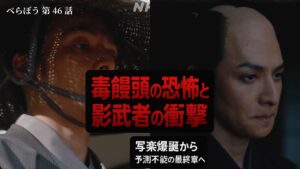松平定信(井上祐貴)の厳しい倹約令により、蔦屋重三郎(横浜流星)の黄表紙『鸚鵡返文武二道』と『天下一面鏡梅鉢』が絶版を命じられる中、恋川春町こと倉橋至は武家としての責任と戯作者としての誇りの間で苦悩します。
べらぼう第36話 あらすじ
定信から直接呼び出しを受けた春町は、家名を守るため病気を装い隠居することを決断。しかし最終的に、「豆腐の角に頭をぶつけて死ぬ」という究極のギャグで切腹を遂げ、戯作者として最後まで笑いを追求する姿勢を貫きました。
一方、蔦重は南畝(桐谷健太)からの知らせで東作(木村了)の病を知り、須原屋(里見浩太朗)らと共に見舞いに向かいます。江戸の出版界に吹き荒れる統制の嵐の中で、文人たちの友情と別れが描かれた感動的な回となりました。
春町の死を知った定信の慟哭シーンも話題となり、真面目すぎるが故の悲劇的な人物像が視聴者の同情を集めています。
恋川春町の壮絶な最期〜豆腐の角で究極のギャグ切腹〜
大河ドラマ「べらぼう」第36話「鸚鵡のけりは鴨」は、恋川春町(岡山天音)の衝撃的な最期により、視聴者に深い感動と驚きを与えました。松平定信(井上祐貴)の厳しい倹約令により出版統制が強化される中、春町は武家としての責任と戯作者としての信念の間で究極の選択を迫られることになります。
「豆腐の角に頭をぶつけて死ぬ」の衝撃
春町の最期を告げる駿河小島藩主の松平信義は、視聴者に強烈なインパクトを与えました。
「豆腐の角に頭をぶつけて、ご公儀を戦ったことに、至るとしては腹を切って詫びるべきと、恋川春町としては、死してなお、世を笑わすべきと考えたのではないかと」
という台詞は、春町の戯作者としての最後の意地を表現した名シーンです。
この演出について、SNS上では「まさかの『ナレ死』に惜別の声」「源内先生が迎えに」といった反応が多数見られました。豆腐の角で頭をぶつけて死ぬという表現は、一見ユーモラスでありながら、実際には切腹を意味する深刻な場面です。春町らしい、最後まで笑いを忘れない姿勢が込められており、視聴者の心を強く揺さぶりました。
岡山天音さんの演技も非常に印象的で、春町の複雑な心境を繊細に表現していました。武家としての誇りと戯作者としての使命感、そして死への恐怖と覚悟が入り混じった表情は、多くの視聴者の涙を誘いました。
武家と戯作者、二つの顔を持つ男の葛藤
春町の死は、江戸時代の身分制度と表現の自由という現代にも通じるテーマを浮き彫りにしました。
「某が死んでしまえば、責める先がなくなる。これ以上しつこくなりましょうし」
という春町の台詞は、自らの死によって家名を守り、同時に戯作の世界を守ろうとする彼の深い愛情を表しています。
「恋川春町は当家唯一の自慢」「そなたの筆が生き延びるのであれば、いくらでも」という殿様(尾美としのり)の言葉からは、春町の才能がいかに貴重だったかが伝わってきます。しかし春町は、家のためにも戯作界のためにも、自らの死を選択しました。
この選択について、視聴者からは「武家として戯作者としての分を、それぞれわきまえ、全うしたのではないか」という評価の声が上がっています。春町の死は、単なる悲劇ではなく、彼なりの責任の取り方だったのです。
松平定信の慟哭〜真面目すぎる改革者の悲劇〜
春町の死を知った松平定信の慟哭シーンは、第36話のもう一つの見どころでした。井上祐貴さんの迫真の演技により、定信の人間的な一面が描かれ、視聴者の同情を集めました。
倹約令がもたらした出版統制の厳しさ
定信が推し進めた倹約令は、江戸の文化活動に深刻な打撃を与えました。「これはもはや謀反も同じである」「オウムガイシ文武の二道天下1面鏡の梅鉢、絶版とする」という厳しい処分は、表現の自由への弾圧そのものでした。
定信のキャラクター再評価と視聴者の同情
これまで厳格な改革者として描かれてきた定信ですが、第36話では人間的な弱さも見せました。
「私の言うとおりにしておればよいのだ。言うとおりにすれば、うまく回るように、私は取り計らっておるのだ」
という台詞からは、彼なりの善意と責任感が伝わってきます。
しかし、その真面目さが裏目に出て、春町の死という悲劇を招いてしまいました。視聴者からは
「ファンからアンチに変わるのは一瞬? 井上祐貴”松平定信”にも同情が集まるワケ」
といった分析もあり、定信への見方が変わってきていることがうかがえます。
定信の
「そなたは、そんなことは、そもそも事業とは、宝庫をなすためのもらうものはもらいたいが、宝庫をなしたくない。では、筋が通らない」
という理想論は、現実の複雑さを理解していない指導者の典型的な発言です。真面目すぎるが故の悲劇が、視聴者の心に響いています。
蔦屋の危機と江戸文人たちの絆
第36話では、蔦屋重三郎を中心とした江戸文人たちの友情も丁寧に描かれました。出版統制という危機の中で、彼らの絆がより一層深まる様子が感動的に表現されています。
黄表紙絶版命令と蔦重の苦悩
蔦重は、自身が手がけた黄表紙が絶版を命じられ、大きな打撃を受けました。「唯一の書き手がお金で転んで黄表紙を他所で書いて 蔦重、激おこ」という視聴者の反応が示すように、蔦重の苦悩は深刻でした。
「天下の蔦屋ノリに乗って、これは1人に先生方が面白いもんあげてくださったおかげです」
という蔦重の台詞からは、作家たちへの感謝の気持ちが込められています。しかし、その作家たちが次々と筆を折らざるを得ない状況は、蔦重にとって大きな痛手でした。
朋誠堂喜三二が、
「遊びっていうのは、誰かを泣かせてまでやるこっちゃないしな」
という台詞は、娯楽の本質を的確に表現しています。朋誠堂喜三二も人々を楽しませることに真摯に取り組んでいたのです。
東作の病と友情の描写
第36話の演出と脚本の巧みさ
「べらぼう」第36話は、演出と脚本の両面で非常に優れた作品でした。特に、ナレ死という手法と歴史的背景の現代的解釈が印象的でした。
ナレ死という手法の効果
春町の死をナレーションで表現する「ナレ死」という手法は、視聴者に強い印象を与えました。直接的な死のシーンを見せるのではなく、語りによって想像させることで、より深い感動を生み出しています。
「版元の蔦屋重三郎は申しておりました。1人の、四国真面目な男が、武家として戯作者としての分を、それぞれわきまえ、全うしたのではないかと」
というナレーションは、春町の生き方を的確に要約し、視聴者の心に響きました。
この演出について、視聴者からは「豆腐の角もぶつけ方次第」「すごくかっこよかった」といった評価が寄せられており、印象的な最期として多くの人の記憶に残ったようです。
歴史的背景と現代への示唆
第36話は、江戸時代の出版統制を通じて、現代の表現の自由についても考えさせる内容でした。
「腹を切られればならぬ世とは一体誰を幸せにするのか。学問ない翻訳では、わかりかねると」
という台詞は、権力による弾圧の無意味さを鋭く指摘しています。
また、
「1つもたわけられようになっちまうんだよ。倹約倹約が行き過ぎて地獄になっちまうよ」
という庶民の声は、過度な規制や統制の弊害を表現しており、現代社会への警鐘としても読み取れます。
視聴率は7.4%と低迷していますが、内容の深さと完成度の高さから「地味だが深いテーマの再評価」を求める声も多く、質の高いドラマとして評価されています。
まとめ
第36話「鸚鵡のけりは鴨」の見どころ・伏線
- 恋川春町の壮絶な最期: 豆腐の角で切腹という究極のギャグで、戯作者としての誇りを最後まで貫いた感動的なシーン
- 松平定信の人間的描写: 真面目すぎる改革者の悲劇が描かれ、視聴者の同情を集める井上祐貴の名演技
- 出版統制の厳しさ: 江戸時代の表現規制を通じて現代の自由について考えさせる深いテーマ性
- 文人たちの絆: 危機の中でも互いを支え合う蔦重、南畝、東作らの友情が美しく描かれた人間ドラマ
- ナレ死演出の効果: 直接的でない表現により、より深い感動を生み出した巧妙な演出手法
- 歴史と現代の接点: 江戸時代の問題を現代に重ね合わせた普遍的なメッセージ性