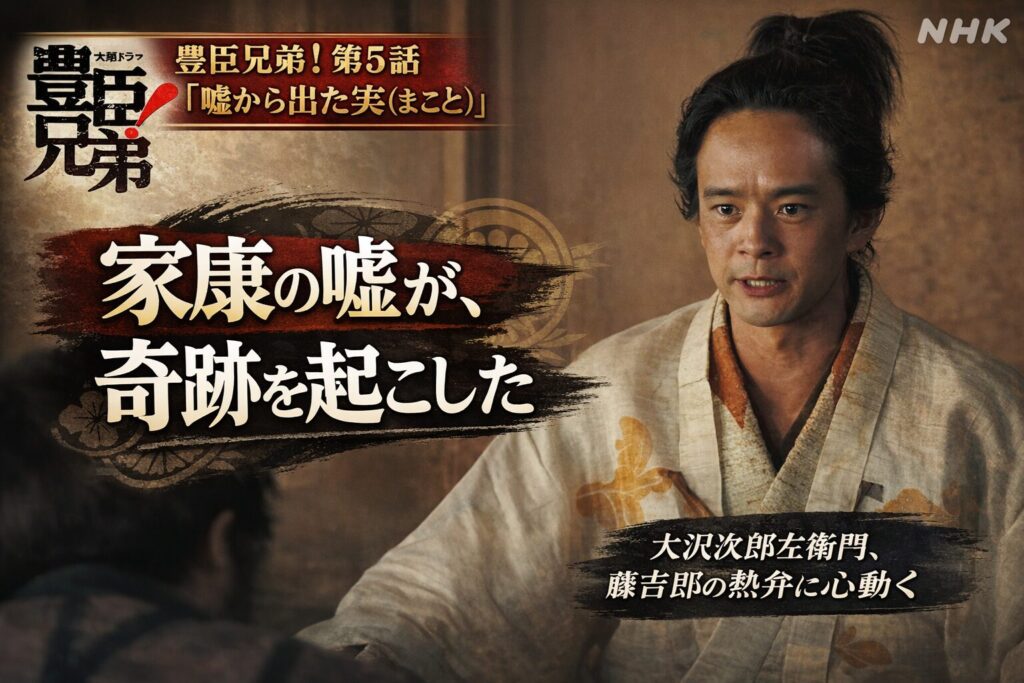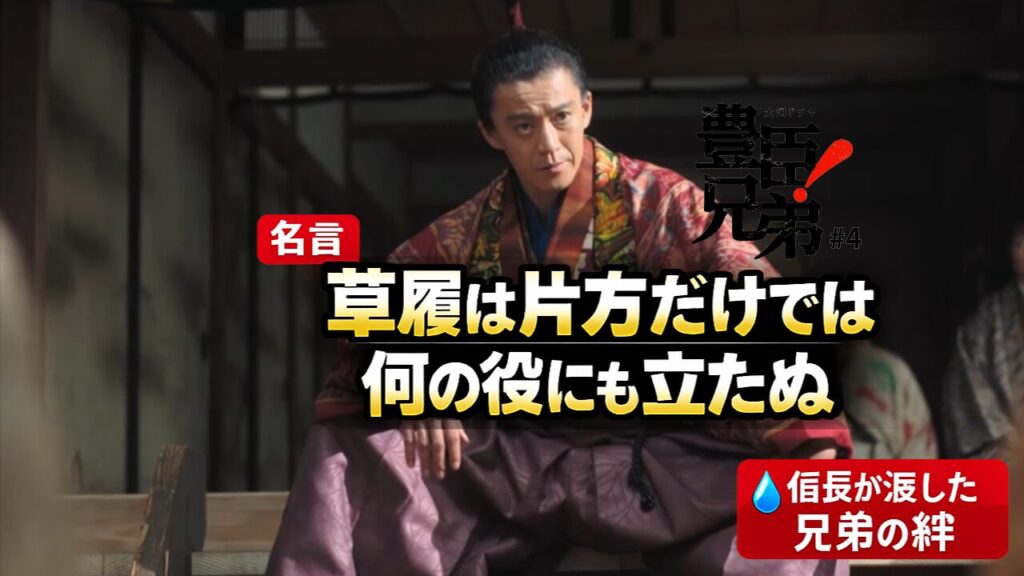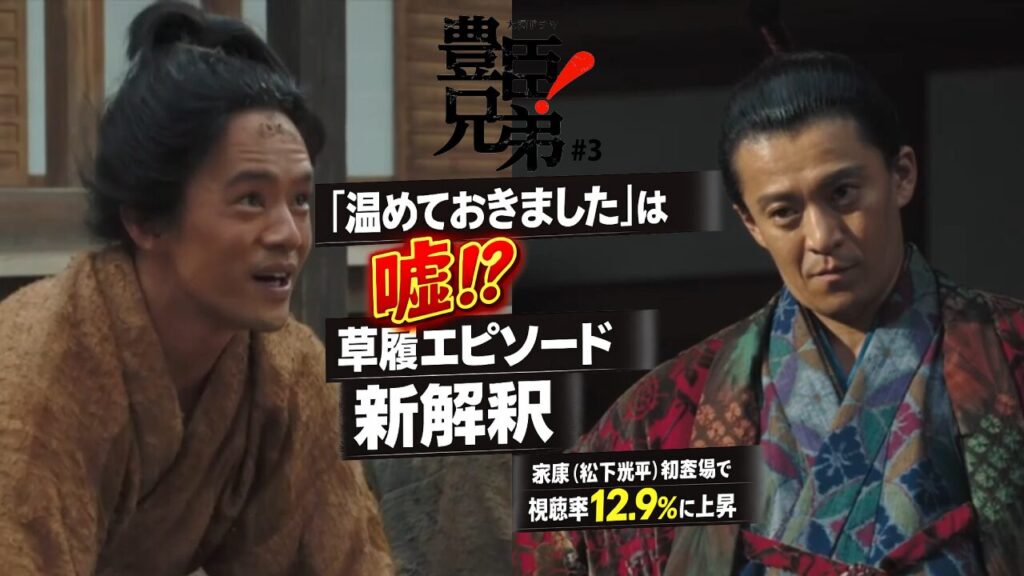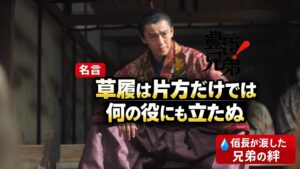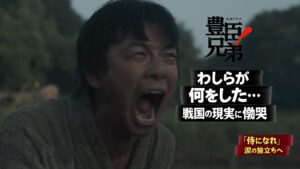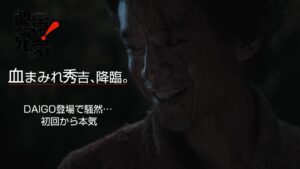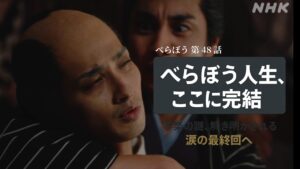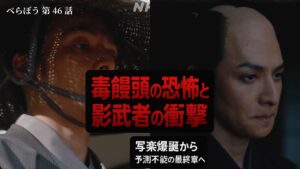大河ドラマ「べらぼう」第37話が放送され、視聴率8.9%(前回比+1.5%)を記録する中、SNSでは「涙が止まらない」「蔦重の目が怖すぎる」と話題が沸騰しています。春町先生の自害という悲劇を受け、蔦重(横浜流星)は「倹約くそくらえ!」と叫びながら吉原救済のため黄表紙出版を強行。一方、おてい(橋本愛)は「少々己を高く見積もりすぎているのでは」と眼鏡を外して蔦重を諫める衝撃の場面も。さらに、歌麿(染谷将太)の妻・きよ(藤間爽子)の足に映された不穏なあざが「梅毒では?」と視聴者をざわつかせ、京伝(古川雄大)の褌姿と「善玉悪玉」概念の誕生秘話には笑いと感動が交錯。定信(井上祐貴)の倹約政策が吉原を地獄に変える中、蔦重の孤独な闘いが始まります。
べらぼう第37話 あらすじ
春町の自害後、黄表紙を書く戯作者たちが次々と筆を折る中、蔦重は吉原を救うため新たな黄表紙の出版を決意する。一方、歌麿は栃木の豪商から肉筆画の依頼を受け、妻のきよと喜びを分かち合うが、彼女の足には不穏なあざが映される。定信は棄捐令や中洲取り壊しなど倹約政策を次々と実行し、その煽りで吉原には行き場を失った女郎たちが溢れかえる。蔦重は歌麿と京伝に絢爛豪華な吉原を描く仕事を依頼するが、おていが「己を高く見積もりすぎている」と反論。京伝は吉原の実情を描いた作品を生み出すも、蔦重自身が初めて書いた黄表紙は不評に終わる。そして京伝は「もう蔦屋では書かない」と決別を告げる。
春町の死が蔦重を変えた「倹約くそくらえ!」の叫びに込められた覚悟
戯作者たちが次々と筆を折る恐怖の連鎖
第37話は、春町先生の自害という衝撃的な出来事の余波から始まります。冒頭で蔦重がおたえに感謝の言葉を伝える場面では、春町先生の自害の回想が流れ、視聴者の胸を締め付けました。
耕書堂では営業中にも関わらず、春町先生の噂が駆け巡ります。
「豆腐の角に頭をぶつけて、なお、よう笑わすべきと考えたのではないかと」
という言葉からは、春町が最後まで笑いを追求した姿勢が伝わってきます。
日本橋の版元たちの集まりでは、戯作者たちの危機感が露わになります。
「南畝先生も筆を置かれるんですか」
「前に一度お咎めを受けておられますし、このまま続ければ、次は間違いなくご自分と南畝先生は」
という会話から、お上の締め付けがいかに深刻かが分かります。
ある版元は
「国元に戻されたんでしたっけ?」
と確認し、
「うちで書いてもらってた先生も」
と続けます。
「お武家さんは、そりゃ縮み上がっちまうよな」
という言葉には、武士階級の戯作者たちが恐怖で身動きが取れなくなっている様子が表れています。
そんな中、蔦重は
「お武家様が難しいなら、次は町方の先生たちに踏ん張ってもらいましょう」
と前向きな姿勢を見せます。そして京伝に
「これからの黄表紙はお前の肩にかかってくから」
と重責を託すのです。
蔦重が必死に京伝を説得する姿には、春町の死を無駄にしたくないという強い想いが滲んでいました。SNSでは「春町先生の死が蔦重を闇堕ちさせた」「蔦重の目が怖いくらいの演技がすごかった」との声が相次ぎ、横浜流星の演技力が改めて評価されました。
蔦重が京伝に託した「絢爛豪華な吉原」への想い
物語が進むと、蔦重は歌麿と京伝に新たな仕事を依頼します。吉原の忘八たちとの会議で、蔦重は吉原の窮状を知り、何か策を練ろうと考えます。
蔦重が家に帰って構想を練り始めると、そこへおたえがやってきます。蔦重は歌麿と京伝に
「絢爛豪華な女郎を絢爛豪華に書いてほしいんだ」
と依頼内容を伝えます。
「お前、吉原には散々世話になってる身だ」
と京伝に語りかける蔦重。
「やだとは言わないけど、お咎め受けるようなのは分かってる」
と続けながらも、
「悪いのは倹約なんだよ。倹約ばかりしてちゃ景気が悪くなり続け、皆貧乏、そのツケはつまるところ、立場の弱いやつに回されるんだ」
と熱く語ります。
ここで蔦重が叫んだのが「倹約くそくらえ!」という印象的な台詞です。この言葉には、理不尽な政策によって苦しむ人々を救いたいという蔦重の強い信念が込められていました。
「そういうことを面白おかしく伝えてほしいんだ。世にもふんどしにも」
と続ける蔦重。
「例えばよ、倹約が行き過ぎて、てめえそのものを倹約するってのはどうだ?それが流行って、最後には国から人がいなくなっちまうってな」
という企画案には、現代の少子化問題を思わせるような皮肉が効いています。
SNSでは「倹約くそくらえ!の叫びが心に刺さった」「蔦重の孤独な闘いが切ない」といった感想が多く見られました。この場面は、蔦重が春町の意志を継ぎ、さらに過激な道を突き進む決意を示す重要なターニングポイントとなりました。
歌麿の妻・きよの足に映る不穏なあざ「梅毒では?」視聴者ざわつく
肉筆画依頼で喜ぶ歌麿夫婦の幸せな日常
一方、歌麿のパートでは幸せな場面が描かれます。蔦重と歌麿が話をする中、扇屋の旦那が場を設けてくれた豪商が現れます。
栃木から来た豪商・釜屋伊兵衛は
「近ごろ黄表紙をよく読むようになりまして」
と自己紹介し、
「この先生の絵本を拝見しまして、あまりの美しさに、うちの屋敷に飾る絵をお願いできないかと」
と歌麿に肉筆画の依頼をします。
肉筆画とは、絵師が描いた一点もの。版画と違って大量生産できないため、絵師にとっては名誉ある依頼です。ナレーションでは
「値がつくだけでなく、絵師としての名も高まるものでありました」
と説明されます。
歌麿は興奮気味に
「俺がじかで描いた絵がこういうでかい子にドーンと、そうめでててこと」
と確認し、理解が追いつくと喜びを爆発させます。
家に帰った歌麿は、きよに身振り手振りで説明します。きよも耳が聞こえないながらも、歌麿の様子から内容を理解し、2人は抱き合って喜びを分かち合います。
「俺なんでもできる気がするよ」
という歌麿の言葉には、画家としての自信と妻への愛情が溢れていました。
SNSでは「肉筆Skeb頼む栃木の人、栃木すぎ」「歌麿夫婦の幸せな時間が尊い」といった温かいコメントが見られました。
カメラが映したきよの足のあざ、次回への伏線か
しかし、この幸せな場面の直後、カメラは意味深にきよの足のあざをアップで映します。明らかに視聴者に何かを示唆する演出でした。
さらに物語が進むと、歌麿と京伝が二人で話をする場面があります。おきよがお茶を持ってきてくれた際、足のあざなどが歌麿の目に入る場面も、歌麿自身もきよの異変に気づいている様子が伝わります。
京伝が
「どこできよとどこで出会ったか」
と尋ねると、歌麿は
「雨の日に、洗濯を取り込んだのが縁で」
と答えます。きよの身の上について
「親も随分前に亡くしてしまったようで、今日まで、生きてこられなかったんだよな」
と語る歌麿。
歌麿は
「なんで、身を売るしか生きるすべのない人たちにとって、遊ぶな倹約しろってやっぱり野たれ死にってことになっちまう」
と現実を指摘します。この言葉には、きよがかつて遊女だった可能性が示唆されています。
SNSでは「おきよさんの足の発疹が増えている。また次回嫌な予感しかしない。あれは梅毒なのかな」「おきよさんの足…」「歌麿夫婦は勘弁してくれんか」といった不安の声が多数上がりました。
MANTANWEB記事でも「嫌な予感”意味深”足アップ”にザワつく視聴者」と報じられ、この演出が大きな話題となりました。幸せな日常の裏に忍び寄る不穏な影が、視聴者の心を強く揺さぶったのです。
京伝の褌姿が話題爆発!「善玉悪玉」概念を生んだ天才の葛藤
蔦重との衝突
京伝(古川雄大)の活躍も第37話の大きな見どころでした。特に、蔦重に捕まって褌姿で逃げるコミカルなシーンは、SNSで「政演、まさかの褌姿で古川オタクが騒然。トート閣下が褌に!」と大きな話題になりました。
物語では、京伝が吉原の花魁のもとへ行き、花魁から渡された本を簡単に読んで何かを考える場面があります。この時、京伝は吉原のリアルな実情を目の当たりにし、後の作品創作のヒントを得ます。
その後、京伝は「仕懸文庫」という作品を完成させます。蔦重が文を読み進める場面では、険しい表情のままだった蔦重が、読み進めるうちに作品の世界に引き込まれていく様子が描かれます。
美濃吉も呼び止めて一緒に読むよう依頼すると、美濃吉がすっかり文に取り込まれ、蔦重が呼んでも気づかないほどになります。
「なんていうか、てめえが、この場にいるような気になって。俺だけじゃってことが、どうもおかしいな具合なんだよ。景色が目に浮かんできて出てくる女郎や客が動いてしゃべって」
という蔦重の感想は、京伝の作品の没入感を見事に表現しています。
蔦重は
「そこに書いてある女郎のこと、どう思った?」
と美濃吉に尋ねます。美濃吉は
「最初のお話の女郎が、ちょいと妹に似てまして」
と答え、蔦重は
「女郎をきょうだいや知り合いのように思わせる。幸せになってほしいと、これ以上の指南書はございません」
と絶賛します。
感激した蔦重が
「改めてうちで買い取らせてください」
と頭を下げると、京伝は
「お高くお願いします」
とユーモアある返答をします。この掛け合いには、二人の信頼関係が表れていました。
しかし、この後、京伝は吉原で身請けの話を受けている最中に、蔦重が乗り込んでくる場面があります。京伝が逃げ惑う中、蔦重が京伝を叩く衝撃的な展開に。京伝は
「俺もうかかねぇす」
「もう蔦屋では書かない」
と決別を告げます。
SNSでは「登場人物に感情移入させ読み手に人の幸せを願わせたり善玉悪玉のルーツを生んだ政演こと山東京伝の才に感動するも蔦重との衝突は悲しい」といった感想が見られました。
吉原ルポから生まれた名作『仕懸文庫』の誕生秘話
京伝が生み出した作品の中でも特に注目されたのが、「善玉悪玉」という概念です。ナレーションでは
「それは、善と悪魂が1人の男の体をめぐって戦う話で、しまいには善魂が勝利し、男は善人として生きていくというそれだけの話。ですが、今でも使われる善玉悪玉という言葉はここがルーツ」
と説明されます。
この作品は
「1柱の神様が推し進める正直、勤勉といった教えを見事にエンタメ化したもの」
として高く評価されました。石門心学という、京都で生まれた庶民向けの道徳の教えを、京伝が黄表紙としてエンターテインメント化したのです。
京伝は「りくつくさいことを1つの趣向とした」と序文に記しており、堅苦しい学問を笑いに変える手法で読者を魅了しました。SNSでは「善玉悪玉の概念発明は強いよ京伝」「吉原ルポってことか。さすが遊び慣れてる京伝先生だ」といった称賛の声が上がりました。
鶴屋がやってきて進学本を紹介する場面では、
「神仏の教えに、自我を折りませて、わかりやすく道徳を説いたものです」
と説明されます。この進学ブームの中で、京伝は独自の切り口で作品を生み出したのです。
しかし、この才能と引き換えに、京伝は蔦重との関係に亀裂が生じます。
「面白けりゃいいんじゃないですかね。面白いことこそ黄表紙には大事なんじゃないですかね」
という京伝の言葉は、彼の創作哲学を示すと同時に、蔦重との価値観の違いも浮き彫りにしました。
「ほんとついてるとか担いでねとかよりも、面白くなきゃ。病死は先細りになっちまうよ」
という京伝の主張は、春町の死を乗り越えて新しい表現を模索する姿勢として評価される一方、
「春町先生にあらしめていなへいられるってもんじゃです」
という蔦重の言葉とは真っ向から対立します。
おていvs蔦重、眼鏡を外した本気の対決「己を高く見積もりすぎている」
「所詮、一介の本屋に過ぎません」おていの痛烈な言葉
第37話で最も緊張感のある場面の一つが、おてい(橋本愛)と蔦重の対立シーンです。蔦重が歌麿と京伝に絢爛豪華な吉原を描く仕事を依頼していると、おたえがやってきて
「どうか書かないでくださいませ」
と頼み込みます。
「さようなものを出せば、歌麿さん、正信先生、蔦屋もどうなるか知れません。どうか書かないでください」
というおたえの言葉は、家族としての当然の心配から出たものでした。
しかし蔦重は
「あのよ、吉原は一切り24文で身を売るようなことになってんだぞ」
と反論します。ここでおたえが放ったのが、視聴者に衝撃を与えた一言です。
「申し上げにくございますが、旦那様は所詮、一介の本屋に過ぎません」
と眼鏡をはずして蔦重を見つめます。この演出が非常に印象的で、おたえの本気度を視聴者に強く印象づけました。
おたえはさらに
「立場の弱い方を救いたい、よくしたい。そのお志は分かりますが」
と前置きした上で、蔦重の限界を指摘します。
「同志向のように生きろって言ったのは、どこのどなたでしたっけ?」と蔦重がおたえの過去の言葉を引用し、
「よくするような商人になれって言いませんでしたっけ?」
と反論します。
「倒れてしまっては、志を遂げることもできませぬと申し上げております」
というおたえの主張は、極めて論理的で現実的なものでした。SNSでは「おていさんは正しいことを言う。そして戦うときは眼鏡を外す」と、橋本愛の演技と演出が高く評価されました。
蔦重の「てめえには情けってもんがねえのか」という叫び
おたえの正論に対し、蔦重は感情的に反論します。
「春町先生は、黄表紙の火を消さないために、腹まで切ったんだ。それをてめえらの保身ばっかり、恥ずかしいと思わのか?」
という言葉には、春町への強い想いが込められていました。
するとおたえは、さらに痛烈な提案をします。
「黄表紙の火が消えることをご案じなら、このようなきょう…」
と前置きし、昔の青本のように
「人の道を説く教訓を旨としたもの」
に戻すことを提案します。
「これなら、ご公儀に目をつけられることはないかと」
という現実的な解決策でした。
しかし蔦重はこの提案に激怒します。
「ふざけんじゃねぇよ。それじゃあ、春町先生は一体何のために生きてたんだって」
と叫びます。横浜流星の鬼気迫る演技が光りました。
「何だろうが、てめえには情けってもんがのが、春町先生のご行為は?」
という蔦重の言葉に対し、おたえは動じません。
「私どもに類を及ぼさないためのものでもありましたが、だからゆえに、覚悟で突き進むことは、望んでおられぬと存じます」
と冷静に返します。
この一連のやり取りについて、SNSでは「蔦重がひさびさに『べらぼうが!』と言われる展開すぎる」「でも、蔦重を『べらぼう!』とバシッと叩いてくれる人たちが軒並み退場しているのが無情すぎる」といった感想が見られました。
定信の倹約地獄が吉原を崩壊させる「一切り24文」の絶望
棄捐令と中洲取り壊しで行き場を失う女郎たち
定信(井上祐貴)の倹約政策は、第37話でさらに過激さを増します。まず実行されたのが棄捐令です。「要するに昔の特政例のようなものだ」という説明から始まり、
「札差に武家が借りた金を帳消しにさせ、武家の借金を救うのだ」
と定信が宣言します。
定信の論理は明快です。
「武家が金目当てに動くのは、そもそも金に窮しておるからだ。ならば、借金さえなくせば、本来の正しき心持ちで奉公ができる」
というものでした。
部下が
「しかし、借金を帳消しになどすれば、貸方の札差しが倒れます」
と懸念を示しますが、定信は
「やつらが倒れたり、貸し渋りを起こさぬための仕組みも考えておいた」
と自信満々です。
次に定信が実行したのが中洲の取り壊しです。
「中津のあれは田沼が作り上げた俗悪の側窟、女店物博。遊ぶところがあるから、人は遊び、無駄金を使うならば、遊ぶところをなくしてしまえばよい」
という極端な論理でした。
吉原では深刻な状況が報告されます。
「中州が取り壊しになって、岡橋も取り締まりが始まっただろう。そこの女達を吉原に放り込んできやがったのさ」
という言葉からは、定信の政策の矛盾が浮き彫りになります。
吉原側も
「店にもなってないようですけど。抱えきれる数じゃないからね」
と対応に苦慮している様子が伝わります。行き場を失った女郎たちが吉原に流れ込み、価格競争が始まったのです。
「ワッチは24も一切り24文でいいよ。あたいはもっと安くするよ」
という女郎たちの声には、生き残るための必死さが滲んでいます。
「倹約のご時世だぞ、うぬらも倹約しろ。倹約」
という客の声も聞こえ、倹約ムードが吉原全体を覆っていることが分かります。
SNSでは「緊縮倹約デフレ来たる」「結局、行き場を失くした女郎が吉原にあふれてるだけという…来たな貧乏侍」といった現代の経済問題を重ね合わせた考察が多く見られました。
「ただの大きな岡場所になる」吉原の未来への警鐘
吉原の危機はさらに深刻化します。
「倹約で物も買わなくなったろう」
という状況の中、頼みの綱だった札差しも棄捐令でやられてしまいます。
そして吉原の経営者たちから、衝撃的な提案が出されます。
「実はさ、茶屋も鍵盤もなくしちゃ、どうだって言い出す。女郎屋も出てきてて」
という言葉には、吉原のシステムそのものを崩壊させる危険性が含まれていました。
蔦重が
「茶屋や鍵盤もやめる。口利きの金が契約できれば、女郎屋はもっと安く、女郎世話できるんだろうけど、そんなことしたら、無法な力が入ってき放題で、女郎のみがどんどん危うくなりはしませんか?」
と危惧を示します。
「女郎だって、鍵盤があるから守られてるわけで」
という指摘は、吉原のシステムが単なる遊郭ではなく、女郎たちを守る仕組みでもあったことを示しています。
そして忘八が絶望的な言葉を口にします。
「これじゃあ、吉原はただの大きな丘場所。女郎は一部の夢も見られない。めっぽうでかいだけの、地獄になっちまうよ」
この「一切り24文」という価格について、SNSでは「吉原がただの『大きな岡場所』になってしまうという言葉の絶望感よ」「一切り24文で身を売る地獄」といった悲痛なコメントが相次ぎました。
定信は大奥に対しても容赦がありません。
「大奥はすでに倹約に努めております」
という報告に対し、
「鈴木越後のようかんを日使いにしておろう。ようかんなど、御膳所で作ることとすれば、1/10のかかりで済む」
と細かく指摘します。
「他にも反物やま物産経予算、まだまだ削れるところはある」
と続け、
「この通りにするがよい」
と指図書を渡す定信。大奥から
「大奥があまりに質素なのは、ご公儀の意向にかかわる」
という嘆願が出ても、定信は
「贅沢であれば、威厳があるというのは、船舶極まりない考え方」
と一蹴します。
定信が黄表紙による世論への影響も意識していることが伝わります。SNSでは「春町の死を以ってさらに倹約の鬼となる定信、対する徳川治貞の忠告は膝を打つ」と、井上祐貴の演技が高く評価されました。
一橋治済との会話では、定信の独断的な姿勢が明らかになります。治済が仮面を被りながら不気味に
「帝に太上天皇の尊号をお送りしたいという一点にございますか?あれは、認めてもよいと思うがのう」
と提案しますが、定信は
「私のほうで返答いたしておきましょう」
と断固として拒否します。
「帝の望みでも、洗礼を破ることよろしからずと、老中ともまとまりました」
という定信の言葉に、治済は
「私に遠慮するのはもうすぐいい」
と不穏な笑みを浮かべます。次の展開への伏線が張られました。
蔦重の初黄表紙は不発、京伝との決別「もう書かない」
進学本ブームの中で埋もれた蔦重の作品
蔦重は自ら黄表紙を書くことにも挑戦します。
しかし、結果は芳しくありませんでした。
「私が書いた自信作にございます。なんとかかんとか形にはなりました」
という蔦重の言葉には、苦労の跡が滲んでいます。
店頭でお客に渡すと
「今日はやめとくわ」
という反応。
「正月の縁起物もいよいよ倹約なのかね?」
という別の客の声からは、蔦重の作品が全く受け入れられていない状況が分かります。
そこへ鶴屋がやってきて、進学本を紹介します。
「あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いします。ところで、これ知ってますか?」
と持ってきたのが、京伝が大和田という本屋から依頼された進学本でした。
「神仏の教えに、自我を折りませて、わかりやすく道徳を説いたものです」
という説明に、蔦重は複雑な表情を見せます。この進学本こそが、後に「善玉悪玉」という概念を生み出す作品の元となるのです。
SNSでは「蔦重、作家デビュー」「もう春町先生をイタコしようぜ。政治思想とエンタメの狭間、現代」といったコメントが見られ、蔦重の苦戦ぶりに同情する声が上がりました。
高橋秀樹(定信の相談相手)が
「物事を急に変えるのは良くない」
と定信に忠告する場面も印象的でした。体調を崩しながらも
「急ぎすぎると、人は、その変化についてこられぬのではないか」
と指摘します。
鱗形屋と西村屋の復活、そして京伝の身請けへの予感
物語の終盤、次回予告で大きな話題となったのが、退場したはずの人気キャラクターの復活です。デイリースポーツの記事では「蔦重の正面にまさか退場したはずの人気人物いる 髪が真っ白!ネット騒然『いたよね』『蔦重助けて!』」と報じられました。
この人物とは、鱗形屋孫兵衛(片岡愛之助)と西村屋与八(西村まさ彦)です。かつて蔦重と敵対した版元たちが再び登場することが示唆されます。
SNSでは「大河3回討死退場の名優、10月大河は激レア」「髪が真っ白の姿で蔦重を助けに来る展開に期待」といった興奮のコメントが相次ぎました。
一方、京伝は吉原で身請けの話を受けています。女郎が
「先生、今年はこいつをもらってやっちゃくれないか。身代金を安くしとくから、ここから先勤めるのもきついばかりだと思うんだよ」
と提案し、
「馴染んでもう3年月の半分はここに戻られんす。それはもう女房じゃか。毎月のお小遣いももうおっかさんじゃか」
と続けます。
この幸せそうな場面に、蔦重が乗り込んできます。
「そんなふんどし担いで何考えてんだよ」
と問い詰める蔦重に、京伝は
「面白くなかったですか?」
と反論します。
蔦重は
「面白かったよ。お前、こんな面白くされちゃうな。真似してどんどんふんどし担いちまうじゃかよ。春松先生に草葉の陰から雷みたいな屁かけられっぞ」
と激怒します。
しかし京伝は
「面白けりゃいいんじゃないですかね。面白いことこそ黄表紙に一番大事じゃないですかね。ふんどしを担いでいるとか担いでねとかよりも、面白くなきゃどの道。黄表紙は先細りになっちまうよ」
と自分の信念を曲げません。
蔦重が
「戯け物は褌にあらがっていかないと、1つもたわけられようになっちまうんだよ」
と警告すると、京伝は決定的な言葉を口にします。
「これはもう、蔦重さんとこでは一切書かないです」
二人の決別が描かれます。
第37話の見どころと伏線
今回の重要ポイント
- 春町の死が蔦重を変えた: 「倹約くそくらえ!」という叫びは、蔦重が春町の意志を継ぎながらも、より過激な道を選ぶ覚悟を示した象徴的な場面でした。横浜流星の鬼気迫る演技が視聴者の心を掴みました。
- おきよの足のあざが不穏: 幸せな歌麿夫婦の日常に忍び寄る影。カメラが意味深に映したきよの足のあざは、梅毒の可能性を示唆し、「また悲劇の予感」と視聴者をざわつかせました。次回以降の展開が非常に気になる伏線です。
- 京伝の「善玉悪玉」誕生秘話: 古川雄大の褌姿がSNSで話題を呼ぶ一方、京伝が生み出した「善玉悪玉」という概念は、現代まで続く言葉のルーツとして描かれました。吉原のリアルを描いた『仕懸文庫』は、読者に登場人物の幸せを願わせる革新的な作品でした。
- おていvs蔦重の本気対決: 眼鏡を外して「己を高く見積もりすぎている」と指摘するおていの冷静さと、感情的に反論する蔦重の対比が印象的でした。橋本愛と横浜流星の演技合戦が光りました。
- 定信の倹約地獄が吉原を崩壊: 棄捐令、中洲取り壊し、大奥への倹約命令と、定信の政策は容赦なく進みます。「一切り24文」という絶望的な価格設定は、吉原が「ただの大きな岡場所」になる危機を象徴していました。
- 蔦重と京伝の決別: 「もう蔦屋では書かない」という京伝の言葉は、二人の価値観の違いを明確にしました。春町の死を乗り越える方法をめぐる対立は、創作の自由と政治的圧力というテーマを浮き彫りにしています。
次回への期待と不安
次回予告では、髪が真っ白になった鱗形屋と西村屋が復活し、蔦重を助ける展開が示唆されています。「3回討死退場の名優」の復活に視聴者は大興奮。一方、きよの病状悪化と京伝の身請けという二つの物語がどう展開するのか、目が離せません。定信と蔦重の対立も激化する中、江戸のメディア戦争はさらなる混迷を迎えそうです。視聴率8.9%を記録した第37話の勢いが、次回以降も続くことに期待が高まります。