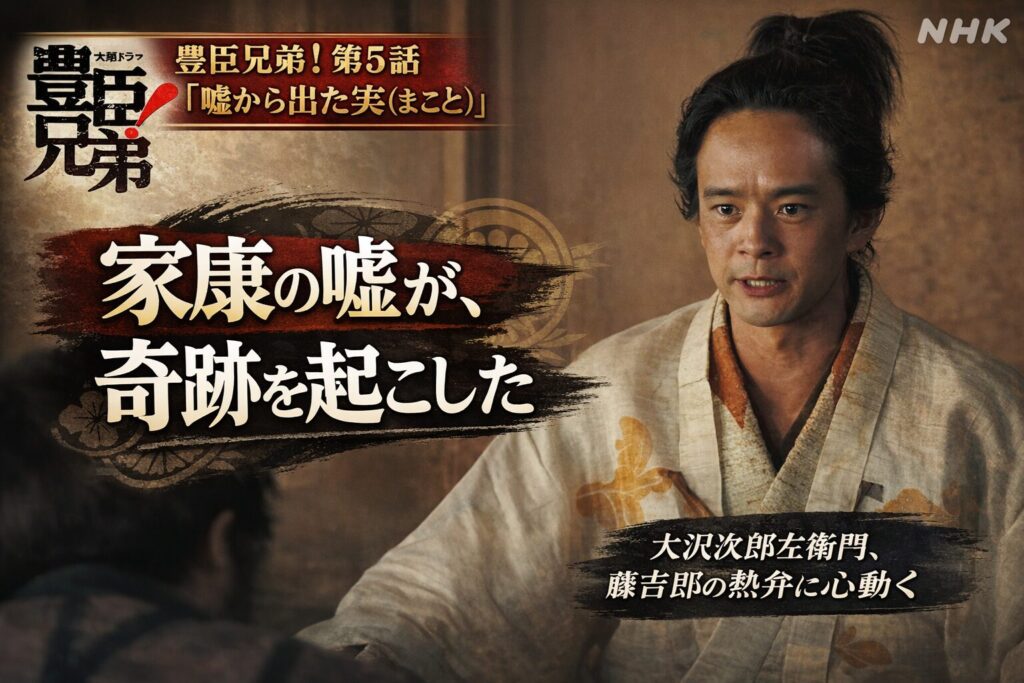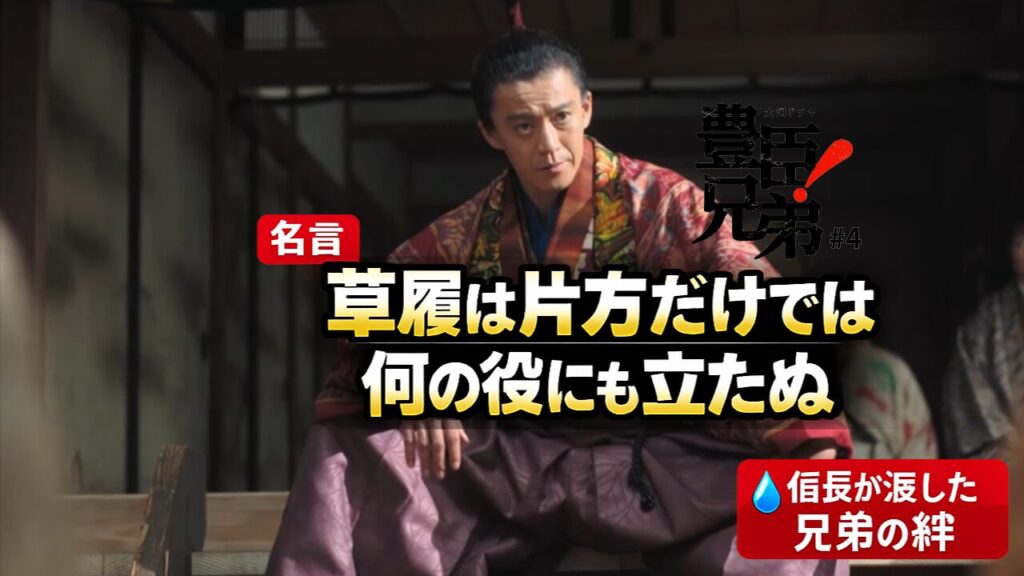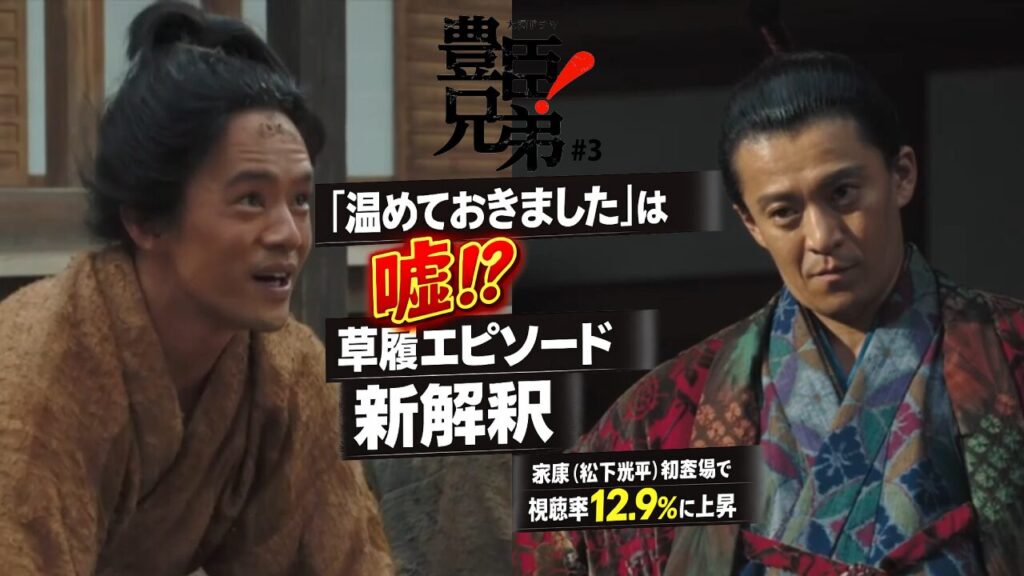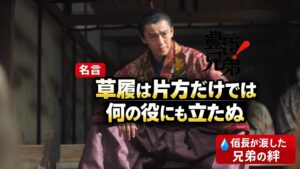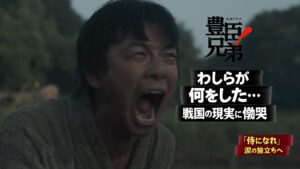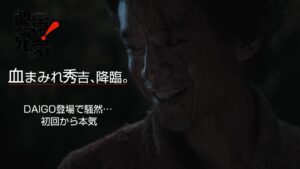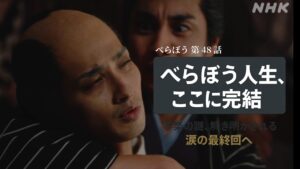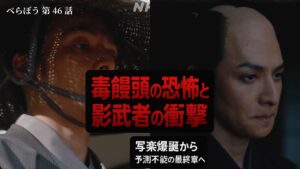大河ドラマ「べらぼう」第28話「佐野世直大明神」が2025年7月27日に放送され、SNSでは視聴者の感動と衝撃の声が溢れています。田沼意知(宮沢氷魚)が佐野政言(矢本悠馬)に斬られ命を落とす壮絶なシーンから始まり、蔦重(横浜流星)と田沼意次(渡辺謙)それぞれの「敵討ち」への決意が描かれました。
べらぼう第28話 あらすじ
田沼意知が佐野政言に斬られ、息を引き取る衝撃的な場面で幕を開けた第28話。意知の最期の言葉でたが袖(福原遥)への想いを託され、田沼意次は深い悲しみに暮れます。一方、民衆は佐野を「大明神」として崇め、田沼家への石投げが始まります。
重三郎は旧友のしんさんとふくさん夫婦に米を渡し、足抜けした二人の苦労を目の当たりにします。「切られた方が石を投げられて、切った方が拝まれるのはついていけねぇっす」という蔦重の言葉が、民衆の複雑な心情を表しています。
田沼意次は蔦重に刀を突きつけ「仇を討てるのか」と問いますが、蔦重は「筆より重いもんは持ちつけねぇんで」と答え、自分なりの敵討ちを決意します。同時に、意次も一橋治済(生田斗真)への復讐を誓い、政治的な対決が激化します。
たが袖は呪詛に取り憑かれた状態となり、視聴者に強烈な印象を残しました。
意知の最期が視聴者の涙を誘う「たが袖への想い」
第28話の冒頭から、視聴者の心を鷲掴みにしたのは田沼意知(宮沢氷魚)の壮絶な最期でした。佐野政言(矢本悠馬)の刀を受け、倒れ込む意知。その瞬間から、SNSでは涙の報告が相次ぎました。
「意知様と誰袖ちゃんが来世では一緒になれますように」の声
「意知様と誰袖ちゃんが、来世では一緒になれますように・・・」という投稿が示すように、視聴者は意知とたが袖(福原遥)の悲恋に深く心を動かされています。意知が最期に父・意次(渡辺謙)に託した言葉「身請けした女郎がいる。たが袖の話を意次にお願いする」は、恋人への最後の想いを表す痛切なセリフでした。
宮沢氷魚の渾身の演技に賞賛の嵐
宮沢氷魚の演技について、SNSでは「渾身の演技」「心に響いた」といった賞賛の声が多数上がっています。特に、手を握り合う意次と意知の父子のシーンは、多くの視聴者が涙したポイントとなりました。
このシーンで注目すべきは、回想として流れるたが袖との幸せな時間の描写です。桜の木の下で微笑み合う二人の姿は、現実の悲劇とのコントラストを際立たせ、より一層視聴者の感情を揺さぶりました。
蔦重の名言「筆より重いもんは持ちつけねぇ」に込められた意味
横浜流星と渡辺謙の魂の演技対決
今回最も話題となったセリフの一つが、蔦重(横浜流星)が田沼意次に放った
「筆より重いもんは持ちつけねぇんで」
という言葉です。意次から刀を突きつけられ「仇を討てるのか」と問われた蔦重の答えは、出版人としての矜持を表した名言として視聴者の心に強く響きました。
SNSでは
「横浜流星と渡辺謙のそれぞれの役とその立場を深く理解した魂の演技で、ものすごい見入ったし、これだから大河が好き!って思った」
という感想が投稿されており、二人の演技力の高さが評価されています。
この場面の演出も秀逸でした。夕景の赤い光の中で、蔦重の顔半分が影に沈む映像は、彼の決意の固さと同時に、これから背負う重い責任を象徴的に表現していました。
「画面の色もいい。夕景らしき赤みある光のなかで重三の顔半分は赤い影に沈む」
という観察眼の鋭い視聴者のコメントからも、この演出の効果が読み取れます。
出版人としての矜持を示した歴史的シーン
蔦重の「敵討ち」は武力ではなく、出版という文化的な手段で行われることが示唆されており、これは現代のメディアの役割にも通じる重要なメッセージを含んでいます。
治済の冷酷な策略「佐野大明神」作り上げ計画
生田斗真演じる一橋治済のサイコパス描写
一橋治済(生田斗真)の恐ろしい政治的手腕が最も際立ったのが、佐野政言を「大明神」として祭り上げる策略でした。佐野が切腹した後、民衆の間では
「佐野様が田沼の息子を切ったから米の値が下がった」
という噂が広まり、佐野は英雄視されるようになります。
SNSでは
「治斉のサイコパスっぷりが半端ない」
「政言に意知を切りつけさせ、切腹後に大明神と奉る様仕向け、田沼を堕とそうとする治済の言葉に、私の心が抉られる」
といった投稿が相次ぎ、治済の冷酷さに視聴者は戦慄しています。
政治的陰謀の恐ろしさを現代に投影
特に注目すべきは、治済の命であろう丈右衛門(仮名)が佐野の墓のある寺に「佐野大明神」という幟を立てさせ、参拝者を呼び込む計画を実行した点です。これは現代のマーケティング手法にも通じる巧妙な世論操作として描かれており、政治権力の恐ろしさを物語っています。
生田斗真の演技については「サイコパス描写が怖すぎる」という感想が多く、彼が演じる治済のキャラクター造形が視聴者に強烈な印象を与えていることが分かります。
民衆の複雑な心情「切られた方が石投げられて」
今回の放送で特に印象的だったのは、民衆の複雑な感情を表現したシーンでした。意知の葬列では、最初は人々が死を悼み手を合わせていたにも関わらず、煽動者の石投げをきっかけに一転して田沼家への攻撃が始まります。
しんさん夫婦の言葉が表す庶民の本音
蔦重の
「切られた方が石を投げられて、切った方が拝まれるのはついていけねぇっす」
という言葉は、この矛盾した状況を端的に表現した名セリフとして話題になりました。しんさんとふくさん夫婦の
「安い米が出回ってんだって」
「佐野様が田沼の息子を切ったから米の値が下がったんだろう」
という会話からは、生活に困窮する庶民の切実な思いが伝わってきます。
SNSでは
「本来ならよくも意知をぉぉぉってなるところだけど、佐野政言の事情と民衆の生活苦を入念に見せ付けられてたので無効感が残るばかり。新さん夫婦の言葉が田沼に対する庶民の偽らざる感想なのだと思う」
という深い考察も投稿されており、脚本の巧妙さが評価されています。
お口巾着と橋本愛の癒し効果
重い政治劇の中で、視聴者の心を和ませたのが「お口巾着」と呼ばれる小道具とそれを操るてい(橋本愛)の存在でした。SNSでは「お口巾着がかわいい!」といった投稿が相次ぎ、シリアスな展開の合間の癒し要素として機能していることが分かります。
重いシーンを和ませる絶妙な演出
「つったじゅ〜さ〜んの甲高い声とちょこちょこ走りで、半分出てた涙が引っ込んだ」
という投稿は、演出の絶妙なバランス感覚を表しています。
また、「今日の蔦重、ていさん夫婦は和田と巴御前なみに癒された」という投稿からは、蔦重とおていさんの夫婦関係も視聴者の心を和ませる要素として機能していることが読み取れます。
三浦庄司の怪しい動きに視聴者困惑「裏切り者説」が浮上
第28話で最も話題を集めたキャラクターの一人が、三浦庄司(原田泰造)でした。SNSでは
「やっぱり三浦庄司は治済サイドに情報流してるんすかね?その説聞いてからはもう三浦庄司の顔ばっかり見ちゃう」
という投稿が注目を集め、視聴者の間で裏切り疑惑が急浮上しています。
特に注目されたのは、蔦重が田沼意次に「敵討ち」を宣言するシーンを三浦が聞いていた点です。
「蔦重が仇討ちするって言ってたの聞いてたし、目を付けられてない?ヤバくね?」
という投稿が示すように、視聴者は三浦の今後の行動に強い不安を抱いています。
「大河で『三浦』と言えば怪しいヤツの代名詞だ」という投稿では、過去の大河ドラマ『鎌倉殿の13人』の三浦義村(山本耕史)との比較が話題になりました。大河ドラマにおける「三浦」姓のイメージが、視聴者の疑念を増幅させる要因となっています。
一方で、「息子を喪った田沼様の慟哭、それを目にして泣き崩れる三浦庄司の姿が見ていて辛い」という感想も多く、三浦の涙が本心なのか演技なのかを巡って議論が白熱しています。
「『俺にはそんな資格はないんだ』のところの表情、無理やり笑おうとしてる感じというか自嘲している感じがめちゃくちゃ切なくて」
という投稿からは、原田泰造の演技力の高さが評価されていることも分かります。
原田泰造の癒し系イメージとのギャップが話題
原田泰造の「癒し系」イメージを信じたい視聴者からは
「もう三浦はただの癒し系なんだと信じてるのに…だって三浦はあの『曲がった〜事が大嫌い〜』な原田泰造じゃないか!」
という切実な声も上がっており、キャスティングの絶妙さが話題を呼んでいます。
森下佳子脚本の巧妙さと演出技法
第28話では、森下佳子の脚本の巧妙さが随所に光りました。SNSでは「絶好調だな森下佳子」「それにしても脚本が秀逸です」といった賞賛の声が上がっています。
特に注目すべきは、政治と出版の関係性を現代的な視点で描いた点です。
「政治と書物の出版という一見離れていそうな立場でも、実は深く繋がっていてることがよくわかる」
という投稿が示すように、江戸時代の出版文化と現代のメディアの役割を重ね合わせた構成は非常に現代的で意義深いものでした。
「ザッピング」演出がもたらす緊張感
演出面では「ザッピングをかましてくるエグい演出」という表現で評されたテンポの良い編集が話題になりました。特に意知の斬撃シーンでは「最初の斬撃を鞘で受けちゃう意知」という描写で、一瞬の攻防が緊迫感を持って描かれました。
また、回想シーンの使い方も効果的で、源内の「竜こそが仕立て上げられている」という言葉が現在の状況と重ね合わされ、物語に深みを与えています。
まとめ:第28話の見どころと伏線
- 蔦重の敵討ち宣言: 「筆より重いもんは持ちつけねぇ」の名言と共に、出版を通じた闘いが本格化
- 田沼意次の復讐誓い: 一橋治済への政治的対決が激化し、権力闘争が新たな局面へ
- 治済の策略の全貌: 佐野大明神作り上げ計画により、世論操作の恐ろしさが露呈
- たが袖の呪詛: 意知の死により錯乱状態に陥り、今後の展開に不安要素
- 民衆心理の複雑さ: 生活苦からくる複雑な感情が、政治的利用される危険性を示唆
- 現代への警鐘: 江戸時代の政治と出版の関係が、現代のメディアと権力の問題に重なる構造