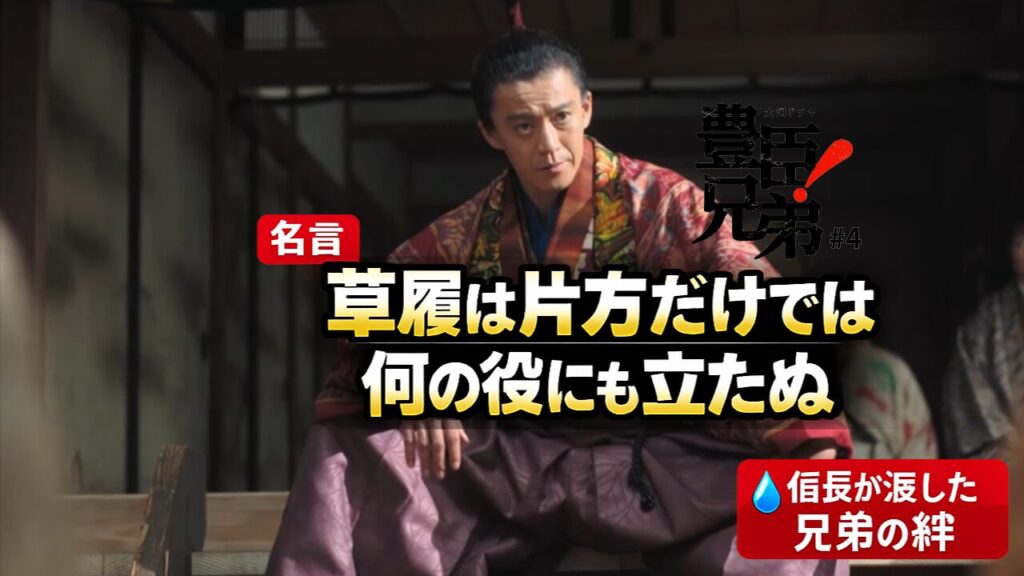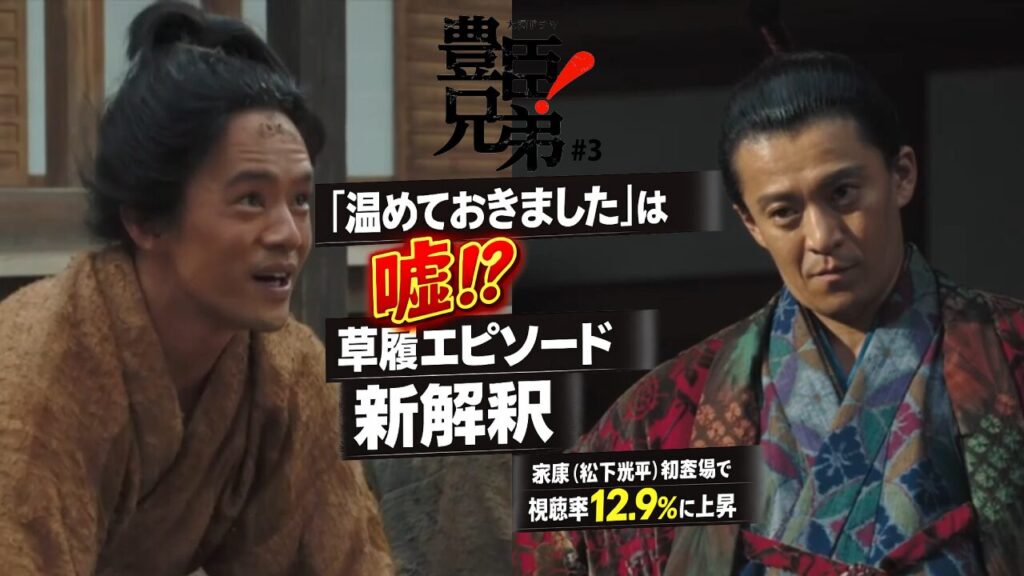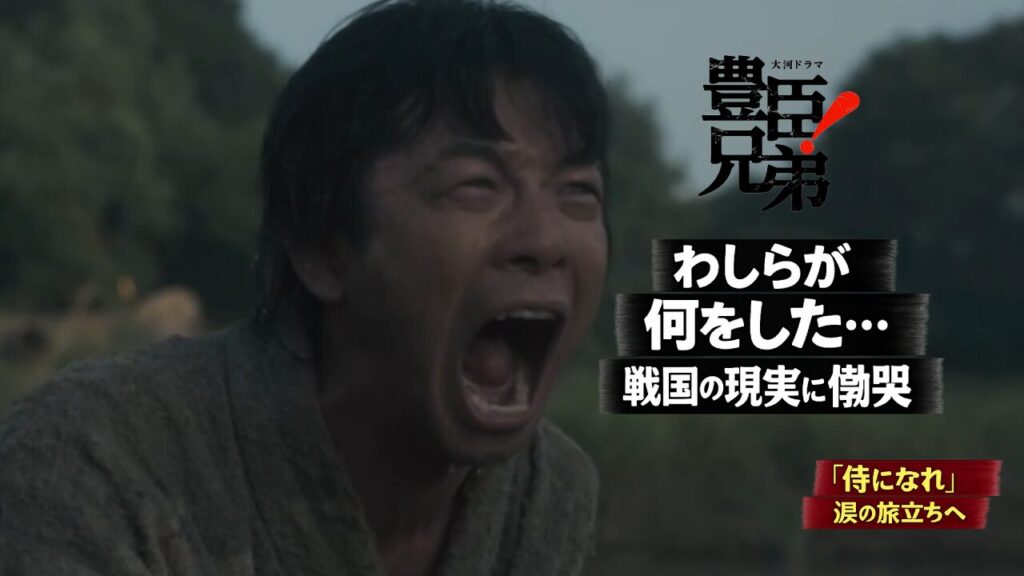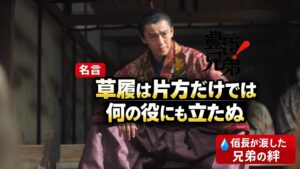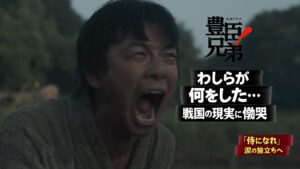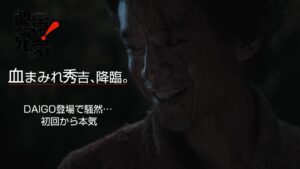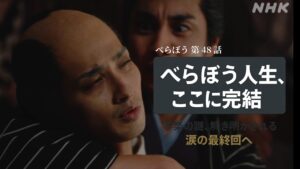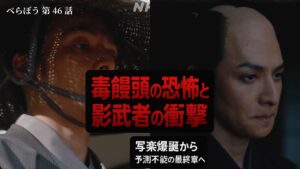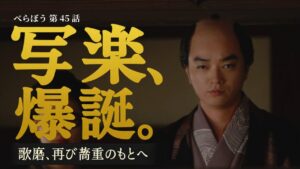大河ドラマ「べらぼう」第34話「ありがた山とかたじけ茄子」が放送され、ついに田沼意次(渡辺謙)が歴史の表舞台から去る展開となりました。新老中首座に就任した松平定信(井上祐貴)は質素倹約を掲げ、田沼派への粛清と言論統制を開始。その影響で狂歌師・太田南畝(桐谷健太)は筆を折る宣言をし、蔦重(横浜流星)の周辺にも危険が迫ります。
べらぼう第34話 あらすじ
第34話では、定信が推し進める「田沼病」撲滅政策により、江戸の空気が一変。自由闊達だった田沼時代の終焉を象徴するように、意次と蔦重は最後の対話を交わし、「ありがた山とかたじけ茄子」という言葉で絆を確かめ合います。一方、言論統制の嵐の中で蔦重は「書をもって抗う」決意を固め、定信を皮肉る豪華な狂歌絵本の制作を宣言。歌麿の「画本虫ゑらみ」を手に、最後の田沼派として抵抗する覚悟を示しました。視聴者からは田沼退場への悲鳴と、現代政治とリンクする内容への注目が集まっています。
田沼意次ついに退場!「ありがた山とかたじけ茄子」で結ばれた師弟の絆
大河ドラマ「べらぼう」第34話は、多くの視聴者が涙した回となりました。ついに田沼意次(渡辺謙)が歴史の表舞台から去る展開が描かれ、蔦重(横浜流星)との最後の対話シーンでは、二人の深い絆が「ありがた山とかたじけ茄子」という印象的な言葉で表現されました。
このタイトルの意味について、SNSでは「蔦重を”ありがた山”と呼んでいたのがここで繋がるのか」「意次が蔦重を名前で呼ばなかった理由がわかった」といった考察が多数投稿されています。実際に劇中では、意次が蔦重の手を握りながら「好きにするがいい。自らによしとして、心のままに」と語りかけ、蔦重も「ありがたい山のかんガラスにございます。」「こちらこそ、かたじけなすびだ」と応答する感動的なシーンが展開されました。
渡辺謙の最後の名演技に視聴者涙
田沼意次として物語を支えてきた渡辺謙の演技は、最後まで視聴者の心を掴んで離しませんでした。蔦重に対して
「私は先の上様のもと、田沼様が作り出した世が好きでした」
と語らせ、
「皆が欲まみれでいい加減で、でも。だからこそ、文を超えて親しみ、心のままに生きられる隙間がた」
という蔦重の思いを受け止める姿は、まさに名優の真骨頂でした。
「お前と同じ成り上がりであるからな。持たざる者には良かったのかもしれん」
という意次の言葉からは、同じ境遇の者同士として蔦重を理解し、愛情を注いできた深さが伝わってきます。Xなどでは「田沼様がいなくなったら蔦重はどうなるの?」という質問が多く寄せられており、視聴者の不安の声が上がっています。
三浦様も同時退場で「ロス」現象続出
田沼意次と同時に、三浦も退場となったことで、SNSでは「三浦様ロス」の声が続出しています。「見納め?」「つらい」といった悲鳴がX(旧Twitter)で多数投稿され、人気キャストの同日退場は大きな話題となりました。
オープニングでも変化があり、「手が蔦重を運んで日本橋に置いたら、蔦重が歩き始めてた」演出から「日本橋を歩いてた蔦重を手が運んで行った」演出に変更されており、時代の転換点を象徴する演出として注目されています。
松平定信の「田沼病」撲滅宣言!質素倹約で江戸が激変
新たに老中首座に就任した松平定信(井上祐貴)は、田沼時代の空気を一掃すべく、強力な改革に乗り出しました。劇中で定信は「田沼病」という概念を提唱し、その内容を詳しく説明しています。
「田沼病とは、斜視をやたらと憧れる病である。斜視をしたいがために、武家は恥を忘れ、マイナをもらうことに血道を上げた。商人は得を忘れ、己が儲けることばかり考え、百姓は分を忘れ、江戸に出てきた」
この痛烈な田沼批判は、現代の視聴者にも強いインパクトを与えました。定信はさらに続けて
「上から下まで己の欲を満たすことばかり考え、わがまま放題に振る舞った。その行き着いた先が、先日の打ち壊しである」
と分析し、その治療法として質素倹約を提唱します。
「ふんどし野郎」の異名を持つ新老中の正体
蔦重をはじめとする庶民たちは、定信を「ふんどし野郎」と呼んで揶揄しています。この呼び方について、劇中では
「人のふんどしで相撲を取って、ふんどしやろうじゃかなあ」
という説明があり、打ち壊しを収めたのは田沼様なのに、それをさも自分の手柄のようにして老中になったという批判が込められています。
言論統制の始まりと現代政治とのリンク
定信の政策で最も注目されているのが、言論統制の側面です。狂歌や戯作に対する弾圧が始まり、表現の自由が脅かされる状況が描かれています。この展開について、視聴者からは現代政治とのリンクを指摘する声が多数上がっています。
「お上の言いなりの記事を書くマスメディアとか、保守派の巻き返しで首相(にあたる立場の人間)失脚とか、完全に今そのものという印象。言論統制が起きた時ににどう対処するかという、今までで一番他人事と思えなかった回だった」
という投稿に代表されるように、江戸時代の出来事が現代の課題と重なって見えるという感想が多く寄せられています。
太田南畝「筆を折る」宣言の真相!狂歌一つで処罰の恐怖
狂歌師として活動してきた太田南畝(桐谷健太)が「筆を折る」と宣言したシーンは、言論統制の恐ろしさを象徴する場面となりました。南畝は定信を皮肉った狂歌を詠んだ疑いで処罰の危機に瀕しており、その具体的な内容も劇中で明かされています。
問題となった狂歌は
「世の中に、かほどうるさきものはなし。文武という」
というもので、文武と蚊の羽音をかけた洒落が込められていました。しかし南畝は
「この歌はまことそれがしの策ではございませぬ。私は人様をおとしめる歌は決して読みませぬ」
と否定します。
戯れ歌への弾圧で見せしめ効果狙い
定信側の狙いは明確でした。
「その歌をうまいと申した。それは、越中の神様を文武とうるさいかと思ってはおるということであろう。その心根は、由しきものと断ぜざるをえ」
という理論で、作者でなくても賞賛した者まで処罰対象とする方針が示されています。
この展開について、視聴者からは
「戯言一つで沙汰を待てなんてな。いけと思うんでさ。いくら何でも野暮が過ぎる」
という蔦重の言葉に共感する声が多数寄せられています。Xでは「江戸時代の言論統制はどこまで厳しかったの?」という質問も投稿されており、歴史への関心の高さがうかがえます。
文化人たちに広がる萎縮ムード
南畝の処罰は見せしめの意味が強く、他の文化人たちにも大きな影響を与えています。劇中では
「これからは狂歌読んだら咎められるかもしれないってことか?」
「ふざけりゃお縄になる夜が来ると思っています」
といった不安の声が描かれ、創作活動への萎縮効果が表現されています。
土山様の処罰についても触れられ、「見せしめだ」という認識が広がっています。この状況について、SNSでは「表現の世界にも容赦なく訪れる見せしめの嵐の中、蔦重は表現物での反撃を決意」といった投稿が見られ、主人公の決断への期待が高まっています。
蔦重「書をもって抗う」決意表明!最後の田沼派として立ち上がる
言論統制の嵐の中で、蔦重は重要な決断を下します。田沼意次との最後の対話で
「私は書を持って、その流れに抗いたく存じます。最後の田沼様の一派として、田沼様の世の風を守りたいと思います」
と宣言し、出版業を通じた抵抗の意志を示しました。
この決意について、蔦重は具体的な戦略も語っています。
「この流れに性を持って抗いてえ?と思います。皆様。力をお貸しください」
と仲間たちに呼びかけ、
「ふんどしのご聖堂をからかう奇集を出して、と思ってます」
と具体的な計画を明かします。
歌麿の「画本虫ゑらみ」が示す創作への意志
蔦重の抵抗計画の中核となるのが、歌麿(染谷将太)の作品「画本虫ゑらみ」です。実際に東京国立博物館の蔦屋重三郎展で現物を見た視聴者からは
「とんでもない精緻さで、描いた歌麿の画力も画力だけど彫師も摺師も超人技だったなあ。載ってる狂歌は下ネタもありのふざけきった内容で、その落差も凄かったりする」
という投稿が寄せられています。
劇中でも、この作品の持つ反骨精神が強調されています。蔦重は
「俺は税を尽くしたもんを作りたいんです。贅沢になって言われても欲しくて、たまんなくなるような、ものからの狂歌が」
と語り、質素倹約に真っ向から対抗する姿勢を示しています。
豪華絵本で定信政権への反撃開始
蔦重の戦略は二段構えでした。
「1つはそういう向きのき拍子を出します。それからもう1つは、倹約ばやりの世の中に、目玉が飛び出るほど、豪華な狂歌絵本を出します」
という計画で、定信の政策に対する皮肉と挑戦を込めています。
この計画について、蔦重は熱く語ります。
「税を尽くしたとは言え。俺ってのは素晴らしい遊びだと思ってまさ、意味もくだら。ただただ面白い。これぞ遊び!これぞ贅沢!しかも身1つでできる心の贅沢だ。だから上から下まで遊んだ。文を超えて、それぞれが生み出した天明の疑いです。俺はそれを守りていとおもってます」
「屁踊り」再び!仲間たちと共に挑む粋の戦い
蔦重の決意表明を受けて、耕書堂では再び「屁踊り」が始まります。このシーンは第34話のハイライトの一つとなり、視聴者からも大きな反響を呼びました。今回は南畝先生も参加し、「屁の流れが意味合いが変わって再登場し、今回は春町先生も混じってるのがアツい」という投稿が見られます。
耕書堂に響く「屁!屁!屁!」の声
静まり返った耕書堂に響く「屁!屁!屁!」の声は、この状況下では特別な意味を持ちます。SNSでは
「持つ者と持たざる者──価値観が一変する瞬間。静まり返った耕書堂に響く『屁!屁!屁!』の声が、むしろ不気味すぎて…」
という投稿があり、緊迫した状況の中での異様な光景として印象に残っています。
この踊りは単なるおふざけではなく、定信の統制に対する文化的な抵抗の象徴として描かれています。「分が悪いとわかっている戦に出陣する悲壮感が漂っている」という投稿が示すように、笑いの中にも覚悟が込められた場面となっています。
ていも参戦で結束深まる
今回の「屁踊り」では、普段は真面目なてい(橋本愛)も参加し、チーム一丸となる様子が描かれました。「戸惑うていだが、ていもその中に何とか混じる」という描写があり、視聴者からは「愛様が屁踊りを強いられていくう」といった同情の声も上がっています。
しかし、この参加は蔦重たちの結束を象徴する重要な場面でもあります。
「チーム一丸となる系のワクワク感を味わえるとは去年の今頃は全く思ってなかった」
「べらぼうサイコー蔦重サイコー」
という投稿に表れているように、視聴者も登場人物たちの団結に胸を熱くしています。
まとめ:第34話の見どころと今後への伏線
今回の見どころと伏線(箇条書き5~6個)
- 田沼意次の退場シーン:「ありがた山とかたじけ茄子」で結ばれた師弟の絆が物語の大きな転換点となり、蔦重の精神的支柱の喪失が今後の展開に大きく影響
- 松平定信の言論統制政策:現代政治とリンクする展開で視聴者の関心を集め、表現の自由をテーマとした普遍的な問題提起を実現
- 蔦重の「書をもって抗う」宣言:最後の田沼派として定信政権に立ち向かう覚悟を示し、今後の出版戦略が物語の中心軸となる予感
- 太田南畝の筆折り宣言:狂歌一つで処罰される恐怖が文化人全体に萎縮効果をもたらし、創作活動の危機的状況を象徴
- 歌麿の「画本虫ゑらみ」登場:実在の名作を通じて江戸文化の粋と反骨精神を表現し、蔦重の反撃計画の具体的な武器として機能
- オープニング映像の変更:時代の転換点を視覚的に表現し、今後の展開への期待感を高める演出効果を発揮
第34話は、田沼時代の終焉と定信時代の始まりという歴史的転換点を、現代にも通じる普遍的なテーマで描いた秀逸な回でした。蔦重の新たな戦いが始まる中で、視聴者は次回以降の展開に大きな期待を寄せています。