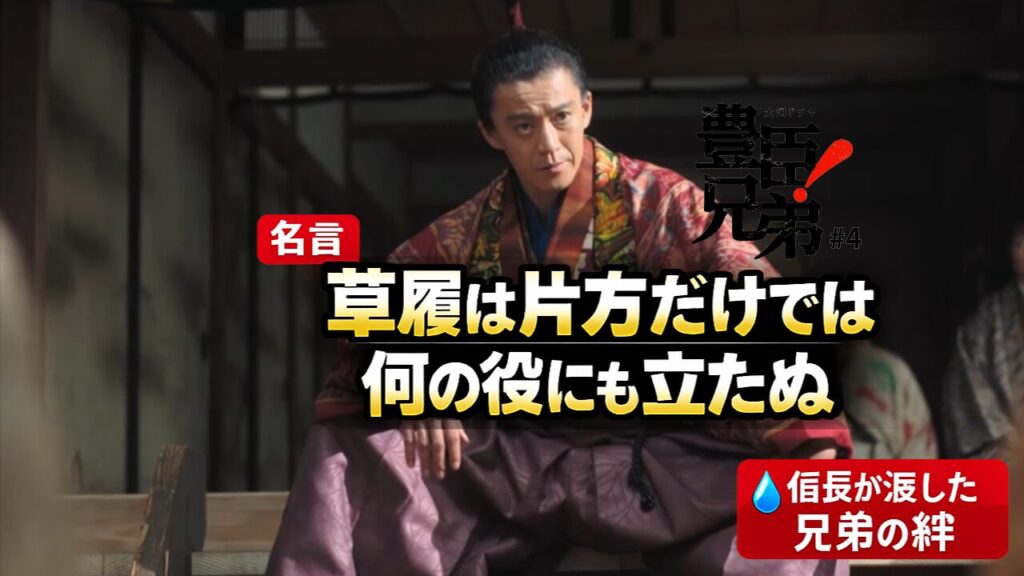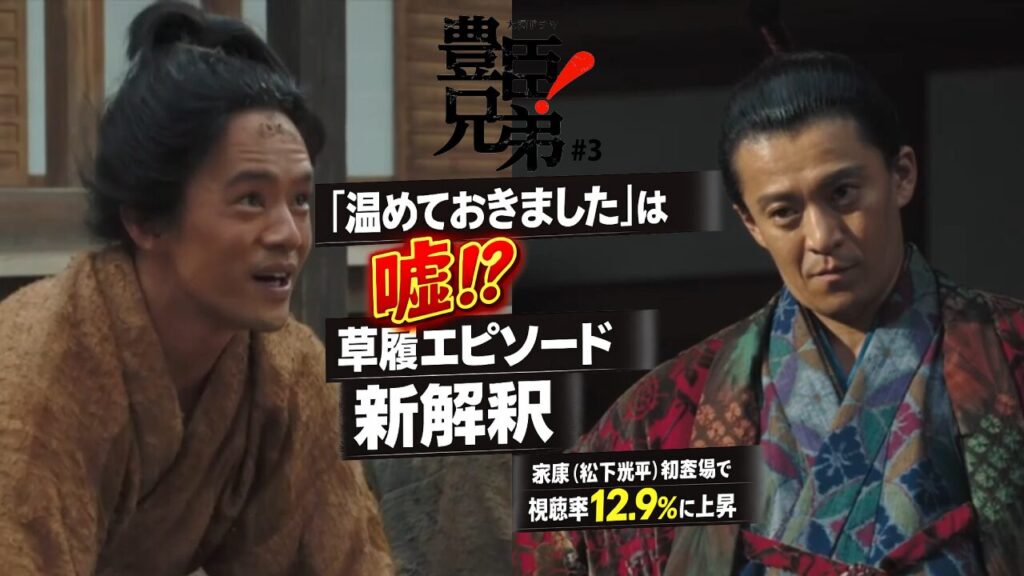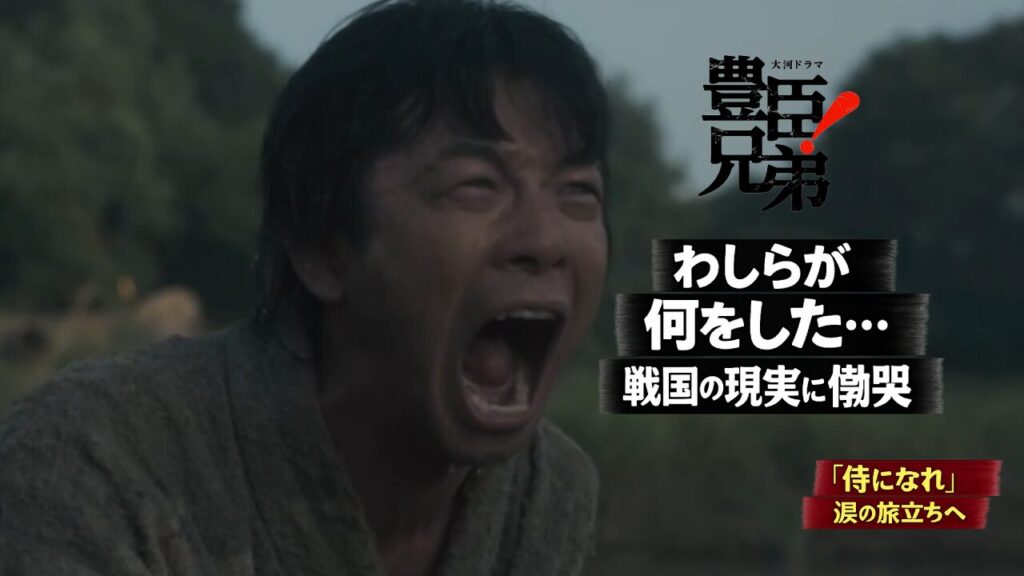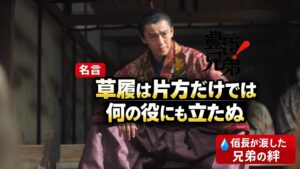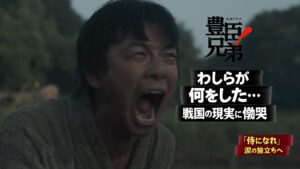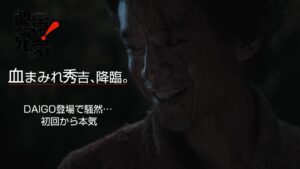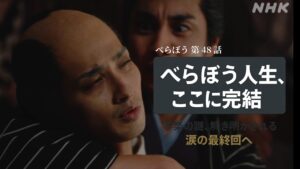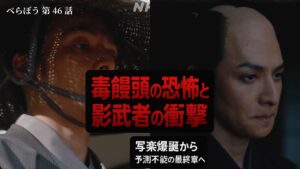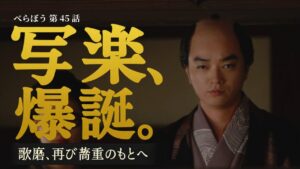大河ドラマ「べらぼう」第40話「尽きせぬは欲の泉」が放送され、SNSでは芸人キャストの怪演と歌麿復活劇が大きな話題となりました。くっきー!演じる葛飾北斎(勝川春朗)の破天荒な演技、津田健次郎が演じる曲亭馬琴(滝沢瑣吉)の毒舌、そして古川雄大演じる山東京伝のミュージカル調の歌唱が視聴者を魅了しています。本記事では、物語の流れを追いながら、印象的なセリフの意味や演出の意図、そして次回への伏線を徹底解説します。
べらぼう第40話 あらすじ
松平定信の倹約令が江戸を支配する中、蔦屋重三郎は新書半減のブームが去り、経営に苦しんでいました。起死回生を図るべく、蔦重は山東京伝に新作を依頼しますが、京伝は筆を折ると拒否します。そこへ、京伝の「友人」を名乗る滝沢瑣吉(後の曲亭馬琴)が現れ、さらに絵師・勝川春朗(後の葛飾北斎)も登場。2人は激しく対立しながらも、新たな才能として蔦屋に関わり始めます。一方、栃木で療養中の歌麿は、亡き恋人・おきよへの想いから筆を取れずにいました。蔦重は歌麿のもとを訪ね、美人大首絵という新しい挑戦を提案。歌麿の心に再び創作への欲が芽生え始めます。
定信の倹約令が江戸を締め付ける|改革路線の強化と蔦屋の苦境
物語は、松平定信の改革路線がさらに強まる場面から始まります。老中たちが定信のもとを訪れ、
「風紀の取り締まりを緩めていただけませぬか」
と懇願しますが、定信は一切聞く耳を持ちません。
「世が乱れ、悪党がはびこるのは、武士の儀器が衰えておるからだ。武士が儀器に満ち満ちれば、民はそれにならい、正しい行いをしようとする」
このセリフから、定信の理想主義的な信念が伝わってきます。武士が模範を示せば民も正しく生きるという考え方は、儒教的な徳治主義に基づいています。しかし、長谷川平蔵が苦い表情を浮かべる演出から、現場を知る役人たちがこの政策に疑問を抱いていることが示唆されます。定信は黒ごま結びの会以来の親友たちを遠ざけ、独裁色を強めていきます。
一方、蔦屋重三郎は新書半減のブームが去り、経営難に陥っていました。鶴屋南北に愚痴をこぼす蔦重は、
「身上半減か商いを取り上げてしまっては、倹約していこうというふうにはならない。半減ならば、店を潰すには惜しいとなると、おのず倹約していくことになる」
と語ります。このセリフは、定信の政策の巧妙さを示しています。完全に禁止するのではなく、半分にすることで、本屋たちに自主的な倹約を促す。蔦重自身が倹約の苦労を体験させられる皮肉な状況に、視聴者も複雑な思いを抱いたのではないでしょうか。
起死回生を図るため、蔦重は「再印本をどんどん出してみようかと」提案します。古い版木を安く買い取り、名作を揃える戦略です。しかし、その成功には山東京伝の新作が不可欠でした。
山東京伝の引退宣言と新たな才能の登場|滝沢瑣吉と勝川春朗の衝撃
蔦重と鶴屋が京伝のもとを訪れると、京伝は筆を折ると宣言します。
「手首をやられ、もう筆も持てませんので」
と言い訳する京伝に、鶴屋が
「ずいぶんと滑らかに動いておいでですけど」
とツッコミを入れる場面は、コミカルながらも京伝の心の傷を感じさせます。手鎖50日の処罰を受けた京伝は、心身ともに疲弊していたのです。
鶴屋が前金30両の返還を迫ると、京伝は仕方なく
「この方、どうです?」
「俺の代わりに、この人書けます」
と、一人の男を紹介します。それが滝沢瑣吉、後の曲亭馬琴でした。
「門人ではない、友人だ!」馬琴の毒舌に隠された自尊心
津田健次郎演じる瑣吉は、老けた顔に不遜な態度という強烈なキャラクターで登場します。京伝が
「一応、門人といいますか…」
と紹介しようとすると、瑣吉は強い口調で遮ります。
「俺が門をたたいたにもかかわらず、お前が弟子は取れない。友人で頼むと申したではないか」
このセリフには、瑣吉の強烈な自尊心が表れています。弟子という立場を拒否し、対等な「友人」であることを主張する姿勢は、後に読本作家として大成する馬琴の気質を象徴しています。京伝との師弟関係を認めず、自分の才能に絶対的な自信を持つ若き瑣吉。津田健次郎の低音ボイスがこの不遜さをさらに際立たせ、SNSでは「遊戯王級の緊張感」「ラスボス感」と評されました。
さらに、
「手代のくせに損得勘定もできるのか。この愚か者もめ!」
と店の手代として働くことを拒否する瑣吉。しかし、瑣吉の書いた原稿を読んだ蔦重は
「細かく読んでいくと、面白いとこもあるんですよ」
と評価し、その才能を認めます。
くっきー北斎の破天荒な演技|”おなら攻撃”が生んだ大河史上最大の爆笑
続いて登場したのが、勝川春朗(後の葛飾北斎)です。くっきー!が演じる春朗は、まさに破天荒そのもの。
「たら~りたらりたりらりら、たらたらしてやがんな~だんな」
と意味不明な言葉を発しながら現れ、
「滝沢瑣吉だ。俺の滝沢は、粕川と違って家宝ではないが」
と春朗を挑発します。
「クソイカだっていいたいのか?」
と応戦する滝沢に、2人は激しく言い合いになります。この場面で、春朗がおならをするという前代未聞の演出が入り、SNSでは「大河史上最も笑った」「放送コード擦れ擦れ」と大反響を呼びました。
しかし、この一見コミカルな演出には意味があります。史実の葛飾北斎は、破天荒で型破りな人物として知られており、常識を打ち破る創造性の持ち主でした。くっきー!の演技は、その北斎の本質を芸人らしい表現で昇華したものと言えるでしょう。
後に蔦重と春朗がタッグを組んだ作品について、蔦重は
「かなり京伝に寄せさせたんですが」
と語り、春朗の
「負けず嫌いなもんで。こりゃ、京伝の名で京伝よりいいもんだして、一気に抜いてやろうぜ!」
という野心が明かされます。この競争心こそが、後の北斎を大成させる原動力となるのです。
ナレーションが
「因みに、滝沢瑣吉後の曲亭馬琴このとき25、勝川春朗のちの葛飾北斎32、数々の名作を残すことになる2人はこうして出会いました」
と語る通り、馬琴と北斎の歴史的な出会いがこの回で描かれました。
歌麿の心の空白|おきよへの想いと創作への葛藤
物語の並行線として、栃木で療養中の歌麿の姿が描かれます。豪商たちに丁重にもてなされながらも、歌麿の表情には影が差しています。蔦重の母・つよが付き添い、歌麿の心を気遣います。
「もう前みたいな絵は描かない」に込められた喪失感
栃木の滞在先で、つよが歌麿に尋ねます。
「もう前みたいな絵は描かないってことかい?」
この問いに対し、歌麿は明確に答えません。しかし、その表情から、おきよを失った悲しみが創作意欲を奪っていることが痛いほど伝わってきます。おきよをモデルにした美人画は、歌麿にとって恋人との思い出そのものでした。彼女を失った今、同じような絵を描くことは、その喪失を再確認する行為に他なりません。
歌麿が虫の絵を描いている場面では、過去の師・鳥山石燕との思い出が語られます。
「鳥山石燕先生にそこら辺にあるもん書けって言われて、よくよく見ていると、同じ虫でも色が違うなとか、こいつ足が少ないとか、動きにも癖があって、おれらにはわからねぇけど、それぞれの性格や感性があるんだなって」
このセリフは、歌麿の観察眼の鋭さを示すと同時に、彼が今、小さな命に目を向けることで心の平静を保とうとしていることを暗示しています。人間を描く痛みから逃れるように、歌麿は虫という無害な対象に向き合っていたのです。
「3つ目の目に見えるものを描くんだって」
という歌麿の言葉は、単なる写実ではなく、対象の本質を捉える芸術家の姿勢を表しています。しかし、今の歌麿には、女性の本質を描く勇気がありませんでした。
蔦重の執念と美人大首絵への挑戦|「欲の泉」を呼び覚ます言葉
江戸では、蔦重が新たな企画を模索していました。役者絵や武者絵ばかりが売れる中、蔦重は
「女を出せば間違いなく目を引く。それにこの大きさ、女の大首絵なんて、見たことがだろう」
と、革新的なアイデアを思いつきます。
しかし、この大首絵を描けるのは歌麿しかいません。蔦重は栃木の歌麿のもとを訪れます。
「お前の心1つで決めてくれ」蔦重の本気の説得
再会した歌麿は、蔦重の提案を冷たくあしらいます。
「ずっと自分だけを見ていてほしいと願ってたから。」
このセリフから、歌麿がおきよへの想いを抱き続け、他の女性を描くことに罪悪感を感じていることが分かります。おきよだけを見つめていたいという願いは、創作者としての歌麿を縛る鎖となっていました。
しかし、蔦重は歌麿の心に火をつけます。
「知らねぇよ。けど、この世でいっちゃん好きな絵師は同じだからよ。お前の絵が好きなやつは、お前が描けなくなることは決して望まない。幸せだったと思うぜ。何百枚何千枚って大好きな絵師に店主に、こんなふうに書いてもらってよ」
この説得は、蔦重の商人としての計算を超えた、絵師への純粋な愛情が込められています。おきよは歌麿に愛され、その才能を一身に受けて幸せだったはずだ。だからこそ、歌麿が筆を折ることをおきよは望まないはずだ、という論理です。
そして、蔦重は最後にこう言い放ちます。
「俺がおきよさんだったら、草葉の陰で自慢しまくるぜ!なんだもんなしで、だから、お前の心1つで、お前が俺とこれをやりてえか?やりたくか?それだけで決めてくれ」
この言葉は、歌麿に決断を委ねる形を取りながらも、実は強烈な説得力を持っています。おきよの幸せを肯定し、歌麿の才能を必要とする人々の存在を示し、そして最終的には歌麿自身の欲望に訴えかける。蔦重は、歌麿の心の奥底に眠る創作への渇望、つまり「欲の泉」を呼び覚ましたのです。
江戸の美人詣でと相学ブーム|時代の流行を捉えた新発想
蔦重が美人大首絵を思いついた背景には、江戸で流行していた「相学」がありました。吉原で流行っている
「形で人の性分が分かるってやつで、お座敷にはうってつけ」
という占いのような遊びです。現代で言えば手相占いのようなものでした。
さらに、蔦重と瑣吉が「巷の美人詣で」をする場面では、
「高島屋のおせんべいは大したことないのに、この客だ!買いに来る」
というセリフが登場します。看板娘を目当てに客が集まる現象は、現代のアイドルビジネスにも通じる江戸の商法でした。
「不景気で皆、吉原など高くて行けぬ。その点、この辺の美人はタダで見られる」
この瑣吉の言葉は、庶民の娯楽としての「見る美人」の需要を的確に捉えています。蔦重はこの社会現象と相学ブームを掛け合わせ、女性の表情や性格を描き分ける大首絵というアイデアに辿り着いたのです。
歌麿が女性を観察する場面では、細かな仕草や表情の違いに注目します。
「このおきよさんは何かがあって振り返ったと思ったのよ。鳥でも飛んでたのか?見知った人でも、そう考えると、じっと見ちまうわけだ」
という蔦重の言葉は、絵を「じっと見させる」仕掛けの重要性を示しています。
さらに、
「浮気相手と一緒にいるとこ見られて、知り合いに平気の平左で嘘ついてる場面」
など、物語性のある表情を描くアイデアが次々と生まれます。ただ美しいだけでなく、見る者の想像力をかき立てる絵。それが歌麿の大首絵のコンセプトでした。
京伝の「モテのスコール」と別れの予感|ミュージカル調の演出が意味するもの
一方、京伝は煙草屋を始めるための最後の書画会を開いていました。ここで披露されたのが、古川雄大演じる京伝の歌唱シーン「モテのスコール」です。
このミュージカル調の演出は、京伝のモテっぷりと華やかさを表現すると同時に、どこか寂しさも漂わせています。女性たちに囲まれ、歌を歌う京伝の姿は、戯作者としての絶頂期を示す一方で、これが「最後の輝き」であることを暗示しているかのようです。
「タバコ入りと2足のわらじで行くことにした」
という京伝の決断は、もはや戯作だけでは生きていけない現実を受け入れたものでした。
しかし、この場面で注目すべきは、京伝が完全に筆を折るわけではないという点です。煙草屋を営みながらも創作を続ける選択は、江戸の文化人たちが生き延びるための現実的な戦略でした。定信の倹約令という逆風の中、京伝は自分なりの生存戦略を見出したのです。
次回への伏線|大首絵誕生と定信の辞職が物語を加速させる
第40話は、多くの伏線を残して終わります。
まず、須原屋市兵衛の処分です。本の内容を確認し、統制に従って販売していたにも関わらず、須原屋は処分を受け、引退を決意します。里見浩太朗演じる須原屋の重厚な演技は、出版統制の理不尽さと時代の厳しさを象徴しています。
そして、次回予告では松平定信の辞職願いが衝撃的に描かれます。家斉の嫡男・竹千代誕生の祝いの場で、定信が突然「将軍補佐と奥勤め、勝手掛の辞職」を願い出るのです。この展開は、定信の改革路線が限界に達したことを示唆しています。
歌麿と蔦重の関係も新たな局面を迎えます。「描くのは理想の女か、それとも失った面影か」という問いは、歌麿がおきよへの想いとどう向き合うかという心理的葛藤を表しています。
蔦重が考える大首絵の販促策、歌麿の創作への復帰、そして定信の政治的退場。これらの要素が次回でどう絡み合うのか、視聴者の期待は高まるばかりです。
まとめ|第40話の見どころと今後の注目ポイント
- 葛飾北斎(くっきー!)と曲亭馬琴(津田健次郎)の衝撃的な初登場 – 2人の天才の出会いが大河史上最もコミカルに描かれ、SNSで大反響
- 歌麿の心の葛藤と蔦重の熱い説得 – 「お前の心1つで決めてくれ」という言葉が、創作者の欲望を呼び覚ます名場面
- 定信の倹約令と江戸の文化人たちの苦闘 – 出版統制という時代の圧力が、新たな表現への挑戦を生む皮肉な構図
- 美人大首絵誕生の予兆 – 相学ブームと巷の美人詣でという時代の流行を捉えた蔦重の商才が光る
- 京伝の「モテのスコール」と煙草屋への転身 – ミュージカル調の演出で描かれた、戯作者としての最後の輝き
- 馬琴と北斎の対立が生む創造性 – 互いに競い合う2人の関係性が、後の大成への伏線となる
次回第41話「歌麿筆美人大首絵」では、ついに歌麿の代表作となる大首絵が誕生します。定信の辞職がもたらす政治的変化と、蔦重の新たな挑戦がどう交錯するのか。そして、おきよへの想いを抱えた歌麿が、どのような女性像を描くのか。物語はいよいよクライマックスへと向かっていきます。